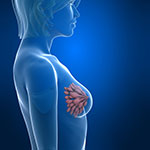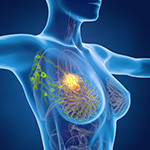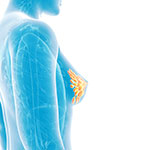提供元:CareNet.com

40歳以下の原発性乳がんの女性は、それ以降に発症した女性よりも2次原発性乳がんのリスクが高いことが、過去のデータから示唆されている。今回、米国・Harvard T. H. Chan School of Public HealthのKristen D. Brantley氏らが、片側乳房切除術または乳房温存術を受けた40歳以下の乳がん患者を対象に検討したところ、生殖細胞系列遺伝子に病的変異がない女性では2次原発性乳がんの10年発症リスクが約2%であったのに対し、病的変異がある女性では約9%と高かったことが示された。JAMA Oncology誌オンライン版2024年4月11日号に掲載。
前向きコホート研究のYoung Women’s Breast Cancer Studyには、2006年8月~2015年6月にStage0~III乳がんと診断された40歳以下の女性1,297例が登録された。そのうち、片側乳房切除術または乳房温存術を受けた685例(初回診断時の平均年齢:36歳)について、2次原発性乳がんの累積発症率とそのリスク因子を検討した。人口統計学的データ、遺伝子検査データ、治療データ、転帰データは、患者調査および診療記録から収集した。主要評価項目は 2次原発性乳がんの5年および10年累積発症率だった。
主な結果は以下のとおり。
・追跡期間中央値10.0年(四分位範囲:7.4~12.1)で17例(2.5%)が2次原発性乳がんを発症した。うち2例は乳房温存術後に同側乳房で発症した。
・原発性乳がんの診断から2次原発性乳がん発症までの期間の中央値は4.2年(四分位範囲:3.3~5.6)であった。
・遺伝子検査を受けた577例において、2次原発性乳がんの10年発症リスクは、生殖細胞系列遺伝子に病的変異のない女性では2.2%、病的変異がある女性では8.9%であった。
・多変量解析では、2次原発性乳がん発症リスクは病的変異がある患者はない患者に比べて高く(部分分布ハザード比[sHR]:5.27、95%信頼区間[CI]:1.43~19.43)、初発乳がんが非浸潤性乳がんの場合は浸潤性乳がんに比べて高かった(sHR:5.61、95%CI:1.52~20.70)。
本研究の結果、生殖細胞系列遺伝子の病的変異のない若年乳がん患者は、診断後最初の10年間に2次原発性乳がんの発症リスクが低いことが示唆された。著者らは「若年乳がん患者において、生殖細胞系列遺伝子検査で2次原発性乳がん発症リスクが予測され、治療の意思決定やフォローアップケアに役立てるために重要であることを示している」としている。
(ケアネット 金沢 浩子)
【原著論文はこちら】
Brantley KD, et al. JAMA Oncol. 2024:e240286. [Epub ahead of print]