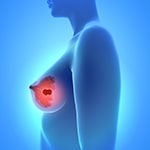提供元:CareNet.com

免疫チェックポイント阻害薬の対象とならない局所進行切除不能または転移のあるトリプルネガティブ乳がん(TNBC)の1次治療で、ダトポタマブ デルクステカン(Dato-DXd)が化学療法に比べ有意に全生存期間(OS)および無増悪生存期間(PFS)を延長したことが第III相TROPION-Breast02試験で示された。シンガポール・National Cancer Center SingaporeのRebecca Dent氏が、欧州臨床腫瘍学会(ESMO Congress 2025)で発表した。
・試験デザイン:国際共同ランダム化非盲検第III相試験
・対象:免疫チェックポイント阻害薬の対象とならない未治療の局所再発切除不能/転移TNBC
・試験群:Dato-DXd(3週ごと6mg/kg点滴静注)323例
・対照群:治験責任医師選択化学療法(ICC)(nab-パクリタキセル、カペシタビン、エリブリン、カルボプラチンから選択)321例
・評価項目:
[主要評価項目]OS、盲検下独立中央判定(BICR)によるPFS
[副次評価項目]治験担当医師評価によるPFS、奏効率(ORR)、奏効期間(DOR)、安全性
主な結果は以下のとおり。
・データカットオフ時(2025年8月25日)の追跡期間中央値は27.5ヵ月で、PFSイベントが63%に、OSイベントは54%で発生していた。被験者の再発までの期間(DFI)別の割合は、de novoが34%、0~12ヵ月が21%(0~6ヵ月は15%)、12ヵ月超が約45%であった。
・BICRによるPFS中央値は、Dato-DXd群が10.8ヵ月とICC群(5.6ヵ月)より有意に延長した(ハザード比[HR]:0.57、95%信頼区間[CI]:0.47~0.69、p<0.0001)。この傾向は、臨床的に重要なサブグループで一貫していた。
・OS中央値は、Dato-DXd群が23.7ヵ月でICC群18.7ヵ月より5ヵ月延長し、有意に延長した(HR:0.79、95%CI:0.64~0.98、p=0.0291)。この傾向はほとんどのサブグループで一貫していた。
・BICR評価によるORRは、Dato-DXd群が62.5%とICC群(29.3%)の2倍以上、完全奏効率(CR)は3倍以上であった。この傾向はすべてのサブグループで一貫していた。
・DOR中央値は、Dato-DXd群12.3ヵ月、ICC群7.1ヵ月であった。
・治療期間中央値は、Dato-DXd群(8.5ヵ月)がICC群(4.1ヵ月)の2倍以上だったが、Grade3以上の治療関連有害事象(TRAE)の発現割合は両群で同程度であり、中止率はICC群より低かった。Dato-DXd群の主なTRAEはドライアイ、口内炎、悪心であった。
Rebecca Dent氏は「本試験の結果は、免疫療法の対象とならない局所進行切除不能または転移のあるTNBC患者における新たな1次治療の標準治療としてDato-DXdを支持する」と結論した。
(ケアネット 金沢 浩子)
【参考文献・参考サイトはこちら】