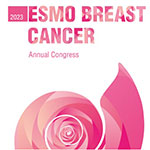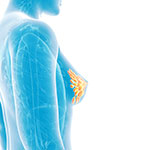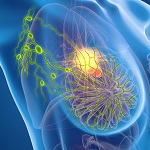提供元:CareNet.com
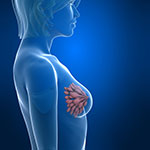
ホルモン受容体陽性の早期乳がん既往患者(42歳以下等の条件あり)において、妊娠を試みるための内分泌療法の一時的な中断は、乳がんイベントの短期リスクを増大しなかったことを、米国・ダナファーバーがん研究所のAnn H. Partridge氏らが報告した。これまで乳がん後に妊娠を試みるために内分泌療法を一時中断した女性の、再発リスクに関する前向きデータは不足していた。今回の結果を踏まえて著者は、「長期安全性の情報を確認するために、さらなる追跡調査が必要である」とまとめている。NEJM誌2023年5月4日号掲載の報告。
妊娠希望で内分泌療法を一時中断、乳がんイベント発生数を評価
研究グループは、国際多施設共同研究者主導の単群試験で、乳がんを有した若い女性で妊娠を試みるために術後補助内分泌療法の一時中断を評価した。
42歳以下、乳がんStageI、IIまたはIIIで、術後補助内分泌療法期間が18~30ヵ月の妊娠を希望する女性を適格とした。
主要評価項目は、追跡期間中の乳がんイベント(同側または局所の浸潤性乳がん、遠隔再発、対側浸潤性乳がんの発生と定義)発生数であった。主要解析は、追跡期間1,600患者年後に実施することが計画された。事前に規定した安全性の閾値は、同一期間中の乳がんイベント発生数が46件とした。
一時中断群の乳がんアウトカムを、本試験の組み入れ基準に該当すると思われた外部の女性コホート(対照群)と比較した。
63.8%が出産、乳がん再発リスクは事前規定の安全性閾値内
2014年12月~2019年12月に、516例が有効性に関する主要解析に包含された。年齢中央値は37歳、乳がん診断から試験登録までの期間中央値は29ヵ月であり、93.4%が乳がんStageIまたはIIであった。
妊娠について追跡した497例において、368例(74.0%)が1回以上妊娠し、317例(63.8%)が1人以上の生児を出産した。
追跡期間1,638患者年(追跡期間中央値41ヵ月)において、乳がんイベントを発生した患者は44例で、安全性閾値を上回らなかった。
乳がんイベント3年発生率は、一時中断群8.9%(95%信頼区間[CI]:6.3~11.6)、対照群9.2%(7.6~10.8)であった。絶対群間差は-0.2ポイント(95%CI:-3.1~2.8)、補正後ハザード比は0.81(95%CI:0.57~1.15)であった。
(ケアネット)
【原著論文はこちら】