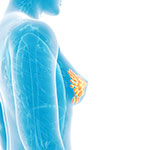提供元:CareNet.com

米国がん協会は、毎年米国における新たながんの罹患数と死亡数を推定して発表している。2023年の最新データがCA Cancer Journal for Clinicians誌2023年1/2月号に掲載された。発表されたデータによると、2023年に米国で新たにがんと診断される人は195万8,310人、がんによる死亡者は60万9,820人と予測されている。死亡者数が最も多いがん種は、男性は肺がん、前立腺がん、大腸がんの順で、女性は肺がん、乳がん、大腸がんの順であった。
がん罹患率は、がんリスクに関連する行動パターンと、がんスクリーニング検査の使用などの医療行為の変化の両方を反映する。たとえば、1990年代初頭の前立腺がんの罹患率(人口10万人当たり)の急増は、それ以前に検査を受けていなかった男性の間で前立腺特異抗原(PSA)検査が急速に広まった結果、無症候性前立腺がんの検出が急増したことを反映している。その後、高齢男性に対するPSA検査が推奨されなくなったことから罹患数は20年間減少を続けていたが、2014~19年には再度増加に転じ、2023年には9万9,000人の新規罹患者が予測されている。また、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種推進によって20代前半の女性の子宮頸がん発症率は2012年から2019年にかけて65%低下した。
全体としては、女性に比べて男性のほうが罹患率の傾向は良好だった。2015から2019年にかけての女性の肺がん罹患率の減少は男性の2分の1のペース(年1.1%対2.6%)であり、乳がんや子宮体がんの罹患率は増加を続けている。肝臓がんやメラノーマの罹患率は50歳以上の男性では安定、若年男性では減少した。結果として、性差は徐々に縮小し、がん全体の男女の罹患率比は1992年の1.59(95%信頼区間[CI]:1.57~1.61)から2019年には1.14(95%CI:1.14~1.15)まで低下した。ただし、この比率は年齢によって大きく異なり、20~49歳では女性が男性よりも約80%高い一方で、75歳以上では男性が約50%高かった。
2020年からはCOVID-19感染流行があったにもかかわらず、また他の主要な死因とは対照的に、がん死亡率は2000年代には年1.5%、2015~20年には年2%と減少を続け、1991~2020年までに33%減少し、推定380万人の死亡が回避された。この進歩は喫煙の減少、乳がん・大腸がん・前立腺がん検査の普及、そして治療の進歩を反映したもので、とくに白血病、メラノーマ、腎臓がんの死亡率が急速に減少(2016~20年には年約2%)したことや、肺がんの死亡率減少が加速したことに表れている。すべてのがんを合わせた5年相対生存率は、1970年代半ばに診断された49%から2012~18年に診断された68%に増加した。しかし、死亡率における人種格差が最も大きい乳がん、前立腺がん、子宮体がんの罹患率上昇により、今後の減少の進展は弱まる可能性があるという。
(ケアネット 杉崎 真名)
【原著論文はこちら】