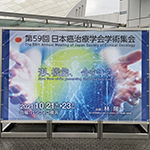提供元:CareNet.com

進行がんの高齢患者への介入として、地域の腫瘍医(community oncology practice)に高齢者機能評価の要約を提供すると、これを提供しない場合に比べ、がん治療による重度の毒性作用の発現頻度が抑制され、用量強度の低いレジメンで治療を開始する腫瘍医が増えることが、米国・ロチェスター大学医療センターのSupriya G. Mohile氏らのクラスター無作為化試験「GAP70+試験」で示された。研究の成果は、Lancet誌2021年11月20日号で報告された。
米国の40施設のクラスター無作為化試験
本研究は、患者管理上の推奨事項を含む高齢者機能評価の要約を地域の腫瘍医に提供することによる介入は、意思決定の改善をもたらし、高リスクのがん治療による重度の毒性を軽減するとの仮説の検証を目的とするクラスター無作為化試験であり、米国の40の地域腫瘍診療施設が参加し、2014年7月~2019年3月の期間に患者登録が行われた(米国国立がん研究所[NCI]の研究助成を受けた)。
対象は、年齢70歳以上、高齢者機能評価のドメイン(8項目)のうち、ポリファーマシーを除く少なくとも1つの機能障害がみられ、非治癒性の進行固形がんまたはリンパ腫(StageIII/IV)に罹患しており、4週間以内に毒性作用のリスクが高い新たながん治療レジメンを開始する予定の患者であった。
参加施設は、高齢者機能評価による介入群または通常治療群に1対1の割合で無作為に割り付けられた。介入群の腫瘍医には、Webベースのプラットフォームを用いて作成された個別の高齢者機能評価の要約と患者管理上の推奨事項が提供され、通常治療群の腫瘍医には提供されなかった。
主要アウトカムは、3ヵ月間にGrade3~5の毒性作用(NCIの有害事象共通用語規準[CTCAE]の第4版で判定)が発現した患者の割合とされた。
転倒の発生率も低下
40施設(腫瘍医156人)のうち、16施設が介入群、24施設は通常治療群に割り付けられた。患者718例が登録され、349例が介入群、369例は通常治療群であった。全体の平均年齢は77.2(SD 5.4)歳、311例(43%)が女性であった。がん種は、消化器がんが34%、肺がんが25%、泌尿生殖器がんが15%、乳がんが8%で、リンパ腫は6%だった。
ベースラインの高齢者機能評価で機能障害が認められた平均ドメイン数は4.5(SD 1.6)であり、両群間に差はなかった。介入群は通常治療群に比べ、黒人が多く(11%[40/349例]vs.3%[12/369例]、p<0.0001)、化学療法による既治療例の割合が高かった(30%[104/349例]vs.22%[81/369例]、p=0.016)。
新たな治療レジメン開始から3ヵ月以内にGrade3~5の毒性作用が発現した患者の割合は全体で61%(440/718例)であった。このうちGrade5(死亡)は5例(1%)で認められた。
Grade3~5の毒性作用が発現した患者の割合は、介入群が51%(177/349例)と、通常治療群の71%(263/369例)に比べて低く、高齢者機能評価による介入は毒性作用のリスクを有意に低減することが確認された(補正後リスク比[RR]:0.74、95%信頼区間[CI]:0.64~0.86、p=0.0001)。Grade3~5の毒性作用のうち、非血液毒性には有意差が認められたが(補正後RR:0.72、95%CI:0.52~0.99、p=0.045)、血液毒性には差がなかった(0.85、0.70~1.04、p=0.11)。
化学療法は、タキサン系薬剤やプラチナ製剤を含むレジメンが多かった。化学療法のパターンには両群間に差がみられ(p=0.011)、介入群では用量強度の低い併用療法や単剤療法、化学療法+他の薬剤(モノクローナル抗体など)、化学療法以外のレジメンの割合が高い傾向が認められた。通常治療群では、2剤併用化学療法の使用頻度が高かった。
また、介入群では、1サイクル目の用量強度が標準よりも低い治療を受けた患者が多く(49%[170/349例]vs.35%[129/369例]、補正後RR:1.38、95%CI:1.06~1.78、p=0.015)、3ヵ月間に毒性関連で減量が行われた患者は少なかったが有意差はなかった(43%[149/349]vs.58%[213/369例]、0.85、0.68~1.08、p=0.18)。6ヵ月生存率(補正後ハザード比[HR]:1.13、95%CI:0.85~1.50、p=0.39)と1年生存率(1.05、0.85~1.29、p=0.68)には差が認められなかった。
さらに、介入群では、3ヵ月以内の転倒の発生率が低く(12%[35/298例]vs.21%[68/329例]、補正後RR:0.58、95%CI:0.40~0.84、p=0.0035)、がん治療レジメン開始前に中止された薬剤の数が多かった(平均群間差:0.14、95%CI:0.03~0.25、p=0.015)。
著者は、「進行がんや加齢に伴う疾患を有する高齢患者に対し、毒性作用のリスクが高い治療レジメンを新たに開始する場合は、高齢者機能評価とこれに基づく患者管理を、標準治療として考慮すべきである」としている。
(医学ライター 菅野 守)
【原著論文はこちら】