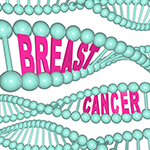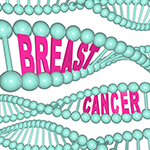提供元:CareNet.com

非浸潤性乳がん(BCIS)患者は浸潤性乳がんリスクが高いという報告があるが、乳がんを除く浸潤性がんの潜在リスクに関する報告は一致していない。今回、スイス・チューリッヒ大学のNena
Karavasiloglou氏らが、組織的なマンモグラフィ検診プログラムのないチューリッヒ州におけるBCIS患者のデータを調査したところ、BCIS患者は一般集団に比べ、浸潤性乳がんは6.85倍、乳がんを除く浸潤性がんは1.57倍、リスクが高いことが示された。また、70歳以上でのBCIS診断が乳がんを除く浸潤性がんのリスクと関連していたが、浸潤性乳がんとは関連していなかった。Frontiers
in Oncology誌2021年3月18日号に掲載。
2003~15年に初めてのがんの診断が原発性のBCISであったチューリッヒ州在住の女性1,082例のデータを調査した。原発性のBCIS患者における浸潤性乳がんまたは乳がんを除く浸潤性がんのリスクを、成人女性集団の対応リスクと比較するため、標準化罹患比(SIR)を計算した。SIRは全体および患者と腫瘍の特徴ごとに計算した。Cox比例ハザード回帰モデルを使用し、その後の浸潤性乳がんまたは乳がんを除く浸潤性がんの潜在的な危険因子(診断時の年齢、治療など)を調査した。
主な結果は以下のとおり。
・BCIS患者は一般集団と比較して、浸潤性乳がんと診断されるリスクが6.85倍(95%CI:5.52~8.41)高かった。また、乳がんを除く浸潤性がんのリスクは1.57倍(同:1.12~2.12)高かった。
・SIRは、浸潤性乳がんおよび乳がんを除く浸潤性がんのどちらも、BCIS診断時50歳未満の患者で高かった。
・70歳以上でのBCIS診断は、その後の乳がんを除く浸潤性がん診断と有意に関連していた。
これらの結果は、これまで報告されているBCIS患者のがんリスク増加を裏付けている。著者らは、「今後の研究が、BCISに続く浸潤性がんの危険因子を確立し、この集団における集中的なモニタリングの必要性を強調し、遠隔転移を全身療法で予防可能なBCIS患者を区別するのに役立つだろう」としている。
(ケアネット 金沢 浩子)
【原著論文はこちら】