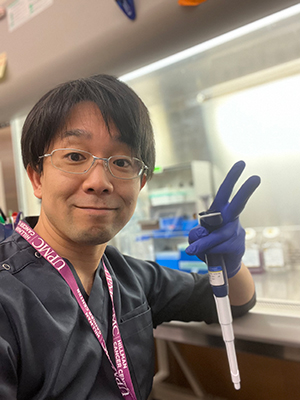[レポーター紹介 ]
寺田 満雄(てらだ みつお)

2013年 3月 名古屋市立大学医学部医学科 卒業
2013年 4月 蒲郡市民病院(臨床研修医)
2015年 4月 名古屋市立西部医療センター 外科(外科レジデント)
2017年 4月 愛知県がんセンター 乳腺科(レジデント)
2019年 4月 名古屋市立大学大学院 医学研究科 乳腺外科学分野(臨床研究医)
名古屋市立大学大学院 医学研究科 博士課程
2019年 6月 名古屋大学 分子細胞免疫学 (特別研究員)(上記と兼務)
2022年10月 名古屋市立大学大学院 医学研究科 乳腺外科学分野(病院助教)
2023年 8月 Department of Medicine and UPMC Hillman Cancer Center
(Post-doctoral associate)
2023年 9月 名古屋市立大学大学院 医学研究科 乳腺外科学分野(研究員)(上記と兼務)
ラボでの分業、実際どうやっている?
よく海外のラボは分業がしっかりされているという話を渡米前に聞いていましたが、実際そのように感じることも多く、その点を中心に実際の研究環境についてお伝えします。Hassane Labは、ポスドクが私を含めて3人、PhD studentが2人、Technicianが2人、バイオインフォマティシャンが1人、あとは実験の方針などを相談できる上司が2人とPIで構成されています。

自宅マンション前の風景。ピッツバーグの冬は雪も多く、寒いです。
日々、たくさんの臨床試験の検体がラボに運ばれてきますが、それらの処理は基本的にTechnicianが担当しています。腫瘍や生検や手術検体を処理して、scRNA-seqのライブラリー作成までもTechnicianの仕事になっています。これらの行程は非常に時間がかかりますが、ある意味では単純作業なので、Researcherは極力実験などに集中するように、との方針です。
Researcherは1人が2つほどのプロジェクトを掛け持ちしています。研究の進捗は毎週月曜日にあるResearch meetingで進捗報告をしながら方針を決めていきます(毎週、この準備が非常に大変なのですが…)。基本的には1人で実験をしますが、大きな実験をするときにはラボ中のメンバーが協力して行います。日本でPhD studentだった頃も、実験は1人でやることが多かったこともあり、つい全部1人でやってしまいそうになるのですが、「Mitsuoは人の手伝いはするけど、誰かに手伝いをお願いするのが苦手だから、ちゃんと必要な時は言って」と言われたり…ですが、それぐらいには、お互いの協力体制があるのだと思います。むしろ1人ですべてやることでミスが増える、という認識のようです。
もう1つ効率化されていると感じたのが、データの管理です。実験データや実験のプロトコル、臨床試験のデータベースなどはすべてクラウド管理をしており、過去データも含め、誰でも確認できるようになっています。またSlackも有効活用されていて、ミーティング以外での情報共有はほぼすべてSlack上で行われています。個人的にはミーティングを重ねるよりも、こちらの方が全体を把握しやすくて好みです(英語が堪能でない私には文章の方が言いたいことも言いやすいし、理解もしやすい)。
大切なのは、“1人で抱え込まずにプロジェクトを進める姿勢”

メラノーマのチャリティマラソンにラボメンバーと家族で参加。
ラボ内には、scRNA-seqやVISIUM用の機器は揃っていますが、それ以外はどこにでもあるような最低限の機材のみで、ラボのスペース自体は意外と広くありません。施設として特徴的なことは、共通機器が非常に充実していることです。UPMC Hillman Cancer CenterはUniversity of Pittsburghの医療群の1施設です。なかでも免疫学の研究には力をいれており、免疫学だけで1つの研究棟があるぐらいです。実験を行う過程で、さまざまな実験手法や解析手法を用いることになりますが、困った時には共通機器を管理している部門で、機器の使用方法から解析の方法を相談することができます。また、たとえば多重免疫染色を行う際には、染色の条件検討など非常に時間がかかることも多いですが、サンプルと抗体を渡すことで一括して条件検討から染色までを担ってくれる部門もあります。これは非常に助かります。
このように、ラボ内だけでなく、大学内でも効率的な分業がされていると言えます。自施設内だけでなく、NIHなどの他施設との共同研究も積極的に行っており、1人で抱え込まずに、内へも外へも借りられる手は借りてプロジェクトを進める姿勢が大切だと痛感します。実際問題、やりたいことに集中できる環境というのは、残念ながら日本ではあまり多くはないように思いますので、一番ギャップを感じる部分でもあります。
バックナンバー