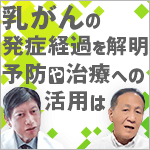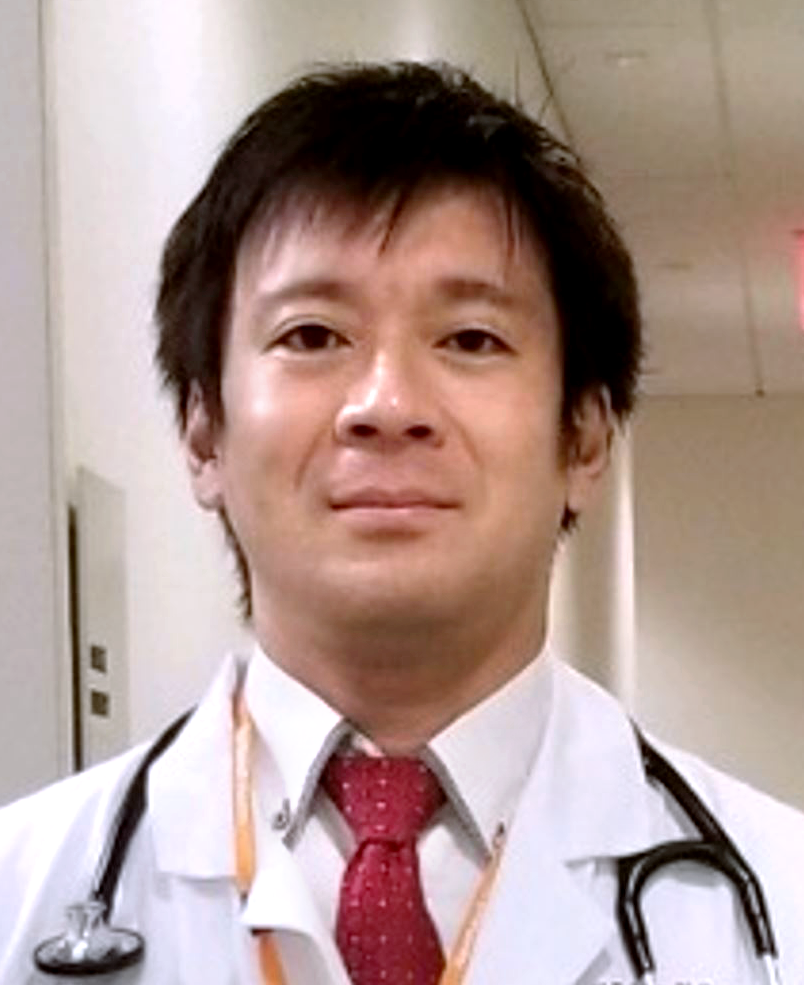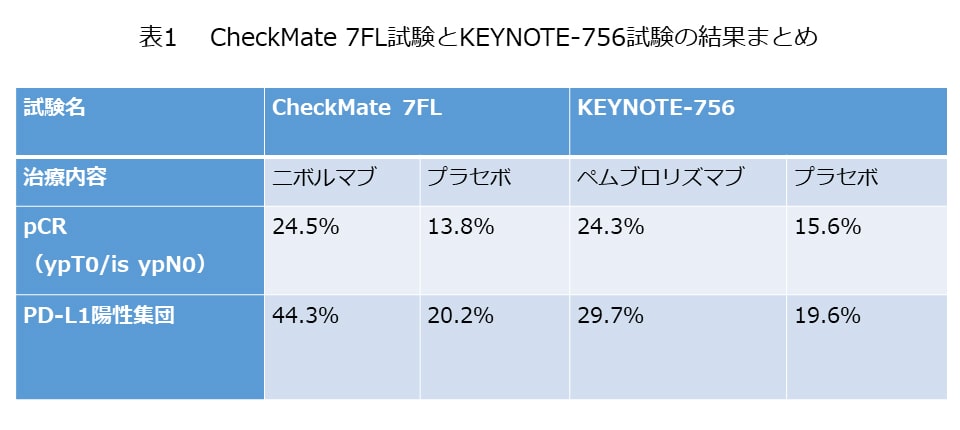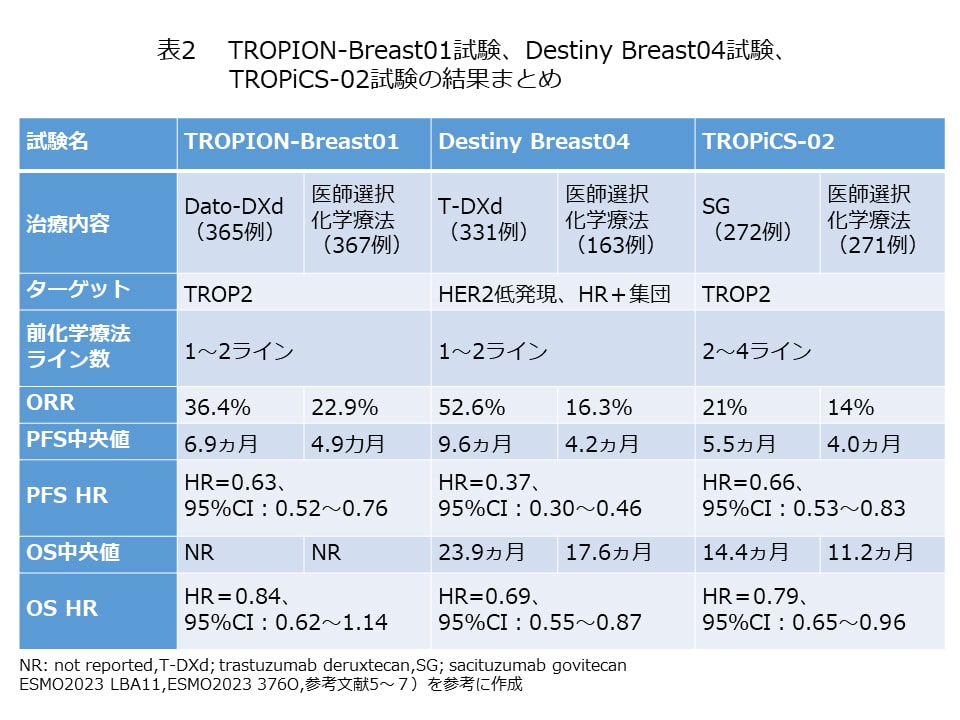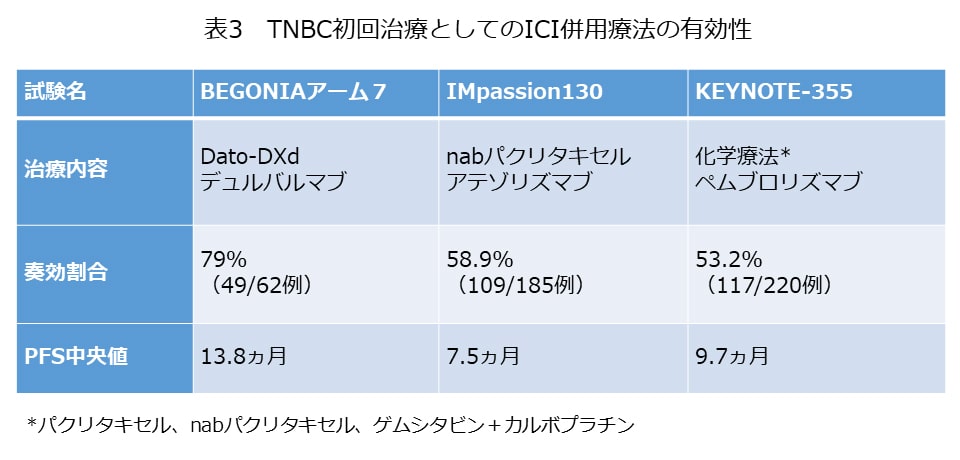[ レポーター紹介 ]
下村 昭彦 ( しもむら あきひこ ) 氏
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 乳腺・腫瘍内科/がん総合内科
新年早々暗いニュースが続いた2024年であるが、毎年恒例のSan Antonio Breast Cancer Symposiumレポートをお送りする。2023年12月5日から12月9日まで5日間にわたり、SABCS2023がハイブリッド形式で実施された。COVID – 19が5類となりさまざまな制約がなくなったこともあってか、日本からも多くの乳がん専門医が参加していた。私も現地で参加、発表させていただいた。学会外での会議や勉強会なども以前と同様実施されていた。以前との違いは、会議なども基本はハイブリッドで行われるようになったことであろうか。集合形式は活発なディスカッションができるものの、どうしても都合がつかない場合もある。ハイブリッド形式が会議を最大限に充実させる形式なのかもしれない。
SABCS2023では日常臨床にインパクトを与える、あるいは今後の治療開発において重要な試験がいくつも発表された。多くの演題の中から、転移乳がんに対する演題を4つ紹介する。
MONARCH3試験
MONARCH3試験は、閉経後ホルモン受容体陽性(HR+)HER2陰性(HER2-)転移乳がんの1次治療におけるアロマターゼ阻害薬へのアベマシクリブの有効性を評価した試験である。アベマシクリブの上乗せは無増悪生存期間(PFS)を統計学的有意に延長し、すでに実臨床では1次治療でも積極的に使用されている。今回は待望の全生存期間(OS)の結果が公表された。
ITT集団におけるOS中央値は、アベマシクリブ群で66.8ヵ月、プラセボ群で53.7ヵ月(ハザード比[HR]:0.804、95%信頼区間[CI]:0.637~1.015、p=0.0664)であり、p値は有意水準である0.034を上回り統計学的有意差は証明されなかった。内臓転移を有するサブグループにおけるOS中央値は、アベマシクリブ群で63.7ヵ月、プラセボ群で48.8ヵ月(HR:0.758、95%CI:0.558~1.030、p=0.0757)であり、こちらも統計学的有意差は示されなかった。
数値としてアベマシクリブ群でOSが有効である期待は残されるものの、有意差がつかなかったということはかなり大きな衝撃であった。なお、後治療としてパルボシクリブを実施した患者はアベマシクリブ群で8%、プラセボ群で25%であり、この差がOSにどの程度インパクトを与えたかは今後の詳細な解析に期待したい。この結果により、世界的に広く用いられているパルボシクリブ、アベマシクリブ、ribociclibのうち、1次治療におけるOSがポジティブなのはribociclibだけとなった。すなわち、日本で処方可能なパルボシクリブ、アベマシクリブはいずれもOSにおけるベネフィットを示せなかったことになる。ただ、だからといってCDK4/6阻害薬をより後ろの治療で用いるべきものになるかというと、そうではない。alpelisib、capivasertibなどSERDとの併用で用いられる別の機序の分子標的薬、あるいはPADA-1試験のような、1次治療、2次治療でCDK4/6阻害薬をbeyondで用いる戦略など、2次治療にCDK4/6阻害薬を“とっておく”と実施できなくなる治療/治療戦略が多数開発されている。現在行われている試験の多くもCDK4/6阻害薬を原則として1次治療で用いることが前提となっており、HR+HER2-転移乳がんの治療シークエンスを考えるうえで、1次治療におけるCDK4/6阻害薬の併用は変わらずスタンダードであると言えよう。
INAVO120試験
INAVO120試験はPIK3CA変異のあるHR+HER2-転移乳がんの2次治療において、フルベストラント+パルボシクリブによる治療にPI3K阻害薬であるinavolisibを併用することの有効性を評価した第III相試験である。本試験でPIK3CA変異はctDNAの中央判定もしくは各施設における組織/ctDNAの評価によって定義されていた。主要評価項目はPFSが設定された。325例がinavolisib群とプラセボ群に1:1に割り付けられた。両群間のバランスはよく、95%以上の症例で内臓転移を有した。
主要評価項目のPFSはinavolisib群15.0ヵ月、プラセボ群7.3ヵ月(HR:0.43、95%CI:0.32~0.59、p<0.0001)とinavolisib群で有意に長かった。OSはHR:0.64、95%CI:0.43~0.97、p=0.0338とinavolisib群で良好な傾向を認めたが、中間解析に割り当てられた有意水準は超えなかった。G3以上の有害事象としては血小板減少(14.3% vs.4.3%)、口内炎(5.6% vs.0%)、貧血(6.2% vs.1.9%)、高血糖(5.6% vs.0%)、下痢(3.6% vs.16.0%)とinavolisib群で血液毒性、非血液毒性のいずれも増加した。
HR+HER2-乳がんの治療を考えるうえで、3剤併用療法が良いのか、2剤までの併用をシークエンスで使用していくのか、なかなか悩ましいところであるが、OSを延長する可能性が示されたことは大きなインパクトであった。これまでに実施された、あるいは現在進行中の2次治療以降の併用試験などの結果も踏まえた治療シークエンスの議論が必要であろう。また、残念ながら本剤は現在のところ国内では開発されていない。
HER2CLIMB-02試験
HER2CLIMB-02試験は、すでにHER2陽性(HER2+)転移乳がんの3次治療においてトラスツズマブ+カペシタビンとの併用の有効性が示されているtucatinibの、T-DM1との併用の有効性を検証した第III相試験である。トラスツズマブならびにタキサンによる治療歴のあるHER2+転移乳がん460例が、tucatinib群とプラセボ群に1:1に割り付けられた。主要評価項目はPFSであった。転移乳がんに対する前治療歴が1ラインの症例が64%、ペルツズマブの投与歴のある症例が約90%であった。
主要評価項目のPFSはtucatinib群で9.5ヵ月、プラセボ群では7.4ヵ月(HR:0.76、95%CI:0.61~0.95、p=0.0163)とtucatinib群で有意に長かった。奏効割合は42.0% vs.36.1%とtucatinib群で良い傾向を認めた。tucatinibは脳転移に対する有効性が示されているが(HER2CLIMB試験)、本試験の脳転移を有する症例に対するPFSは7.8ヵ月vs.5.7ヵ月(HR:0.64、95%CI:0.46~0.89)とtucatinib群で良好な可能性が示された。OSはHR:1.23とtucatinib群で良い可能性は示されなかった。G3以上の有害事象の中で重要なものはAST増加(16.5% vs. 2.6%)、ALT増加(16.5% vs.2.6%)、倦怠感(6.1% vs.3.0%)、下痢(4.8% vs.0.9%)、悪心(3.5% vs.2.1%)などであった。
tucatinibはT-DM1との併用における有効性を示したわけであるが、今後この試験結果を基にT-DM1+tucatinibがよりアップフロントに用いられるかというと疑問が残る。T-DXdの2次治療における有効性を証明したDESTINY Breast-03試験では、T-DXdのPFS中央値は28.8ヵ月である。試験間の比較で治療の優劣は付けられないが、かといってT-DXdよりもT-DM1+tucatinibを優先するのは難しい。今後はT-DXdによる治療歴のある患者に対するT-DM1+tucatinibのデータを創出することが必要であろう。
JCOG1607試験
JCOG1607 HERB TEA試験は、JCOGで行われた高齢者HER2+転移乳がん1次治療における、T-DM1のペルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル(HPD)療法への非劣性を検証した第III相試験である。不肖下村が、今回から新設されたRapid Fire Mini Oral Sessionで(なんとメイン会場で)発表させていただいた。本試験は、65歳以上の高齢者HER2+転移乳がんを対象に、OSを主要評価項目として実施された。250例の予定登録数で行われたが、148例が登録された時点で実施された1回目の中間解析で、OSハザード比の点推定値が非劣性マージンの1.35を超えたため無効中止となった。患者背景は両群間でバランスが取れており、年齢の中央値は71歳ならびに72歳、75歳以上が約35%を占めた。PS 0が75%、HR+が約半数、初発StageIVが65%、脳転移を有する症例はまれであり、内臓転移は65%に認められた。
主要評価項目のOSは両群ともに中央値に到達しなかったが、HR:1.263、95%CI:0.677~2.357、p=0.95322とT-DM1のHPD療法に対する非劣性は示されなかった。PFSはHPD療法で15.6ヵ月、T-DM1で11.3ヵ月(HR:0.358、 95%CI:0.907~2.033、p=0.1236)とHPDで良い傾向を認めた。有害事象はG3以上がHPD療法で多く(56.8% vs.34.7%)、HPD療法では白血球減少(26.0% vs.0%)、好中球減少(30.1% vs. 0%)、倦怠感(21.6% vs.5.6%)、下痢(12.2% vs.0%)、食欲低下(10.8% vs.8.3%)が多く、T-DM1療法では血小板減少(0% vs.16.7%)、AST増加(0% vs.15.3%)、ALT増加(2.7% vs.16.7%)が多かった。
本試験は高齢者に対するless toxicな治療の開発を期待して開始したが、高齢者においてもpivotal studyで示された標準治療を実施すべきという結論となった。一方、高齢者は年齢のみで定義される均一な集団ではなく、ASCOガイドラインなどで示されているように、高齢者機能評価などを適切に実施したうえで治療方針を決めていくことが重要である。今後より詳細な結果を発表していきたい。
掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。
(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。)
本コンテンツに関する下記情報は掲載当時のものです。
[データ、掲載内容、出演/監修者等の所属先や肩書、提供先の企業/団体名やリンクなど]