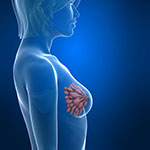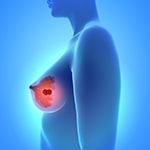提供元:CareNet.com

ホルモン受容体陽性、HER2陽性の進行乳がんの1次治療では、標準的な導入療法で病勢の進行を認めなかった患者の維持療法において、標準療法単独と比較して標準療法+パルボシクリブ(サイクリン依存性キナーゼ4/6阻害薬)は、無増悪生存期間(PFS)が有意に1年超長く、奏効率や奏効例の奏効期間も良好だが、Grade3/4の有害事象の頻度が2倍超であることが、米国・Harvard Medical SchoolのOtto Metzger氏らが実施した「PATINA試験」で示された。研究の成果は、NEJM誌2026年1月29日号に掲載された。
8ヵ国の無作為化第III相試験
PATINA試験は、8ヵ国123施設で実施した非盲検無作為化第III相試験であり、2017年6月~2021年7月に参加者を登録した(Pfizerなどの助成を受けた)。
年齢18歳以上のホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)受容体陽性、HER2陽性の進行乳がんで、1次治療における導入療法として化学療法(タキサン系薬剤)+HER2標的療法(トラスツズマブ+ペルツズマブまたはトラスツズマブ単剤)の投与を4~8サイクル受け、病勢の進行を認めなかった患者(完全奏効、部分奏効、安定)を対象とした。
被験者を、導入療法の最終投与日から12週以内に、維持療法としてHER2標的療法(トラスツズマブ+ペルツズマブまたはトラスツズマブ単剤)+内分泌療法(アロマターゼ阻害薬またはフルベストラント)の投与を開始する群(標準療法群)、または標準療法に加えパルボシクリブの投与を開始する群(パルボシクリブ群)に、1対1の割合で無作為に割り付けた。
主要評価項目は、担当医評価によるPFS。副次評価項目は、奏効率、臨床的ベネフィット、安全性および全生存期間などであった。
PFS中央値は44.3ヵ月vs.29.1ヵ月
518例(年齢中央値53.4歳、男性3例[0.6%]、白人401例[77.4%]、閉経後女性320例[61.8%])を登録し、パルボシクリブ群に261例、標準療法群に257例を割り付けた。無作為化前の導入療法のサイクル数中央値は6であり、導入療法終了時に70.1%が完全奏効・部分奏効、29.3%が安定であった。維持療法では、94.0%が2剤併用抗HER2療法、90.7%がアロマターゼ阻害薬の投与を受けた。
追跡期間中央値53.5ヵ月の時点におけるPFSは、標準療法群が29.1ヵ月(95%信頼区間[CI]:23.3~38.6)であったのに対し、パルボシクリブ群は44.3ヵ月(32.4~56.8)と有意に延長した(ハザード比:0.75、95%CI:0.59~0.96、両側非層別log-rank検定のp=0.02)。
また、12、24、48ヵ月時のPFS率は、パルボシクリブ群がそれぞれ84.9%、65.2%、46.5%、標準療法群は73.2%、55.3%、38.3%だった。
確定された奏効率(導入療法による完全奏効例を除外し、少なくとも2回の連続した評価で完全奏効または部分奏効が持続していた患者の割合)は、パルボシクリブ群が32.9%(95%CI:26.9~39.4)、標準療法群は24.8%(19.3~30.0)であった。
確定された奏効期間中央値は、パルボシクリブ群が44.9ヵ月(95%CI:27.1~51.6)、標準療法群は30.8ヵ月(26.0~評価不能)だった。
Grade3の有害事象が79.7%、Grade4は10.0%
Grade3の有害事象は、パルボシクリブ群で79.7%と、標準療法群の30.6%の2倍超の頻度で発現し、主に好中球減少(55.9%vs.2.0%)と白血球減少(15.7%vs.0.8%)であった。Grade4の有害事象は、それぞれ10.0%および3.6%に見られた。
Grade5の有害事象(試験薬以外の原因による致死的イベント)は、パルボシクリブ群で3.8%、標準療法群で4.4%に認めたが、担当医判定による試験薬関連の死亡の報告はなかった。重篤な有害事象は、それぞれ28.7%および21.8%で発現した。
また、パルボシクリブ群では、57.7%で減量を要し(27.7%が1回、30.0%が2回の減量)、18%で投与中止の原因となった有害事象が見られた。
著者は、「本試験では、導入療法中に病勢が進行した患者を除外したため、病変の生物学的特性がより良好な患者を試験集団に集積した可能性がある」「44ヵ月を超える無増悪生存期間の達成は臨床的に意義のある進展を示すもの」「早期死亡はまれで、6ヵ月全生存率は両群とも99%を超えており、これは導入療法を完了して維持療法の段階に移行した患者の良好なアウトカムを反映するものである」としている。
(医学ライター 菅野 守)
【原著論文はこちら】