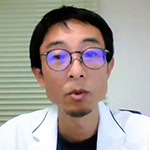提供元:CareNet.com

フランス・ソルボンヌ・パリ・ノール大学のAnais Hasenbohler氏らは大規模前向きコホート研究において、加工食品で広く使用されている保存料の摂取と、がん(全体、乳がん、前立腺がん)罹患率上昇に、複数の正の関連が観察されたことを報告した。保存料は、微生物や酸化による劣化を防ぐことで保存可能期間を延長する、包装食品に添加される物質。それら保存料については、in vivoおよびin vitroの実験的研究において、終末糖化産物(AGE)ならびに変異原性および潜在的発がん活性に関与する負の影響が示唆されていた。BMJ誌2026年1月7日号掲載の報告。
大規模前向きコホートで、保存料の摂取量とがん罹患の関連を評価
保存料が添加された食品とがん罹患率の関連を大規模前向きコホートで調べる検討は、French NutriNet-Sante cohort(2009~23年)のデータを用いて行われた。
対象は、ベースラインで少なくとも2回の24時間食事記録を完了し、がんに罹患していない15歳以上10万5,260例であった。
研究グループは、ブランド加工食品に含まれている保存料の累積時間依存摂取量を、24時間食事記録を用いて評価し、3つの食品成分データベースとNutriNet-Santeデータベースを統合して加工食品に含まれる特定の食品添加物を調べ、事後的ラボ解析で最も頻繁に摂取された添加物と食品の組み合わせについて評価した。
参加者を、保存料(単一、グループ)別の摂取量で三分位に分類(第1三分位~第3三分位)し(参加者の3分の1以上が摂取していた保存料では参加者を性別に低・中・高摂取者の三分位に分類。それ以外は性別に中央値により非摂取者および低/高摂取者に分類)、摂取量とがん罹患率の関連を、潜在的交絡因子を補正した多変量比例ハザードCoxモデルを用いて解析した。
数種の保存料で、摂取量が多いとがん罹患率が上昇
参加者の平均年齢は42.0歳(SD 14.5)、女性が78.7%であった。平均追跡期間7.57年(SD 4.56)において、4,226例ががん罹患の診断を受けていた(乳がん1,208例、前立腺がん508例、大腸がん352例、その他2,158例)。
数種の保存料について、摂取量が多いこととがん罹患率が高いことの関連が次のように認められた。
・非抗酸化物質の総摂取量と(1)全がん(高摂取者vs.非摂取/低摂取者のハザード比[HR]:1.16[95%信頼区間[CI]:1.07~1.26、尤度比検定のp<0.001]、60歳時点の絶対がんリスクはそれぞれ13.3%vs.12.1%)および(2)乳がん(1.22[1.05~1.41、尤度比検定のp=0.02]、5.7%vs.4.8%)。
・ソルビン酸の総摂取量(とくにソルビン酸カリウム)と、(1)全がん(1.14[1.04~1.24、尤度比検定のp=0.01]、13.4%vs.11.8%)および(2)乳がん(1.26[1.07~1.49、尤度比検定のp=0.02]、5.7%vs.4.6%)。
・亜硫酸塩の総摂取量と、全がん(1.12[1.02~1.24、尤度比検定のp=0.03]、13.4%vs.11.9%)。
・ピロ亜硫酸カリウムと、(1)全がん(1.11[1.03~1.20、尤度比検定のp=0.01]、13.5%vs.12.0%)および(2)乳がん(1.20[1.04~1.38、尤度比検定のp=0.01]、5.7%vs.4.9%)。
・亜硝酸ナトリウムと、前立腺がん(1.32[1.02~1.70、傾向のp=0.03]、4.2%vs.3.4%)。
・硝酸カリウムと(1)全がん(1.13[1.05~1.23、尤度比検定のp=0.001]、14.0%vs.12.0%)および(2)乳がん(1.22[1.05~1.41、尤度比検定のp=0.003]、5.9%vs.4.8%)。
・酢酸塩の総摂取量と(1)全がん(1.15[1.06~1.25、尤度比検定のp=0.003]、14.3%vs.12.2%)および(2)乳がん(1.25[1.07~1.45、尤度比検定のp=0.02]、6.1%vs.4.9%)。
・酢酸と全がん(1.12[1.01~1.25、尤度比検定のp=0.01]、14.4%vs.12.4%)。
・エリソルビン酸ナトリウムと、(1)全がん(1.12[1.04~1.22、尤度比検定のp<0.001]、13.5%vs.11.9%)および(2)乳がん(1.21[1.04~1.41、尤度比検定のp=0.01]、5.7%vs.4.8%)。
がんと関連しない保存料は17種のうち11種
個別に検証した保存料17種のうち11種は、がん罹患との関連が示されなかった。
著者は、「がん発症との関連をより深く理解するためには、健康関連バイオマーカーをベースとした疫学調査および実験的研究を行う必要があるが、もし今回の新たなデータが確認されれば、消費者保護強化の観点から、食品業界に対して添加物の使用規定の見直しを求めることになる。少なくとも今回得られた知見は、消費者に、加工食品は最小限にとどめ新鮮な食品を好んで食するよう推奨する根拠となるものである」とまとめている。
(ケアネット)
【原著論文はこちら】