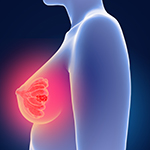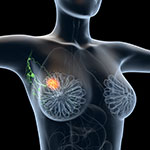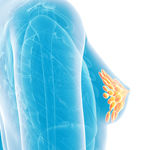提供元:CareNet.com

米国の乳がん死亡率は、乳がんのスクリーニングと治療の改善によって、1975年から2019年までに58%低下したことが、米国・スタンフォード大学のJennifer L. Caswell-Jin氏らによるシミュレーションモデル研究で示された。シミュレーションでは、StageI~IIIの乳がんの治療が、47%の低下に寄与していることが示された一方で、転移のある乳がんについては、治療の寄与は29%、スクリーニングの寄与は25%であった。米国における乳がん死亡率は、1975年から2019年の間に減少したことが報告されていたが、転移のある乳がん治療の変化と乳がん死亡率低下との関連はわかっていなかった。JAMA誌2024年1月16日号掲載の報告。
CISNETの4つのモデルで乳がん死亡率をシミュレーション
研究グループは、本研究のためにCancer Intervention and Surveillance Modeling Network (CISNET)が開発した4つのモデルを用い、マンモグラフィーによるスクリーニングと治療(StageI~IIIの乳がん治療、転移のある乳がん治療)の普及および効果に関する観察研究ならびに臨床試験のデータを集約し、1975~2019年の米国における30~79歳の女性の乳がん死亡率を、全体およびエストロゲン受容体(ER)およびERBB2(HER2)状態別にシミュレーションした。
主要アウトカムは、乳がんの年齢調整死亡率で、スクリーニング、StageI~IIIの治療および転移のある乳がん治療の介入がない場合と比較した。また、乳がんの転移再発後の生存期間中央値についてもモデルで推定した。
1975年から2019年に乳がん死亡率は58%低下、転移治療の寄与は29%
米国における乳がんの年齢調整死亡率は、1975年が女性10万人当たり48、2019年は同27であった。
スクリーニング、StageI~IIIの乳がん治療および転移のある乳がん治療の3つすべての介入を反映したモデルでは、1975年に比べて2019年の乳がん死亡率は58%低下(モデル範囲:55~61)した。この低下について、転移のある乳がん治療の介入だけを反映したモデルでは29%(モデル範囲:19~33)、StageI~IIIの乳がん治療のみだけの場合は47%(35~60)、マンモグラフィー検査のみだけの場合は25%(21~33)の低下であった。
シミュレーションに基づくと、転移再発後の生存の最も大きな変化は2000年から2019年の間に起きており、生存期間中央値は1.9年(モデル範囲:1.0~2.7)から3.2年(2.0~4.9)に延長していた。また、ER陽性/ERBB2陽性乳がんの生存期間中央値は2.5年(2.0~3.4)延長していた一方で、ER陰性/ERBB2陰性乳がんの生存期間中央値の延長は0.5年(0.3~0.8)であった。
なお著者は、モデルの精度は実施された仮定に依存していること、モデルにはスクリーニングや治療の普及と有効性における年齢、人種、民族などによる潜在的な格差や、治療費やアウトカムとの関連性は組み込まれていないことなどを研究の限界として挙げている。
(医学ライター 吉尾 幸恵)
【原著論文はこちら】