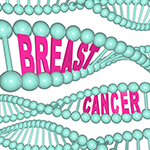提供元:CareNet.com

19万人以上のUKバイオバンクのデータを用いて、世界がん研究基金(WCRF)による生活習慣のアドバイスを遵守することが13種類のがんのリスクとどのような関係があるのか、また遺伝的リスクによってこれらの関連性が異なるのかを調査するため、前向きコホート研究が実施された。南オーストラリア大学のStephanie Byrne氏らによるInternational Journal of Epidemiology誌オンライン版2023年1月18日号への報告。
2006~10年にかけて37~73歳の参加者の生活習慣を評価し、2015~19年までがんの発生率を追跡調査した。解析対象は、悪性腫瘍の既往がない19万5,822人。13のがん種(前立腺がん、大腸がん、閉経後乳がん、肺がん、悪性黒色腫、非ホジキンリンパ腫、腎臓がん、子宮がん、膵臓がん、膀胱がん、口腔・咽頭がん、卵巣がん、リンパ性白血病)とがん全体について多遺伝子リスクスコア(PRS)を計算し、WCRFの勧告からライフスタイル指数を計算。両者の加法的・乗法的交互作用が評価された。
ライフスタイル指数は体型(BMI、腹囲)、身体活動、全粒粉・果物・野菜摂取、赤肉・加工肉摂取、アルコール消費、喫煙状況について2018 WCRF/米国がん研究財団(AICR)のスコアリングシステムに基づき評価され、スコアが高いほど推奨事項への忠実度が高いとされる。
主な結果は以下のとおり。
・192万6,987人年(追跡期間中央値:10.2年)で1万5,240件のがんが発生した。
・交絡因子で調整後、ライフスタイル指数の高さはがん全体のリスク(1標準偏差増加当たりのハザード比:0.89、95%信頼区間:0.87~0.90)および、大腸がん(0.85、0.82~0.89)、閉経後乳がん(0.85、0.81~0.89)、肺がん(0.57、0.54~0.61)、腎臓がん(0.78、0.72~0.85)、子宮がん(0.82、0.74~0.89)、膵臓がん(0.79、0.72~0.87)、膀胱がん(0.72、0.65~0.79)、口腔・咽頭がん(0.78、0.71~0.86)のリスク低下と関連していた。
・ライフスタイル指数と悪性黒色腫、非ホジキンリンパ腫、卵巣がん、リンパ性白血病との間に関連はみられず、前立腺がんリスクとの間には、逆方向の関連性がみられた(1.04、1.01~1.08)。
・PRSが高いほどがん全体および口腔・咽頭がんと卵巣がんを除く評価したすべてのがん種のリスクが高い傾向がみられた。とくに膵臓がん(1.51、1.36~1.66)、リンパ性白血病(1.50、1.33~1.69)、悪性黒色腫(1.39、1.32~1.47)、大腸がん(1.36、1.31~1.42)、前立腺がん(1.36、1.32~1.40)で高かった。
・大腸がん、乳がん、膵臓がん、肺がん、膀胱がんのリスクにはライフスタイル指数とPRSの加法的相互作用がみられ、推奨されるライフスタイルは、遺伝的リスクの高い人ほど絶対リスクの変化と関連していた(すべてでp<0.0003)。
著者らは、WCRF推奨の生活習慣は、ほとんどのがんについて有益な関連性がみられたとし、さらにいくつかのがんでは遺伝的リスクの高い集団で保護的な関連が大きいと結論づけた。そのうえで、これらの知見は遺伝的にそれらのがんに罹患しやすい人々や、がん予防のための標的戦略にとって重要な意味を持つとまとめている。
(ケアネット 遊佐 なつみ)
【原著論文はこちら】
Byrne S, et al. Int J Epidemiol. 2023 Jan 18. [Epub ahead of print]