提供元:がん@魅せ技
診断:乳癌 T1N0M0 患者Prof:50代 女性
執刀:埼玉医科大学総合医療センター 矢形寛 医師
Chapter 3:乳腺切除
同症例のChapter一覧
| Chapter 1 : | 画像診断 |
| Chapter 2 : | センチネルリンパ節切除 |
| Chapter 3 : | 乳腺切除 |
| Chapter 4 : | 止血 |
| Chapter 5 : | 再建 |
| Chapter 6 : | 縫合 |
(フェーズワン)

ケアネットはピンクリボン運動を支援し、乳がんの予防・診療に関わる情報提供に取り組んでいます。

ケアネットはピンクリボン運動を支援し、乳がんの予防・診療に関わる情報提供に取り組んでいます。

[ レポーター紹介 ]
山本 眞基子
1997年30代で乳がんを発症。
NPO法人BCネットワーク(Young Japanese Breast Cancer Network)を設立 。

米国在住の1997年に、30代で乳がんを発症。仕事や子育てなど多忙な年代で、海外生活の中乳がんになった自身の経験、そして日本国内だけでなく米国在住の日本人女性においても乳がん患者が年々増加傾向にあることから、日本語での乳がんの情報発信を目的としたNPO法人、BCネットワーク(Young Japanese Breast Cancer Network)を設立した山本 眞基子さんに、米国の乳がん診療の状況を患者目線からご紹介いただきます。後編では、米国では20年以上前から行われているという遺伝子検査や、食事・運動療法の実際などについてお聞きしました。
Q 告知や治療方法の説明、セカンドオピニオンの利用状況について教えてください

お話しできるのはニューヨークの病院での経験ですが、告知は当然、治療方法説明も当然という状況です。ただしその告知の仕方が、医師の人気度を決定していると私は感じています。セカンドオピニオンは20年前から当然、かつ初めの病院のスクリーンなどもセカンドオピニオンの病院に持参可能です。むしろ、時間がある場合は、医師のほうから受診を勧められます。セカンドオピニオンを嫌がる医師はニューヨーク近辺では聞いたことがありません。セカンドオピニオンには、保険も適用されます。また、高度な病院ほど自己病院の検査を好む傾向があり、再度検査が必要なことも多いですが、ほとんど保険適用されます。
Q 日米で受けることができる治療法に差はあるでしょうか? 遺伝子検査の普及の実際は?
治療法については、すでに米国で承認されているほとんどの治療法が、日本でも導入されていると思います。一方、遺伝子検査については、米国ではかなり前から普及している印象です。私自身が初めて早期乳がんになった22年前には、乳がんに罹患した患者は全員、本人の承認を得て、BRCA1/2の遺伝子検査(が保険適応で行われていました。BRCA1/2遺伝子についてはこれまで長く、ある1つの企業の製品だけが使える状況でしたが、5年ほど前に、他の企業も検査を提供できるように枠組が広げられました。また、10年ほど前から、米国では保険適用となった遺伝子検査(オンコタイプDX)などが、早期乳がんの腫瘍進行度を調べることを目的に、保険適用にて検査が可能となった州が多いと思います(ちなみに米国は、日本と違い、州により検査の普及がかなり違います。その理由は、州により健康保険、私的保険の適用の治療、検査などの枠組みが違うので、国が検査を承認しても、保険適用にならない場合もあります)。
Q 食事や運動療法など、手術・薬物療法以外の治療法についてはどのような状況でしょうか?
これもニューヨークでの状況ではありますが、大学病院では、すべてと言ってもよいほど多くの病院で、20年ほど前から、食事・運動療法を奨励し、ほとんどの場合は、病院のホームページでその方法を紹介したり、病院内に栄養士のクリニック、運動療法(乳がん系ではヨガ、ストレッチ、瞑想、鍼などが主体です)の専門家が揃っています。保険のタイプによっては、そういったクリニックでの施術や指導に保険が適用されることもあります。
Q 最後に、乳がん診療に携わる医師に伝えたいことはありますか
日本以外の乳がん罹患率の高い国々の治療法などにも興味を示していただき、ぜひ世界中の医師と患者とのつながりを意識して治療をしていただきたいと思います。また、患者が医師に対等に質問や意見をできる環境ができるとよいなと考えます(ニューヨークの大病院では、患者と医師のディスカッションが大いに可能です)。

[ レポーター紹介 ]
松柳 美咲 (まつやなぎ みさき) 氏
昭和大学病院 乳腺外科 助教
2019年9月4~6日の3日間にわたり、米国・サンフランシスコで5th World Congress on Controversies in Breast Cancer (CoBrCa)が開催されました。CoBrCaは通常の学会とは形式が異なり、多くの臨床医が診療上で遭遇する疑問点に対し、それぞれの分野のエキスパートが登壇して“Yes”、“No”それぞれの立場に分かれてエビデンスに基づいたディベートを行います。扱うトピックは、外科治療、薬物治療、放射線治療、画像診断、病理診断、乳房再建といった広範囲にわたっています。
これまで、1回目はスペイン、2回目はオーストラリア、3回目は日本、4回目はオーストラリアで開催されてきました。今年で5回目の開催となり、カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)主催の下、メインテーマは“When is Less More?”でした。患者のリスク因子を層別化し、de-escalationとescalationをどのように行っていくかというセッションが多くみられました。
19の課題について賛成・反対を議論

3日間で19のセッションがあり、各セッション4~6人のdiscussantが活発な議論を行いました。どのテーマも、エキスパートの中でも意見が分かれるであろうものが多く、最新のエビデンスや今後の課題などが挙げられました。
“ほとんどのDCISは精査の対象とすべきではないのか”、“ACOSOG Z0011(Z11)とAMAROS試験の結果によらず、センチネルリンパ節生検陽性で腋窩リンパ節郭清を行うべき症例はあるのか”、“免疫チェックポイント阻害薬は転移のあるトリプルネガティブ乳がんのstandardとなるのか”、 “CDK4/6阻害薬は転移のあるホルモン陽性乳がんの1st line治療とすべきか”、 “RCTのみが日常臨床を変える方法となるのか”など、大変興味深いテーマが多くありました。最終セッションは、“Vision for breast cancer 2025”で締めくくられました。
本稿では、ゲノム医療とHER2陽性乳がんについて、それぞれのセッションでの議論をご紹介します。
1 ゲノム医療
パネル検査は多くの患者に必要? それとも意義なし?
[テーマ:That most patients with breast cancer should be panel tested]
Yesでプレゼンテーションを行ったのは、「MammaPrint」の開発に携わったUCSFのvan’t Veer博士で、乳がんの罹患リスク上昇に関わる遺伝子異常の相対リスクや頻度についての報告を行いました。遺伝子検査の目的としては、2nd cancer riskを考慮した術式選択の決定、術前化学療法の効果予測、サーベイランスを行ううえでの再発リスク評価を挙げたうえで、「今の時代は患者個人が自分の遺伝子について当然知るべきである」と発言しました。

Noの立場からは、パネル検査は病的意義を持たないvariant of uncertain significance(VUS)が多く、pathogenic variant(PV)は比較的稀であることが挙げられました。また、近年VUS/PVの誤った解釈が、とくに術式選択の場面で行われている現状について報告が挙げられています。KurianらによるアメリカSEERデータベースを使用した乳がん症例(全例で遺伝子検査を施行)の報告では、BRCA1/2の遺伝子異常のある患者で両側乳房切除が行われた患者は57.5%であったが、遺伝子異常がない患者でも23.6%、ATM 、CHEK2 、PALB2などの乳がん発症において中等度の発症リスクとなる遺伝子のPVでも34.0%の患者で両側乳房切除が行われており、over surgeryとなっている現状があります。さらにこの研究ではホルモン陽性、21遺伝子アッセイでRS<18の再発低リスクとされる患者で、36.5%と高率に化学療法が行われていたことについても報告されています(遺伝子異常がない患者では23.0%に化学療法が行われていた)。
遺伝子異常の有無によって予防的切除を判断すべきか
[テーマ:That all gene carries with early breast cancer should have a bilateral mastectomy]
Yesの立場からは、BRCA1/2遺伝子異常を持つ患者の場合、2nd cancer riskの発症が高率である点(20年間の追跡の結果、対側の乳がん発症率はBRCA1異常で28~40%、BRCA2遺伝子異常で16~26%と報告されている)、また、費用対効果の面からMRIサーベイランスより予防的切除のほうが優れるとする報告がある点から、両側乳房切除を推奨すべきと意見されていました。
Noの立場からは、乳房切除による患者の心理的負担を考慮したうえでMRIによる1年ごとのサーベイランスを行えば、予防切除を行った患者と比較し10年間のOSに差はないという報告が挙げられていました。
2.HER2陽性乳がん
抗HER2補助療法の併用は必要か? 逆にde-escalationできるケースとは?
[テーマ:All high risk adjuvant HER2 patients receive dual antibody therapy]
Yesの立場からは、HER2陽性乳がんを対象とした術後補助療法において、化学療法+トラツズマブにペルツズマブを上乗せするペルツズマブ群とプラセボ群の無作為割り付け比較を行ったAPHINITY試験について言及されていました。3年の時点でのIDFSはペルツズマブ群92.0%に対し、プラセボ群では90.2%という結果でした(ハザード比:0.77、95%信頼区間:0.62~0.96、p=0.02)。サブグループ解析の結果からは、リンパ節転移陽性、ホルモン陰性、閉経後、65歳以上で有意差がみられました。
Noの立場からは、パクリタキセル+トラツズマブ併用療法について検討したAPT試験の結果が挙げられていました。低リスクのHER2陽性乳がん(pT1、N0)を対象とし、7年のOSは95.0%(95%信頼区間:0.95~0.99)と良好であったことが報告されており、de-escalatingすべきと発言しています。

もう1つのセッションでは、HER2陽性乳がんにおける抗HER2補助療法の短縮化についてディベートされました。2019年6月Lancet誌で報告されたPHARE試験の結果では、7.5年時点の解析における、トラツズマブ12ヵ月群に対するトラツズマブ6ヵ月群のDFSは、ハザード比:1.08(95%信頼区間:0.93~1.25、p=0.39)で非劣性が証明されました。試験の対象者は90%がアントラサイクリンベースの化学療法を施行され、55%はリンパ節転移陰性であり、そのような患者にはトラツズマブを6ヵ月へ短縮化してもよいのではないか、と結論付けられていました。
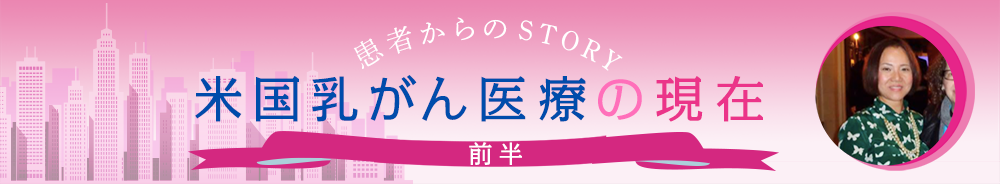
[ レポーター紹介 ]
山本 眞基子
1997年30代で乳がんを発症。
NPO法人BCネットワーク(Young Japanese Breast Cancer Network)を設立 。

米国在住の1997年に、30代で乳がんを発症。仕事や子育てなど多忙な年代で、海外生活の中乳がんになった自身の経験、そして日本国内だけでなく米国在住の日本人女性においても乳がん患者が年々増加傾向にあることから、日本語での乳がんの情報発信を目的としたNPO法人、BCネットワーク(Young Japanese Breast Cancer Network)を設立した山本 眞基子さんに、米国の乳がん診療の状況を患者目線からご紹介いただきます。前編では、保険制度や地域による格差、病院や治療法選択の実際についてお聞きしました。
Q 米国での乳がん検診の認知度、普及の状況について教えてください
米国での乳がん検診受診率は、70~80%ほどと聞いていますが、一時期高くなり過ぎて、それ以降は下がっているという記事も見たことがあります。米国の場合は、社会的地位や保険の良し悪しにより検診受診率が高いグループと低いグループの差が大きい状況です。
Q 格差の問題をよく耳にしますが、地域による格差も大きいのでしょうか?

米国在住37年になりますが、ニューヨーク近辺しか住んだことがないので、地域差を意見する立場にありません。しかしながら、病院数だけを見れば、米国中で最適な治療を受けることができる可能性が最も高いのは、ニューヨークだと考えます。何よりも医師、病院間の競争が激しいので、それが医師の治療への熱心度や、高度な治療につながるのではないでしょうか。患者も質の高い治療を求めているので、それに応えることのできる医師が残るのではないかと感じています。
東海岸地方には、大小多くの病院があるので、選択肢は多くあります。米国は乳がん罹患率が高いので、友人で乳がんになった人がいない女性はいないでしょう。友人からの紹介、または近さや通いやすさで病院を選ぶ人が多いです。ニューヨーク市内では、有名・著名な医師も多くおられるので、それを求めて選択する人も多くいます。大病院では、何人もの乳腺外科医、乳腺腫瘍内科の医師を抱えていて、患者が医師を選択することが可能です。
Q 患者が治療法や治験などについて情報を得るにはどのような方法がありますか?
米国の有名ながん病院はそれぞれホームページが素晴らしく、情報が充実しているので、実際に足を運ぶことなく、ホームページ上で各病院での治療の概要を知ることが可能です。治験薬については、自分の病院の医師から話を持ちかけられたり、病院内に張り紙がしてあることが多いです。また標準的治療法がなくなってきた患者さんには、医師から、どこどこの病院の治験に行ってはどうか、と教えてもらえることもあります。
Q 医療費(保険制度)の実際と、それを理由とする治療選択の現実などはいかがでしょうか
米国の保険制度については、日本でも語られているとおり、私的保険が主体で費用や内容に大きな幅があり、一律には良いとも悪いとも言えません。しかし、65歳以降に国から保障される老人保険は、乳がんの標準治療については、かなり良くカバーされていると思います。標準治療については、保険会社が上限を設けているため、患者はそれ以上を支払う義務はありません(これもニューヨーク近辺での経験ですので、全国ではわかりません。それほど、州により保険の内容が異なります)。
提供元:CareNet.com

血清亜鉛(Zn)濃度の低下は肝性脳症や味覚異常など、さまざまな疾患に影響することが報告されている。しかしながら、非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)患者における関連はほとんど報告されていない。今回、名古屋大学消化器内科学の伊藤 隆徳氏らは、血清中のZn濃度と総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR:molar ratio of total branched-chain amino acid to tyrosine)が、NAFLD患者の予後と関係することを明らかにした。著者らは、「血清中のBTRおよびZn濃度が、それぞれNAFLD患者の肝細胞がん(HCC)および他臓器がんの発生予測に有用」とコメントしている。Nutrition&Cancer誌オンライン版2019年8月21日号掲載の報告。
本研究では、名古屋大学と大垣市民病院において1999年1月~2014年12月の期間に肝生検を受け、NAFLDと診断された363例のうち、基準を満たした179例を登録。NAFLD患者の悪性腫瘍の発生率に対する血清中のBTRとZn濃度の影響を調査した。
主な結果は以下のとおり。
・被験者179例の内訳は、NAFLが71例、NASHが108例だった。
・平均年齢は53歳(四分位:40~62歳)、女性82例(45.8%)、男性97例(54.2%)だった。
・被験者の各中央値はBTR:6.7、Zn:78.0μg/dLだった。
・フォローアップ期間(中央値7.9年)中にHCCは7例(3.9%)、他臓器がんは10例(5.6%)発生し、他臓器がんの内訳として乳がん・婦人科がん・大腸がんが多くを占めていた。
・Bruntの分類による活動性は、Grade1が107例(59.8%)、Grade2が64例(35.8%)、Grade3が8例(4.5%)であり、線維化は、Stage0が49例(27.4%)、Stage1が72例(40.2%)、Stage2が29例(16.2%)、Stage3が25例(14.0%)、そしてStage4が4例(2.2%)だった。
・Cox比例ハザードモデルによる多変量解析により明らかとなったHCCのリスク因子は、肝線維化(F3~4、ハザード比[HR]:24.292、95%信頼区間[CI]:2.802~210.621、p=0.004)、BTR 5.0未満(HR:5.462、95%CI:1.095~27.253、p=0.038)であった。一方で、他臓器がんのリスク因子としては、血清Zn濃度70μg/dL未満(HR:3.504、95%CI:1.010~12.157、p=0.048)と病理学的肝内炎症(A2~3、HR:3.445、95%CI:0.886~13.395、p=0.074)が選択された。
・血清中のBTR低値(5.0未満)およびZn欠乏(70μg/dL未満)の患者では、HCC(p<0.001)と他臓器がん(p=0.026)の発生率がそれぞれ有意に高かった。
(ケアネット 土井 舞子)
【原著論文はこちら】
(ご覧いただくには [ CareNet.com ]の会員登録が必要です)
Ito T, et al. Nutr Cancer. 2019 Aug 21. [Epub ahead of print]
提供元:CareNet.com
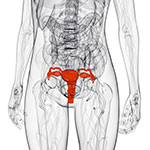
遺伝性乳がん・卵巣がんの発症には、乳がん感受性遺伝子(BRCA遺伝子)の変異が大きく関わっている。アストラゼネカ株式会社が開催したメディアセミナー(共催)にて、吉原 弘祐氏(新潟大学 医学部産婦人科学教室 助教)が、生殖細胞系列BRCA(gBRCA)1/2>遺伝子変異の保有率に関する日本初の大規模調査であるJAPAN CHARLOTTE STUDY(以下、本研究とする)に関して、解説した。
BRCA1、BRCA2はDNAの組み換え修復などの機能を有し、両親のどちらかがBRCA1あるいは2に病的変異がある場合、50%の確率で子に受け継がれる。その変異は卵巣がんなどの発症率を増加させるため、患者本人だけでなくその家族にも影響を与えうる。そのため遺伝子検査にあたっては、認定遺伝カウンセラー等によるカウンセリングが重要となる。
欧米ではガイドラインで、BRCA1/2遺伝子検査の実施を推奨しているが、日本では日常的に遺伝子検査を行う環境が整っていない。実際に、検査結果の説明などを担当する認定遺伝カウンセラーの数は全国で243人(2018年12月時点)にとどまっており、著しく不足している。また、カウンセラー不在の県もあるなど、地域にも偏りがある。
環境が整っていない日本では、卵巣がん患者におけるgBRCA1/2変異頻度に関するまとまったデータがきわめて少なかった。このような状況の中で行われた本研究は、日本初のBRCA1/2遺伝子変異に関する大規模調査である。
本研究では、日本人新規卵巣がん患者、約600例のgBRCA1/2変異陽性率とgBRCA1/2遺伝子検査前のカウンセリングに対する満足度を評価した。
gBRCA1/2変異陽性率は14.7%であり、欧米人を対象とした過去の研究報告と同程度であった。これまで、日本人のgBRCA1/2変異率は欧米人よりも低いという見方もある中で、注目すべき結果といえよう。また、gBRCA1/2変異は進行期のがんで見られることが多い。本試験においても進行卵巣がんの患者ではgBRCA1/2変異陽性率が24.1%と、早期卵巣がんよりも変異陽性率が高かった。
検査前のカウンセリングに対する満足度は、実施者の職種にかかわらず同等だったものの、検査結果がgBRCA1/2変異陽性もしくはVUSの場合、検査後のカウンセリングは全例、認定遺伝カウンセラーもしくは認定遺伝専門医が担当していた。認定遺伝カウンセラーの「ホスピタリティー」は、デリケートな内容を患者に告知する際にとても重要であるという。現状、臨床現場では遺伝子検査の結果を医師が患者に説明するケースが多いが、他の業務に追われる中で、医師がホスピタリティーにまで気を配ることは難しいケースが多々あるのではないだろうか。
BRCA1/2陽性例にリスク低減卵管卵巣摘出術を実施した場合、実施していない場合と比べて、卵巣がんの発症率が80%低下し、全生存期間が有意に延長する。そのためBRCA1/2遺伝子検査を実施することでがんを予防できたり、治療の選択肢が増えたりするケースもあると考えられる。
卵巣がんを克服するために、治療の進歩は非常に重要であるが、それだけでなく、認定遺伝カウンセラーの育成など、遺伝子検査が実施できる環境を整えることも重要になってくるのではないだろうか。
(ケアネット 門脇 剛)
提供元:CareNet.com

肉を食べると乳がん発症リスクは上昇するのか。これまで因果関係が言われながらも、一貫性のあるエビデンスが示されていなかった肉と乳がんの関係について、米国・Columbia Mailman School of Public HealthのJamie J. Lo氏らが、4万2,000例超の女性を平均7.6年間追跡した調査結果を発表した。赤肉(red meat)の摂取量が最も多い群は最も少ない群に比べて浸潤性乳がんのリスクが1.23倍高く、一方で鶏肉は最も多く食べる群が最も少ない群に比べて同リスクは0.85倍と低く、赤肉の代わりに鶏肉を食べることで乳がんリスクが低下する可能性があることが示唆されたという。なお調理法についての関連性は観察されなかったとしている。International Journal of Cancer誌オンライン版2019年8月6日号掲載の報告。
研究グループは、各種の肉摂取量、肉関連変異誘発物質と浸潤性乳がん発症との関連を調べるため、「Sister Study」に参加した4万2,012例から、各種の肉摂取量と調理方法の情報を入手し解析した。参加者は、2003~09年に登録されBlock 1998 Food Frequency Questionnaireを完了し適格基準を満たしていた。
各種の肉曝露および肉関連変異誘発物質の曝露を算出し、浸潤性乳がんリスクを、多変量Cox比例ハザード回帰法にて推算した。
主な結果は以下のとおり。
・追跡期間平均7.6年間において、4万2,012例の被験者のうち、浸潤性乳がんと診断されたのは試験登録後1年以降の時点で1,536例であった。
・赤肉の摂取量増加は、浸潤性乳がんリスクの上昇と関連していた(最高四分位群vs.最小四分位群のHR:1.23、95%CI:1.02~1.48、傾向のp=0.01)。
・一方で、鶏肉の摂取量増加は、浸潤性乳がんリスクの低下と関連していた(同HR:0.85、95%CI:0.72~1.00、傾向のp=0.03)。
・赤肉摂取と鶏肉摂取を固定していた置換モデルにおいて、赤肉摂取を鶏肉摂取に切り替えると、浸潤性乳がんリスクは低下する関連が認められた(同HR:0.72、95%CI:0.58~0.89)。
・調理方法(ヘテロサイクリックアミンや赤肉摂取に由来するヘム鉄)と、乳がんとの関連は観察されなかった。
(ケアネット)
【原著論文はこちら】
(ご覧いただくには [ CareNet.com ]の会員登録が必要です)
Lo JJ, et al. Int J Cancer. 2019 Aug 6. [Epub ahead of print]
提供元:CareNet.com

BRCA遺伝子変異の保有者において、予防的卵巣摘出術は骨にどのような影響を及ぼすのか。カナダ・Women’s College Research InstituteのJoanne Kotsopoulos氏らによる後ろ向きコホート研究の結果、とくに手術時に閉経前だった女性において卵巣摘出術と骨密度低下は関連していることが示された。著者は、「この患者集団に対しては、骨の健康を改善するため定期的な骨密度評価およびホルモン療法などの管理戦略を定めるべきである」と述べている。JAMA Network Open誌2019年8月号掲載の報告。
研究グループは、BRCA遺伝子変異の保有者に対して強く推奨される予防的両側卵管卵巣摘出術と骨密度の関連を評価する検討を行った。2000年1月~2013年5月に、カナダ・オンタリオ州トロントにあるUniversity Health Networkを介し、卵巣摘出術を受けたBRCA変異を有する患者を登録した。手術前に少なくとも1つの卵巣は完全で乳がん以外のがんの既往がないことを適格基準とし、手術の前後にDXA法で骨密度を測定した患者について解析した。データの解析は2018年12月~2019年1月に行った。
主要評価項目は、ベースラインから追跡調査までの骨密度の年間変化率で、腰椎、大腿骨頸部および全股関節に分けて算出した。
主な結果は以下のとおり。
・ベースラインと手術後追跡調査の双方の骨密度測定値があったのは計95例で、平均追跡期間は22.0ヵ月であった。
・卵巣摘出術を受けた時の平均年齢は48.0歳であった。
・手術時に閉経前であった50例(53%)で、追跡調査においてベースラインからの骨密度低下が認められた。
・骨密度低下の年間変化率は、腰椎-3.45%(95%CI:-4.61~-2.29)、大腿骨頸部-2.85%(-3.79~-1.91)、全股関節-2.24%(-3.11~-1.38)であった。
・ホルモン療法の受療者(自己申告)は非受療者と比べ、腰椎(-2.00% vs.-4.69%、p=0.02)および全股関節(-1.38% vs.-3.21%、p=0.04)で、骨密度低下が有意に少なかった。
・手術時に閉経後であった45例(47%)では、腰椎(年間変化率:-0.82%、95%CI:-1.42~-0.23)および大腿骨頸部(-0.68%、-1.33~-0.04)で骨密度の有意な低下がみられたが、全股関節(-0.18%、-0.82~0.46)ではみられなかった。
(ケアネット)
【原著論文はこちら】
(ご覧いただくには [ CareNet.com ]の会員登録が必要です)