提供元:CareNet.com
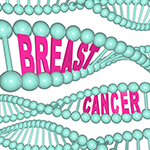
乳がん患者の5~10%が、乳がん感受性遺伝子における生殖細胞系列病的バリアントまたはその可能性が高い病的バリアントと関連することが報告されており、局所療法と全身療法の推奨を変える可能性がある。今回、カナダ・McGill大学のZoulikha Rezoug氏らが、新たに浸潤性乳がんと診断された女性を対象に調査したところ、乳がん感受性遺伝子における生殖細胞系列病的バリアントまたはその可能性が高い病的バリアントを保持する患者の割合は7.3%であった。また、BRCA1/2またはPALB2病的バリアントを保持する患者は5.3%で、その3分の1がPARP阻害薬の適応であったという。JAMA Network Open誌2014年9月3日号に掲載。
この横断研究では、2019年9月~2022年4月にカナダ・モントリオールの3施設で初発の浸潤性乳がんと診断されたすべての女性に遺伝カウンセリングと遺伝子検査が提案され、3遺伝子(BRCA1、BRCA2、PALB2)の1次パネル(必須)と、14遺伝子(ATM、BARD1、BRIP1、CDH1、CHEK2、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2、PTEN、RAD51C、RAD51D、STK11、TP53)の2次パネル(任意)が提案された。本研究に紹介される6ヵ月前までに初めて浸潤性乳がんの診断を受けた18歳以上の女性を適格とし、2023年11月~2024年6月のデータを解析した。
主な結果は以下のとおり。
・1,017例中、適格だった805例に遺伝カウンセリングと検査が提案され、うち729例(90.6%)が検査を受けた。乳がん診断時の年齢中央値は53歳(範囲:23~91歳)、65.4%が白人もしくは欧州系であった。
・53例(7.3%)に54の生殖細胞系列病的バリアントまたはその可能性の高い病的バリアントが同定され、39例(5.3%)が1次パネルの3遺伝子(BRCA1、BRCA2、PALB2)で、15例(2.1%)が2次パネルの14遺伝子中の6遺伝子(ATM、BARD1、BRIP1、CHEK2、RAD51D、STK11)であった。
・多変量解析では、BRCA1/BRCA2/PALB2病的バリアント陽性に独立して関連する臨床的因子として、診断時年齢40歳未満(オッズ比[OR]:6.83、95%信頼区間[CI]:2.22~20.90)、トリプルネガティブ乳がん(OR:3.19、95%CI:1.20~8.43)、高悪性度(OR:1.68、95%CI:1.05~2.70)、卵巣がんの家族歴あり(OR:9.75、95%CI:2.65~35.85)が挙げられた。
・BRCA1/BRCA2/PALB2病的バリアント陽性の39例のうち13例(33.3%)がPARP阻害薬の適応であった。
(ケアネット 金沢 浩子)
【原著論文はこちら】









