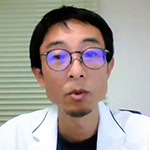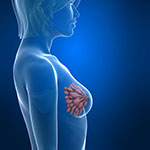提供元:CareNet.com

転移を有するHER2陽性またはHER2低発現の乳がん患者において、トラスツズマブ デルクステカン(T-DXd)と放射線の併用療法は治療上の利点が期待される一方で、安全性と実現可能性に関するエビデンスは限られている。今回、T-DXd治療と放射線療法を同時に併用しても重篤な毒性や治療継続を妨げる毒性の増加は認められなかったことを、イタリア・Azienda Ospedaliero-Universitaria CareggiのLuca Visani氏らが明らかにした。The Breast誌2026年1月2日号掲載の報告。
転移乳がんの治療では全身治療が病勢コントロールの中心であるが、放射線療法も症状緩和や局所制御のために用いられる。そこで研究グループは、T-DXd治療中に放射線療法を同時に併用しても安全かどうかを後ろ向きに検証した。
対象は、イタリア、スロベニア、オーストリア、スウェーデンの6施設で2021年5月~2024年5月にT-DXd治療(±放射線療法)を受けた転移を有するHER2陽性またはHER2低発現の乳がん患者であった。併用療法の定義は、T-DXd治療中または治療開始10日以内に実施された放射線療法とした。主要評価項目は併用療法とGrade3以上の有害事象(AE)との関連で、副次評価項目は無増悪生存期間(PFS)や全生存期間(OS)などであった。
主な結果は以下のとおり。
・全体(147例)の年齢中央値は49歳で、T-DXd+放射線群(67例)は45歳、T-DXd単独群(80例)は53歳であった。脳転移を有する患者はT-DXd+放射線群のほうが多かった(55.2%vs.22.5%)。放射線の照射部位は中枢神経系が最多であった(54.9%)。T-DXd開始からの追跡期間中央値は9(範囲:0.5~46)ヵ月であった。
・Grade3以上のAEは24例(16.3%)に発現し、T-DXd+放射線群(11.9%)とT-DXd単独群(20.0%)の間に有意差は認められなかった(p=0.30)。
・毒性によるT-DXdの中止は19例(12.9%)で、T-DXd+放射線群とT-DXd単独群で同等であった(11.9%vs.13.8%)。
・頭蓋内への放射線照射後に症候性放射線壊死が1例(1.5%)報告された。
・間質性肺疾患は、T-DXd+放射線群で7例(10.4%)、T-DXd単独群で7例(8.8%)に発現した。
・探索的解析では、放射線併用によるPFSまたはOSへの悪影響は示されなかった。
研究グループは「これらの結果は、HER2陽性またはHER2低発現の転移乳がん患者に対するT-DXdと放射線療法の併用療法は実行可能で忍容性も高いことを示唆するものである。T-DXdと放射線療法の最適な順序、安全性および有効性をより明確にするためには前向き研究が必要である」とまとめた。
(ケアネット 森)
【原著論文はこちら】