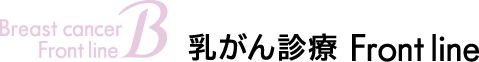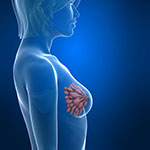提供元:CareNet.com

局所進行切除不能または転移のあるホルモン受容体陽性(HR+)/HER2陰性(HER2-)乳がん患者における内分泌療法(ET)後の1次治療として、サシツズマブ ゴビテカン(SG)は医師選択の化学療法と比較して、統計学的に有意な無増悪生存期間(PFS)の延長を示さなかった。米国・メモリアルスローンケタリングがんセンターのKomal Jhaveri氏が、日本も参加している第III相ASCENT-07試験の主要解析結果を、サンアントニオ乳がんシンポジウム(SABCS2025、12月9~12日)で発表した。
・試験デザイン:第III相非盲検無作為化試験
・対象:局所進行切除不能または転移のあるHR+/HER2-乳がん患者(進行がんに対する化学療法歴がなく、以下のうち1つ以上に該当:2ライン以上のET±標的療法後に進行/1次治療としてのET±CDK4/6阻害薬開始後<6ヵ月に進行/術後ET+CDK4/6阻害薬開始後<24ヵ月に再発し追加のETの対象外)
・試験群:SG(21日サイクルの1日目と8日目に10mg/kg点滴静注) 456例
・対照群:医師選択治療(カペシタビンもしくはパクリタキセルもしくはnab-パクリタキセル) 234例
・評価項目:
[主要評価項目]盲検下独立中央判定(BICR)によるPFS
[重要な副次評価項目]全生存期間(OS)、BICRによる奏効率(ORR)、QOL
[その他の副次評価項目]治験責任医師評価によるPFS、ORR、安全性など
・観察期間中央値:15.4ヵ月(データカットオフ:2025年9月15日)
主な結果は以下のとおり。
・ベースライン特性は両群でバランスが取れており、年齢中央値はSG群57歳vs.対照群58歳、HER2発現状態はIHC 0が42%vs.43%、転移の診断から無作為化までの期間中央値は23.9ヵ月vs.26.2ヵ月、内臓転移ありが89%vs.88%、肝転移ありが70%vs.67%であった。
・前治療歴については、治療ライン中央値はともに2ライン、ET+CDK4/6阻害薬治療歴ありがSG群91%vs.対照群92%、CDK4/6阻害薬による治療期間≦12ヵ月が43%vs.42%であった。
・BICRによるPFS中央値は両群で8.3ヵ月(層別ハザード比[HR]:0.85、95%信頼区間[CI]:0.69~1.05、p=0.130)で、SG群における統計学的に有意な改善は認められなかった。
・BICRによるPFSのサブグループ解析の結果は、全体集団とおおむね一致していたが、HER2 IHC 0の患者ではSG群で数値的に良好な傾向を示した。
・治験責任医師評価によるPFS中央値はSG群8.4ヵ月vs.対照群6.4ヵ月(層別HR:0.78、95%CI:0.64~0.93、名目上のp=0.008)であり、SG群で数値的な改善傾向を示した。
・OSデータは未成熟であり(maturity:27%)、OS中央値は両群ともに未到達であったが、SG群で良好な傾向が示された(HR:0.72、95%CI:0.54~0.97、名目上のp=0.029)。
・試験治療中止後の次治療は、ADCがSG群32%vs.対照群61%、化学療法が84%vs.66%などであった。
・BICRによるORRはSG群37%(CR:1%)vs.対照群33%(CR:0%)、奏効期間中央値は12.1ヵ月vs.9.3ヵ月であった。
・Grade3以上の試験治療下における有害事象(TEAE)はSG群72%vs.対照群48%で発現し、TEAEによる治療中止は3%vs.7%であった。SG群の安全性プロファイルはこれまでの報告と一致しており、多く発現したGrade3以上のTEAEは、好中球減少症(56%)、白血球減少症(14%)、貧血(10%)などであった。
Jhaveri氏は、TROPiCS-02試験に基づき、SGはHR+/HER2-転移乳がんに対する内分泌療法および化学療法後の標準治療として引き続き位置付けられるとした(本邦では2025年12月25日現在未承認)。なお、ASCENT-07試験は進行中で、OSが継続して評価される予定。
(ケアネット 遊佐 なつみ)
【参考文献・参考サイトはこちら】