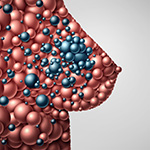提供元:CareNet.com

アストラゼネカは、カピバセルチブ(商品名:トルカプ)について、「HR+HER2- 転移・再発乳癌治療の新たな一手~世界初のAKT阻害薬カピバセルチブとは?~」と題したメディアセミナーを2024年6月21日に開催した。
本セミナーでは、がん研有明病院 乳腺センター センター長の上野 貴之氏より、カピバセルチブの臨床成績および遺伝子検査の現状について語られた。
カピバセルチブの作用機序
閉経後ホルモン受容体(HR)陽性HER2陰性転移・再発乳がんに対する1次内分泌療法として、非ステロイド性アロマターゼ阻害薬とCDK4/6阻害薬の併用が標準的に使用されているが、2次内分泌療法の最適な治療選択は確立されていない。そこでAKT阻害薬カピバセルチブなどの新たな治療選択肢が期待されている。
カピバセルチブは、PI3K/AKT/PTENシグナル伝達経路にあるAKTを阻害する。AKTの活性化が、がん細胞の生存や増殖を促進し、内分泌療法に対する抵抗性に関与するといわれており、HR陽性乳がん患者ではこれらの遺伝子変異が観察されることから治療ターゲットとして注目されている。AKTを阻害することで経路全体を抑えることができ、ホルモン療法に対する耐性を克服し、がん治療の効果を高めることが期待されている。
カピバセルチブの臨床成績
アロマターゼ阻害薬を含む内分泌療法後に増悪した、エストロゲン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能または再発乳がん患者を対象とした、第III相試験(CAPItello-291試験)について紹介された。患者背景を見ると、約70%の患者がCDK4/6阻害薬による前治療を受けており、PIK3CA、AKT1、PTEN遺伝子のいずれかの変異がある患者は約40%、変異がない患者は約56~62%であり、約15%は変異の有無が不明である。
有効性については、PIK3CA、AKT1、PTEN遺伝子変異が1つ以上認められる集団において、カピバセルチブとフルベストラント(商品名:フェソロデックス)の併用療法が、フルベストラント単剤療法と比較し、病勢進行または死亡のリスクを50%低下させることが示された(ハザード比:0.50、95%信頼区間:0.38~0.65、p<0.001、無増悪生存期間[PFS]中央値:7.3ヵ月vs.3.1ヵ月)。上野氏は「カピバセルチブ併用群では投与開始2~4ヵ月後のPFSの落ち込みの抑制が見られる。早期の治療効果判定は、医師と患者間の良好な関係を保つうえでも重要なポイントだ」と語った。
安全性については主に高血糖、下痢、皮膚障害に触れ、「有害事象のマネジメントは早めに対応しながら、必要に応じて休薬や減量による用量調節が重要である。また本剤の用法は4日間連続して服薬し、その後3日間の休薬を1サイクルとしているため、飲み間違えないよう注意が必要だ」と上野氏は解説した。
遺伝子検査の現状
カピバセルチブを投与するに当たってはPIK3CA、AKT1またはPTEN遺伝子変異を有する患者が対象とされる。この遺伝子変異を検出するためには「FoundationOne CDx がんゲノムプロファイル」によるコンパニオン診断が必要であるが、コンパニオン診断可能施設は、がんゲノム医療の中核拠点病院や拠点病院、連携病院と限られる。同氏は、「自施設で検査ができない場合は連携病院などに依頼しなければならない点が課題である。今後はより依頼しやすい連携がつくられることが望まれる」と述べている。
(ケアネット 寺井 宏太)
【参考文献・参考サイトはこちら】