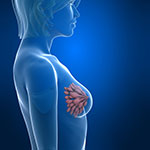提供元:CareNet.com

StageII/IIIのトリプルネガティブ乳がん(TNBC)の術前療法として、アントラサイクリンを含まないカルボプラチン(CBDCA)+パクリタキセル(PTX)にアテゾリズマブの追加を評価する無作為化第II相試験において、病理学的完全奏効(pCR)率の有意な増加が示された。米国・ワシントン大学のFoluso O. Ademuyiwa氏らが、NPJ Breast Cancer誌2022年12月30日号に報告。
これまで、転移を有するPD-L1陽性TNBCを対象としたIMpassion130試験ではnab-PTXへのアテゾリズマブ追加による無増悪生存期間と全生存期間の改善、また早期TNBCを対象としたIMpassion031試験ではアテゾリズマブとアントラサイクリンおよびタキサンをベースとした術前化学療法によるpCR改善が報告されている。
本試験では、StageII/IIIのTNBC 67例(年齢中央値:52歳、範囲:25~78歳)をArm A(CBDCA+PTX)22例、Arm B(CBDCA+PTX+アテゾリズマブ)45例に無作為に割り付け、アテゾリズマブ追加でpCR率および腫瘍浸潤リンパ球(TIL)の割合が増加するかどうかを、修正ITT集団(評価可能で1回以上併用療法を受けた全患者)で評価した。
主な結果は以下のとおり。
・修正ITT集団において、pCR率はArm Aで18.8%(95%信頼区間[CI]:4.0~45.6)、Arm Bで55.6%(同:40.0~70.4)だった(群差の推定値:36.8%、95%CI:8.5~56.6、p=0.018)。
・Grade3以上の治療関連有害事象は、Arm Aで62.5%、Arm Bで57.8%に発現した。
・TILの割合は、ベースラインから第1サイクルまで、Arm A(平均±SD:0.6%±21.0%)およびArm B(同:5.7%±15.8%)ともわずかに増加した。
・TILの割合の中央値は、pCR例(24.8%)で非pCR例(14.2%)より高かった(p=0.02)。
本試験において、術前化学療法のみよりアテゾリズマブ追加でpCR率が有意に高かった。著者らは「非アントラサイクリンベースの化学療法+免疫療法は、早期TNBC治療の代替オプションとなる可能性がある」としている。
(ケアネット 金沢 浩子)
【原著論文はこちら】