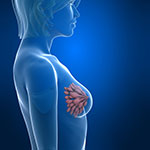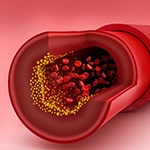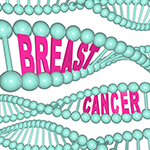提供元:CareNet.com

トラスツズマブ デルクステカン(T-DXd)によるがん治療におけるGrade1の間質性肺疾患(ILD)発症後、回復および適切な管理の実施後であれば、T-DXd再投与が有用な可能性が示唆された。米国・UCSF Helen Diller Family Comprehensive Cancer CenterのHope S.Rugo氏が乳がん、肺がん、胃がんなど9つの臨床試験の後ろ向きプール解析結果を欧州臨床腫瘍学会乳がん(ESMO Breast Cancer 2024、5月15~17日)で報告した。T-DXdによる再治療を受けた患者の約69%は減量しておらず、約67%はILDの再発がなかった。また約18%は1年超再治療を継続していた。
本プール解析では、T-DXd(5.4~8.0mg/kg)単剤療法を1回以上受けたHER2陽性の乳がん、非小細胞肺がん、胃がん、大腸がんの患者を対象とした9つの臨床試験のデータを用いて、Grade1の初回ILD後の患者を対象に、T-DXdによる再治療期間とILD再発について評価した。
主な結果は以下のとおり。
・9試験から2,145例が解析対象とされた。べースラインの患者特性は、年齢中央値が58.0歳、日本の患者が27.3%、乳がん患者が68.2%を占め(肺がん16.3%、胃がん13.7%、大腸がん0.9%など)、肺の併存疾患なしが94.3%、SpO2≧95%が94.5%、T-DXdの用量5.4mg/kgの患者が67.6%であった。
・193例が治験責任医師評価によりGrade1の薬剤関連ILDと判定され、うち97例(50.3%)がステロイドによる治療を受け、45例(23.3%)がT-DXdによる再治療を受けていた。
・初回のILD発症からT-DXdによる再治療開始までの期間中央値は28(8~48)日であった。
・45例中31例(68.9%)が減量なくT-DXdによる再治療を行い、15例(33.3%)は>6ヵ月、8例(17.8%)は>12ヵ月T-DXdによる再治療を継続していた。
・45例中15例(33.3%)がILD再発を経験しており、Grade1が40.0%、Grade2が60.0%であった。8例がステロイドによる治療を受けており、うち6例が回復/後遺症を伴う回復をしていた。≧Grade3のILDおよび再発ILDのアウトカムとしての死亡は確認されていない。
Rugo氏は、より大きなデータセットでのリアルワールド研究が必要としたうえで、適切なモニタリングと管理によりGrade1のILDから完全に回復後のT-DXd再治療は、治療によるベネフィットを最大化する可能性があるとまとめている。
(ケアネット 遊佐 なつみ)