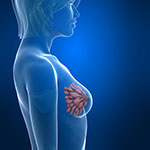提供元:CareNet.com

乳がん患者にとってアンメットニーズとされている術後放射線治療による放射線皮膚障害(RID)について、緑茶に多く含まれるカテキン(epigallocatechin-3-gallate:EGCG)を主成分とした溶剤の予防的塗布が有効であることが示された。中国・山東第一医科大学のHanxi Zhao氏らによる第II相無作為化試験の結果で、EGCG溶液の予防的塗布により、RIDの発生率と重症度が大幅に低下したという。安全性プロファイルの忍容性も高かった。結果を踏まえて著者は、「RIDリスクがある乳がん患者にとって、便利で忍容性が高い有効な選択肢となる可能性がある」と述べている。JAMA Dermatology誌オンライン版2022年6月1日号掲載の報告。
研究グループは、乳がん術後に放射線治療を受ける患者における、EGCG溶液塗布が、RIDの発生を抑制するかを調べる第II相二重盲検プラセボ対照無作為化試験を実施した。2014年11月~2019年6月に山東がん病院研究所で術後放射線治療を受ける180例が試験に登録された。
被験者は2対1の割合で、放射線治療1日目~同治療完了後2週間まで、放射線の全照射野にEGCG溶液(660μmol/L)塗布を受ける群またはプラセボ(0.9%塩化ナトリウム溶液)塗布を受ける群に割り付けられ、追跡を受けた。データ解析は、2019年9月~2020年1月に行われた。
主要評価項目は、Grade2以上(Radiation Therapy Oncology Groupスケールによる定義で、数値が大きいほど悪化)のRIDの発生率。副次評価項目は、RID指数(RIDI)、症状指数、赤外線サーモグラフィーで測定した皮膚温および安全性などであった。
主な結果は以下のとおり。
・全適格患者180例のうち、165例(EGCG溶液塗布群111例、プラセボ群54例、年齢中央値46歳[範囲:26~67])が有効性の評価を受けた。
・Grade2以上のRID発生率は、プラセボ群(72.2%、95%信頼区間[CI]:60.3~84.1)よりEGCG群(50.5%、41.2~59.8)で有意に低かった(p=0.008)。
・EGCG群の平均RIDIは、プラセボ群よりも有意に低かった。さらに、症状指数もEGCG群で有意に低かった。
・EGCG治療関連の有害事象は4例(3.6%)で報告された。3例(2.7%)がGrade1の刺すような痛み、1例(0.9%)はかゆみであった。
(ケアネット)
【原著論文はこちら】
Zhao H, et al. JAMA Dermatol. 2022 Jun 1. [Epub ahead of print]