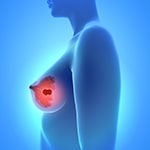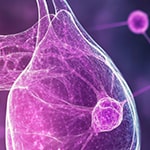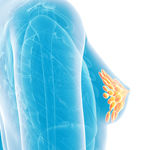提供元:CareNet.com

スウェーデン・カロリンスカ研究所のZiyan Ma氏らの研究チームは観察研究において、初回マンモグラフィの受診勧奨に応じず受診しなかった女性は、受診勧奨に応じ受診した女性と比較して、乳がん発見時の腫瘍の悪性度が高く長期的な乳がん死のリスクが顕著に増加しているが、乳がん発生率は同程度であることを示した。研究の成果は、BMJ誌2025年9月24日号で報告された。
初回の受診勧奨を受けた約43万例の女性を解析
研究チームは、初回マンモグラフィの受診勧奨に応じなかった女性における、その後の受診状況および乳がんのアウトカムを評価する目的で、住民ベースのコホート研究を実施した(スウェーデン研究会議などの助成を受けた)。
1991~2020年に、同国ストックホルム県でSwedish Mammography Screening Programmeの受診勧奨を受け取り、初回の受診勧奨時の年齢が50歳(2005年7月以前)または40歳(2005年7月以降)の女性43万2,775例を解析の対象とした。初回の受診勧奨前にがんの診断を受けた女性は除外した。
2023年までの追跡期間(最長25年)における、受診、乳がん発生、腫瘍特性、乳がん死について調査した。
非受診者は受診率が継続的に低く、StageIII、IVの割合が高い
494万375人年の追跡期間中に、1万6,059例で新たに乳がんが発生した。初回マンモグラフィの受診勧奨を受けた女性のうち、29万4,015例(68.9%)が実際に検診を受け、13万8,760例(32.1%)は受診しなかった。
初回検診の非受診者は、その後の検診でも受診率が継続的に低く、症状の発現によって発見されて進行乳がんと診断される確率が高かった。具体的には、初回検診の非受診者は受診者に比べ、StageIII(4.1%vs.2.9%、オッズ比[OR]:1.53[95%信頼区間[CI]:1.24~1.88])およびStageIV(3.9%vs.1.2%、3.61[2.79~4.68])の乳がんの割合が高かった。
非受診者の乳がん死の増加は、発見の遅れを反映する可能性
681万8,686人年の総追跡期間中に、1,603例が乳がんにより死亡した。初回検診の非受診者は乳がん死のリスクも高く、25年間の累積乳がん死亡率は、初回検診の受診者が7.0/1,000例であったのに対し、非受診者は9.9/1,000例だった(補正後ハザード比:1.40、95%CI:1.26~1.55)。
これに対し、25年間の累積乳がん発生率は両群で同程度(受診者7.8%vs.非受診者7.6%)であった。このことから、初回検診の非受診者における乳がん死亡率の増加は、発生率の上昇ではなく、発見の遅れを反映している可能性が高いという。
著者は、「これらのデータは、初回検診の非受診者が、乳がんによる死亡の長期リスクを有する大規模な集団であることを示している。この高リスク集団は、検診受診率の向上と、それによる死亡リスクの低減を目的とする、対象を絞った介入の機会を提供するものである」「初回検診非受診は、回避可能な乳がん死の早期かつ対応可能な予測因子として優先的に取り組むべき課題である」「本研究の知見は、他のがんの検診プログラムへの示唆をも含むものである」としている。
(医学ライター 菅野 守)
【原著論文はこちら】