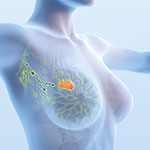提供元:CareNet.com
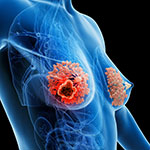
約1万8千例を含む大規模な転移乳がん患者コホートを対象に、サブタイプおよび治療ライン別の脳転移の有病率と累積発生率、またHER2低発現が脳転移発生率に及ぼす影響を評価した結果、すべてのサブタイプで治療ラインが進むごとに発生率が上昇し、HER2低発現は従来のサブタイプ分類における発生率に影響を及ぼさないことが示唆された。米国・ダナ・ファーバーがん研究所のSarah L Sammons氏らによるJournal of the National Cancer Institute誌オンライン版2025年3月31日号への報告。
本研究では、電子カルテに基づく全国規模の匿名化データベースが用いられた。主要評価項目は脳転移の初回診断とし、HER2低発現を含む転移乳がんのサブタイプおよび治療ライン別に、脳転移の有病率および発生率を推定した。全身治療開始時に脳転移を有さなかった患者における脳転移リスクは、累積発症率関数を用いて推定した。すべてのp値は両側検定に基づき、p≦0.05を統計学的有意とした。
主な結果は以下のとおり。
・1万8,075例の転移乳がん患者のうち、1,102例(6.1%)は初回治療開始時点ですでに1つ以上の脳転移を有していた。
・残る1万6,973例における脳転移の累積発生率(60ヵ月時点)は、ホルモン受容体陽性(HR+)/HER2陰性で10%、HR+/HER2陽性で23%、HR陰性/HER2陽性で34%、トリプルネガティブ乳がん(TNBC)で22%であった。
・HR+/HER2陰性およびTNBCサブタイプにおけるHER2低発現の、脳転移発生率への影響はみられなかった。
・すべての乳がんサブタイプにおいて、治療ラインが進むごとに脳転移の有病率は上昇していた。
(ケアネット 遊佐 なつみ)
【原著論文はこちら】
Sammons SL, et al. J Natl Cancer Inst. 2025 Mar 31. [Epub ahead of print]