提供元:CareNet.com
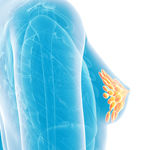
体幹部定位放射線治療(SBRT)+標準ケアの全身性治療(標準治療)は標準治療単独と比較して、無増悪生存期間(PFS)を延長することが示された。ただし、オリゴ転移のある非小細胞肺がん(NSCLC)患者で、SBRT+標準治療は標準治療単独と比較してPFSを4倍以上延長し、有効性のある治療となる可能性が示された一方で、オリゴ転移のある乳がん患者ではベネフィットは観察されなかった。米国・スローン・ケタリング記念がんセンターのChiaojung Jillian Tsai氏らによる第II相非盲検無作為化試験の結果で、著者は「さらなる検討を行い、今回示された所見を検証し、ベネフィットが異なった要因を明らかにする必要がある」とまとめている。転移のあるがん患者の多くは、最終的に全身性治療に対する耐性を獲得し、一部の患者は限定的な病勢進行(すなわちオリゴ転移)を有する。研究グループは、オリゴ転移病変を標的としたSBRTが患者アウトカムを改善可能か評価した。Lancet誌オンライン版2023年12月14日号掲載の報告。
オリゴ転移のある乳がんまたはNSCLC患者を対象に無作為化試験
試験は、18歳以上で、少なくとも1次治療の全身性治療を受けたオリゴ転移(PET-CTまたはCTで進行病変が5つ以下)のある、乳がんまたはNSCLCの患者を対象に行われた。
被験者は、ニューヨーク市にある3次がんセンターと、ニューヨーク州とニュージャージー州にある6つの関連地域センターで登録され、1対1の割合で標準治療群またはSBRT+標準治療群に無作為化された。無作為化はコンピュータベースのアルゴリズムを用いて行われ、転移病変数、レセプターまたはドライバー遺伝子変異の状態、原発巣、前治療の全身性治療の種類で層別化した。患者と試験担当医は治療割り付けをマスキングされなかった。
主要評価項目はPFSで、最長12ヵ月まで測定した。事前規定に基づき、疾患部位別に主要評価項目のサブグループ解析を行った。すべての解析はITT集団で行った。
SBRT+標準治療群のPFSが有意に延長
2019年1月1日~2021年7月31日に、106例が標準治療群(51例[乳がん患者23例、NSCLC患者28例])またはSBRT+標準治療群(55例[24例、31例])に無作為化された。乳がん患者47例のうち16例(47%)がトリプルネガティブであり、NSCLC患者59例のうち51例(86%)は臨床的有用性の期待できる(actionable)ドライバー遺伝子変異を有していなかった。
試験は、事前に計画された中間解析中に主要有効性評価項目が達成されたため、目標サンプルサイズを満たす前に終了となった。
追跡期間中央値は、標準治療群11.6ヵ月、SBRT+標準治療群12.1ヵ月であった。PFS中央値は標準治療群3.2ヵ月(95%信頼区間[CI]:2.0~4.5)、SBRT+標準治療群7.2ヵ月(4.5~10.0)であった(ハザード比[HR]:0.53、95%CI:0.35~0.81、p=0.0035)。
PFS中央値は、SBRT+標準治療を受けたNSCLC患者のほうが標準治療のみを受けた同患者よりも有意に延長した(10.0ヵ月[95%CI:7.2~未到達]vs.2.2ヵ月[2.0~4.5]、HR:0.41[95%CI:0.22~0.75]、p=0.0039)。しかし、乳がん患者では同様の所見は認められなかった(4.4ヵ月[2.5~8.7]vs.4.2ヵ月[1.8~5.5]、HR:0.78[0.43~1.43]、p=0.43)。
Grade2以上の有害事象が、標準治療群で21例(41%)、SBRT+標準治療群で34例(62%)報告された。SBRT+標準治療群の9例(16%)では、SBRTに関連したGrade2以上の毒性(胃食道逆流症、疼痛増悪、放射線肺臓炎、腕神経叢損傷、血球数低下など)が報告された。
(ケアネット)
【原著論文はこちら】






