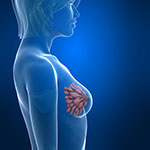提供元:CareNet.com

4年ぶりに乳癌診療ガイドラインが全面改訂され、第30回日本乳癌学会学術総会で「乳癌診療ガイドライン2022年版 改定のポイント」と題したプログラムが開催された。本稿では、治療編(薬物療法、外科療法、放射線療法)の主な改訂点について紹介する。治療編全体における改訂点として、今版では冒頭に「総説」を追加。病気/サブタイプ別の治療方針のシェーマや各CQ/BQ/FRQの治療における位置付けを解説し、治療全体の流れを理解できる構成となっている。
薬物療法:術後アベマシクリブ&S-1、周術期免疫療法等についてCQ新設
薬物療法については遠山 竜也氏(名古屋市立大学)が登壇し、6つの新設CQを中心に解説。まず、早期乳がんに対するエスカレーション治療として、術後のアベマシクリブとS-1について2つのCQが新設された。アベマシクリブはmonarchE試験の結果から、ホルモン受容体陽性/HER2陰性で再発高リスクの患者に対する術後療法として「内分泌療法にアベマシクリブを2年間併用することを強く推奨」(CQ6)。S-1は現在承認申請中であるものの、POTENT試験の結果に基づき「内分泌療法にS-1を1年間併用することを強く推奨」した(CQ5)。両療法における“再発高リスク”の考え方についてはそれぞれ適格基準の表を挿入したほか、総説でその位置づけを解説。遠山氏は「POTENT試験のほうが対象が広いので、そちらにしか該当しない症例にはS-1を、両基準に合致する症例は副作用のプロファイルや投与期間を考慮して使っていくことになるのではないか」と述べた。
周術期の免疫療法として、現在承認申請中ではあるが、トリプルネガティブ乳がん(TNBC)に対するペムブロリズマブについてもCQが新設された。KEYNOTE-522試験の結果に基づき、周術期TNBCに対して「ペムブロリズマブの投与を弱く推奨」している(CQ16)。“弱く”という表現になった理由について同氏は、有害事象があること、どのような患者に対して投与すべきかに充分なコンセンサスがないことを指摘。「今回は先取りして取り上げ、このような表現となっているが、承認されたときには改めてディスカッションが必要」とした。
閉経前のホルモン受容体陽性/HER2陰性転移・再発乳がんに対する一次治療としてのCDK4/6阻害薬について、今回初めてCQが設けられた。日本で承認済のパルボシクリブ・アベマシクリブについては閉経後患者対象の試験でPFS改善が報告されているが、リボシクリブについてのMONALEESA-7試験では閉経前の患者でPFSおよびOSが改善している。併用薬については、タモキシフェンとの併用群でQT延長がみられたことでFDA承認が見送られていることから、本ガイドラインにおいても非ステロイド性アロマターゼ阻害薬との併用が推奨された(CQ18)。
その他、「残存病変に基づく治療選択」として、術後のカペシタビン(HER2陰性)とT-DM1(HER2陽性)について2つのCQが新設されている(CQ10、CQ13)。
外科療法:NAC後センチネルリンパ節生検について一部推奨内容を変更
九冨 五郎氏(札幌医科大学)は外科療法における今回の改訂の目玉としてCQ2を挙げた。まずCQ2aでは、術前化学療法(NAC)前後の臨床的リンパ節転移陰性(cN0)乳がんに対する腋窩リンパ節郭清省略を目的としたセンチネルリンパ節生検について、2018年版では“弱く”推奨していたものを、今版では“強く”推奨に変更している。理由について同氏は、「新しい強力なデータが出たわけではないが、日常診療で9割近い先生が実施しているのなら、それはもう“強い”推奨ではないか、というボードでの議論を経て、変更している」と解説した。
臨床的リンパ節転移陽性(cN+)でNAC 後cN0の症例に対しては、今回新たにtailored axillary surgery (TAS)を行う場合について推奨を追加。「TASによる腋窩リンパ節郭清省略を行うことを弱く推奨」とされた(CQ2b)。九冨氏は、現在targeted axillary dissection (TAD)の妥当性を検討する前向き試験が国内で進行中であることに触れ、「こういったデータが出てくれば、またガイドラインの記述も変わってくる可能性がある」とした。
Stage IV乳がんに対する原発巣切除については、今版ではメタ解析の結果を考慮して「予後の改善を目的とした原発巣切除は行わないことを強く推奨(CQ4a)」としたほか、「局所制御を目的とした原発巣切除は行うことを弱く推奨(CQ4b)」とされた。
また、今後保険収載される可能性を考慮し、乳房再建法としての脂肪注入について新規のFRQが追加された。「細心の注意のもとに行ってもよい」という記述となっている(FRQ6)。
2018年版で8つあったCQは今版では4つとなり、それぞれFRQやBQに変更して取り上げられている。例えば低リスクDCISに対する非切除の意義については、日本も含め現在複数の無作為化試験や観察研究が進行中であることから、今版ではFRQとして記述された(FRQ1)。九冨氏は外科領域では大規模な無作為化試験が組みづらくエビデンスレベルが低いのが現状としたうえで、日本での試験もいくつか進行中で、日本からの発信が増えていくことに期待したいと締めくくった。
放射線療法:寡分割照射推奨の対象者を拡大、APBIを非推奨→条件付きで推奨へ
放射線療法における今版での改訂・新設事項は以下の通り。吉村 通央氏(京都大学)がそれぞれの根拠となったデータとともに解説した。
改訂:CQ1 寡分割全乳房照射/CQ3 APBI/ CQ5 腋窩LN転移1~3個のPMRT
新設:BQ7 腫瘍径大および断端陽性のPMRT/FRQ2 RNI or PMRTの寡分割照射/ FRQ6オリゴ転移に対するSBRT
寡分割全乳房照射については、メタアナリシスの結果、局所再発率や全生存率、整容性に有意差はなく、急性皮膚障害についてはむしろ寡分割で低下しており、今版では「50歳以上、T1-2、化学療法を行っていない」という3条件以外の患者、これまで記載のなかったDCIS症例に対しても、寡分割照射を強く推奨している(CQ1)。
APBIの治療成績については4年間で長期の報告が複数出ており、それらのメタアナリシス結果から、若年ではない低リスク症例に十分な精度管理のもとで行うなどの条件付きで、非推奨から弱い推奨へ変更された(CQ3)。なお術中照射については、「全乳房照射より局所再発率が高いが全生存率には差がないことを説明した上で希望する患者に行うこと」とされた。
腋窩LN転移1~3個の患者に対するPMRTについては、EBCTCGや観察研究のメタアナリシスが行われている。それらを基に、ASCO/ASTRO/SSO PMRTガイドライン2016では、局所・領域再発率や乳がん死亡率を低下させるが、再発リスクの低い患者では害が益を上回る症例もあり、患者ごとに適応を決めるべきとされている。2018年版では、推奨の強さが合意に至らなかったが、今版では合意率は71%ではあったが「弱い推奨」に変更された。
リンパ節転移陰性で腫瘍径が大きい場合もしくは術後断端陽性の場合について、2018年版までは明記がなかったが、今版で初めて明記され、「PMRTを行うことが望ましい」とされた(BQ7)。
その他、2つのFRQが新設されている。1つ目は領域リンパ節照射あるいはPMRTにおける寡分割照射についてで、無作為化試験では治療効果・有害事象に有意差はなく、急性期皮膚炎は軽いことが報告されており、「エビデンスは十分ではないが総合的に検討して、行うことを考慮してもよい」とされた(FRQ2)。吉村氏は、新型コロナ流行の影響で、実際多くの施設でこの2年間は16回照射としていた状況があるとし、とくに有害事象は報告されていないと話した。
もう1つはオリゴ転移に対するSBRTについてで、無作為化第II相試験(SABR-COMET)の結果SBRTの追加で治療成績が良好との報告がある。同試験における乳がん症例は18%であることに注意が必要ではあるが、St Gallen2021でも80%以上のパネル医師がT2N1M1で根治を目指して局所治療を加えると回答している。そこで今版では、「症例を選択した上で考慮してもよい」とされている。ただし、今年のASCOで発表されたBR002試験の結果がネガティブだったことから、吉村氏は「今後の方向性に注意が必要」と指摘した。
(ケアネット 遊佐 なつみ)
【参考文献・参考サイトはこちら】