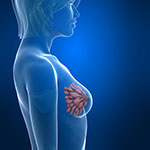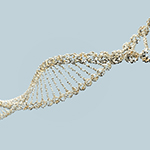提供元:CareNet.com

オリゴ転移乳がんの1次治療で、標準薬物療法に定位放射線治療(SBRT)もしくは外科的切除によるmetastases directed treatment(MDT)を追加しても、生存ベネフィットを得られないことが、第IIR/III相NRG-BR002試験で示された。米国・シカゴ大学のSteven J. Chmura氏が米国臨床腫瘍学会年次総会(2022 ASCO Annual Meeting)で発表した。
オリゴ転移乳がんに対しては、アブレーションにより無増悪生存(PFS)および全生存(OS)が改善されることが後ろ向き研究で示されているが、第III相試験のエビデンスはほとんどない。このNRG-BR002試験は、オリゴ転移乳がんの1次治療として、標準薬物療法にSBRT/外科的切除でのMDTを追加することによる生存へのベネフィットを検討した無作為化第IIR/III相試験である。
・対象:標準的画像診断で頭蓋外転移が4つ以下で、原疾患がコントロールされているオリゴ転移乳がん
・試験群(併用群):標準薬物療法(化学療法、内分泌療法、抗HER2療法)+全転移巣へのMDT
・対照群(薬物療法群):標準薬物療法のみ
・主要評価項目:第IIR相 PFS、第III相 OS
主な結果は以下のとおり。
・第IIR相への登録は129例、うち125例が適格だった(薬物療法群:65例、併用群:60例)。年齢中央値54歳、転移数は1つが60%、ERおよび/またはPR陽性かつHER2陰性が79%、トリプルネガティブが8%だった。無作為化後の治療について、併用群におけるMDTはSBRT93%、外科的切除2%、プロトコール外の治療5%、標準薬物療法は薬物療法群で化学療法28%、内分泌療法83%、併用群で化学療法27%、内分泌療法68%だった。追跡期間中央値は35ヵ月。
・PFS中央値は、薬物療法群23ヵ月、併用群19.5ヵ月で差は認められなかった(HR:0.92、70%CI:0.71~1.17、片側log-rank p=0.36)。
・OS中央値は両群とも未達で、36ヵ月OSは薬物療法群71.8%(95%CI:58.9~84.7)、併用群68.9%(同:55.1~82.6)だった(片側log-rank p=0.54)。
・治療失敗に関する解析では、薬物療法群でのindex領域/併用群での照射領域以外の新たな転移の発生率はどちらも40%程度だった。また、これらの領域内での新たな転移は、併用群(7%)のほうが薬物療法群(29%)より少なかった。
・ベースライン時の循環腫瘍細胞の有無別にみたPFSは同程度だった(HR:1.04、95% CI:0.54~2.02)。
・治療関連有害事象は、Grade4が薬物療法群で1例、Grade3が薬物療法群で6例(10%)、併用群で3例(5%)に発現した。
本試験では、MDT追加によるPFS改善を示すことができなかったため、第III相試験は中止される予定である。Chmura氏は「本試験で定義されたオリゴ転移乳がん患者はPFSおよびOSが長く、SBRTは標準薬物療法群と同様に安全で、有害事象発現率も低かった」と追加した。
(ケアネット 金沢 浩子)
【参考文献・参考サイトはこちら】