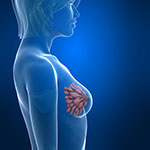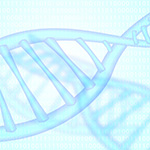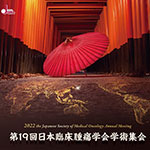提供元:CareNet.com

高リスクの早期トリプルネガティブ乳がん(TNBC)を対象に、術前補助療法としてペムブロリズマブ+化学療法併用を化学療法単独と比較、さらに術後補助療法としてペムブロリズマブとプラセボを比較した第III相KEYNOTE-522試験において、4回目の中間解析までにペムブロリズマブ群が術前補助療法による病理学的完全奏効率(pCR)および無イベント生存期間(EFS)を有意に改善した。今回、本試験のアジア人集団の 4 回目の中間解析結果について、北海道大学/国立病院機構北海道がんセンターの高橋 將人氏が、第18回日本臨床腫瘍学会学術集会(JSMO2022)で発表した。
[KEYNOTE-522試験]
・対象:治療歴がなく、原発巣の腫瘍径2cm以下でリンパ節転移あり(T1c、N1~2)またはリンパ節転移に関係なく腫瘍径2cm超(T2~4d、N0~2)で、遠隔転移がない(M0)ECOG PS 0/1のTNBC患者
・試験群:術前に化学療法(カルボプラチン+パクリタキセルを4サイクル後、ドキソルビシン/エピルビシン+シクロホスファミドを4サイクル)+ペムブロリズマブ(3週ごと)、術後にペムブロリズマブ(3週ごと)を9サイクルあるいは再発または許容できない毒性発現まで投与(ペムブロリズマブ群)
・対照群: 術前に化学療法+プラセボ、術後にプラセボを投与(プラセボ群)
・評価項目:
[主要評価項目]pCR(ypT0/Tis ypN0)、EFS
[副次評価項目]pCR(ypT0 ypN0およびypT0/Tis)、全生存期間(OS)、PD-L1陽性例におけるpCR・EFS・OS、安全性
アジア人集団における主な結果は以下のとおり。
・アジア(韓国、日本、台湾、シンガポール)から216 例が組み入れられた(ペムブロリズマブ群136例、プラセボ群80例)。
・データカットオフ(2021年3月23日)時点で、観察期間中央値は39.7ヵ月(範囲:10.0~46.9)、ペムブロリズマブ群およびプラセボ群でEFSイベントは13例(9.6%)および20 例(25.0%)で観察された。
・EFSのハザード比(HR)は、全集団の0.63(95%信頼区間[CI]:0.48~0.82)に対し、アジア人集団では0.35(95% CI:0.17~0.71)だった。
・術前補助療法でpCRを達成した患者と得られなかった(non-pCR)患者に分けて評価した場合、3年EFSは、pCR達成患者ではプラセボ群94.4%に対してペムブロリズマブ群100%、non-PCR患者ではプラセボ群62.8%に対してペムブロリズマブ群77.7%であった。
・安全性プロファイルは、アジア人集団において各レジメンや以前の解析と同様であった。
高橋氏は、EFSの結果がアジア集団でより有効に見えることについて、「アジア人集団は症例数が少ないので差があるとは言えず、ただ全集団と少なくとも同等の効果が期待できると言える」と述べた。また、non-pCRの場合の術後補助療法におけるカペシタビンの使用については、「ペムブロリズマブにカペシタビンを追加するのか、ペムブロリズマブを中止してカペシタビンを投与するのかは、トランスレーショナルに検討していく必要がある」とした。
(ケアネット 金沢 浩子)
【参考文献・参考サイトはこちら】