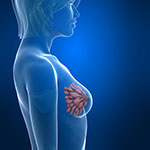提供元:CareNet.com

未治療の手術不能または転移を有するPD-L1 CPS
10以上のトリプルネガティブ(TN)乳がん患者において、ペムブロリズマブ+化学療法はプラセボ+化学療法と比較して、全生存(OS)期間を有意に改善した。米国・カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)包括的がんセンターのHope
S. Rugo氏が、第III相KEYNOTE-355試験におけるOSの最終解析結果を欧州臨床腫瘍学会(ESMO Congress
2021)で発表した。本邦では、PFSを有意に改善した同試験の中間解析結果を基に、2021年8月に承認されている。
・対象:18歳以上の手術不能な局所再発または転移を有するPD-L1陽性のTN乳がん(ECOG PS 0/1)847例
・ペムブロリズマブ群:ペムブロリズマブ(200mg、3週ごと)+化学療法(ナブパクリタキセル、パクリタキセル、ゲムシタビン/カルボプラチンの3種類のうちいずれか)566例
・プラセボ群:プラセボ+化学療法 281例
・層別化因子:化学療法の種類(タキサンかゲムシタビン/カルボプラチン)、PD-L1発現(CPS≧1かCPS<1)、術前/術後化学療法の有無
・評価項目:
[主要評価項目]PD-L1陽性患者(CPS≧10およびCPS≧1)およびITT集団におけるPFSと全生存期間(OS)
[副次評価項目]奏効率(ORR)、奏効期間(DOR)、病勢コントロール率(DCR)、安全性
主な結果は以下のとおり。
・データカットオフは2021年6月15日。観察期間中央値はペムブロリズマブ群が44.0ヵ月、プラセボ群が44.4ヵ月だった。
・ベースライン特性は両群でバランスがとれており、年齢中央値が53歳、CPS≧1が約75%、CPS≧10が約38%だった。試験で投与されたのはタキサンが約45%、ゲムシタビン/カルボプラチンが約55%。de
novo転移が約30%、無再発期間<12ヵ月が約20%だった。
・CPS≧10の患者におけるOS中央値は、ペムブロリズマブ群23.0ヵ月
vs.プラセボ群16.1ヵ月(ハザード比[HR]:0.73、95%信頼区間[CI]:0.55~0.95、p=0.0093)と有意な改善がみられた。OS率は18ヵ月時点でペムブロリズマブ群58.3%
vs.プラセボ群44.7%、24ヵ月時点で48.2% vs.34.0%だった。
・CPS≧10の患者におけるOSのサブグループ解析では、化学療法の種類や治療歴などによらずペムブロリズマブ群におけるベネフィットがみられたが、無再発期間<12ヵ月の患者ではみられなかった。ただし、サンプルサイズが小さいことには留意が必要となる。
・CPS≧1の患者におけるOS中央値は、ペムブロリズマブ群17.6ヵ月
vs.プラセボ群16.0ヵ月(HR:0.86、95%CI:0.72~1.04、p=0.0563)と事前に設定された有意性水準(p<0.0172)を満たさなかった。OS率は18ヵ月時点でペムブロリズマブ群48.4%
vs.プラセボ群41.4%、24ヵ月時点で37.7% vs.29.5%だった。
・ITT集団におけるOS中央値は、ペムブロリズマブ群17.2ヵ月
vs.プラセボ群15.5ヵ月(HR:0.89、95%CI:0.76~1.05)。OS率は18ヵ月時点でペムブロリズマブ群47.8%
vs.プラセボ群41.8%、24ヵ月時点で35.5% vs.30.4%だった。
・Grade3以上の治療関連有害事象は、ペムブロリズマブ群68.1%(死亡2例) vs.プラセボ群66.9%(死亡例なし)で報告された。
・Grade3以上の免疫関連有害事象は、ペムブロリズマブ群5.3% vs.プラセボ群0.0%で報告された。死亡例は報告されていない。多く報告されたのは甲状腺機能低下症・亢進症だった。
(ケアネット 遊佐 なつみ)
【参考文献・参考サイトはこちら】