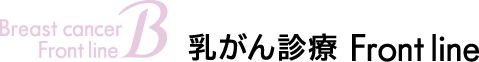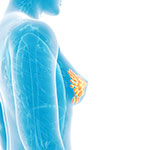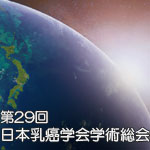提供元:CareNet.com

遺伝性乳癌卵巣癌(HBOC)の診療に関しては、2017年に「遺伝性乳癌卵巣癌(HBOC)診療の手引き」が刊行されている。HBOC既発症者へのリスク低減手術の保険収載や、膵がん・前立腺がんへのPARP阻害薬の承認など、遺伝子検査に基づく治療・マネジメントがいっそう求められる中、Minds「診療ガイドライン作成マニュアル2017」を遵守する形で、今回新たにガイドラインがまとめられた。2021年8月7日、webセミナー「遺伝性乳癌卵巣癌(HBOC)診療ガイドライン 2021年版の解説(主催:厚生労働科学研究費補助金[がん対策推進総合研究事業]「ゲノム情報を活用した遺伝性腫瘍の先制的医療提供体制の整備に関する研究」班)が開催され、各領域のポイントが解説された。
遺伝子診断・遺伝カウンセリング領域のポイント
遺伝子診断・遺伝カウンセリング領域の最も重要なコンセプトは「がん未発症と既発症を区別せず、遺伝的な特性としてHBOCを捉えるという点」と平沢 晃氏(岡山大学大学院医歯薬学総合研究科臨床遺伝子医療学)。BRCA遺伝情報を知ることのメリットは、(1)本人の治療法の選択、(2)本人のがん予防、(3)血縁者へのがん予防であると整理した。
現在、手術や検査の対象によって、保険収載と未収載が混在している状況がある。遺伝BQ1ではこれらの状況について整理している。遺伝BQ2では、表「NCCNガイドラインの遺伝学的検査の基準」を掲載し、どのようなクライエントにBRCA遺伝学的検査を推奨するかがまとめられている。平沢氏はこの表のうち、
・乳がんの発症者で
・45歳以下の発症
・50歳以下の発症で条件に当てはまる場合
・60歳以下のトリプルネガティブ乳がん
・年齢を問わず1人以上の近親者が条件に当てはまる場合
・卵巣がん発症者
・男性乳がん
について、2020年よりBRCA遺伝学的検査が保険診療の対象となったことを解説。その他(既知のBRCA1/2の病的バリアントを保持する家系の個人、膵がん、高グレード前立腺がんで条件に当てはまる場合、腫瘍プロフィール検査でBRCA1/2の病的バリアントを認めた場合)は未収載となっている。
また今回のガイドラインでは、「遺伝BQ10 生殖に関する遺伝カウンセリングにはどのように対応するべきか?」を新設。BRCA病的バリアント保持女性の妊孕性温存への対応フローが掲載されている。
乳がん領域のポイント
領域リーダーを務めた有賀 智之氏(都立駒込病院乳腺外科)はまず、BRCA遺伝学的検査を推奨する乳がん患者について、従来からの血縁者に乳がんまたは卵巣がん患者がいる場合のほか、膵がん患者がいる場合が追加されたことが大きな変更点とした(乳癌BQ1)。
BRCA病的バリアントを有する乳がん患者に対する乳房温存療法については、2017年版の手引きでは「推奨されない」となっていたのに対し、今回は「条件付きで行わないことを推奨する」と変更された(乳癌CQ3)。背景について同氏は、ガイドライン作成にあたり独自に実施されたメタアナリシスの結果、残存乳房内再発率が散発性乳がん患者と比較して高いこと、この傾向は観察期間が長くなるほど明確になることから、温存乳房内の新規発症リスクは長期に継続するものと推察されたと解説。一方で、生存率の悪化についてのデータは認められなかったことから、上記リスクや継続的なスクリーニングの必要性などを理解したうえで選択する場合は、否定しないという位置づけとした。
そのほか、RRMについては2020年4月に保険適応となり、乳がん既発症/未発症のいずれにおいても新規乳がんのリスク低減効果が示されている(乳癌CQ1、2)。造影乳房MRIについては、乳がん既発症/未発症のいずれも条件付きで推奨とされたが(乳癌CQ4、5)、乳がんも卵巣がんも未発症の場合BRCA病的バリアント保持者へのサーベイランスは保険未収載となっている。この点について同氏は、未発症者においてもMRIサーベイランスからのベネフィットは得られるので、早期に対応されることを期待したいと話した。
卵巣がん領域のポイント
卵巣がん領域では、領域リーダーを務めた岡本 愛光氏(東京慈恵会医科大学産婦人科学講座)が登壇、解説を行った。BRCA病的バリアント保持者に対するRRSOについて、標準的な術式として低侵襲(腹腔鏡)手術が推奨され、術中播種を予防するための手術操作が箇条書きで示された(卵巣癌BQ2)。RRSOの際の卵管の病理検索については、SEE-FIMプロトコールに準じることが条件付きで推奨され、条件付きとされた理由として、「STIC検出の臨床的意義が現状不確実であること、標本作成等で病理医の負担が増加することがある」と説明した(卵巣癌CQ2)。
卵巣がんに対する初回薬物療法としては、BRCA病的バリアント保持者においてもプラチナ製剤併用レジメンによるOSの有意な延長がRCT1報、症例対象研究5報で示されており、本ガイドラインでも推奨が示された(卵巣癌CQ3)。PARP阻害薬については、プラチナ製剤を含む初回化学療法後に奏効した同患者に対し、維持療法としての使用を条件付きで推奨するとされた。条件付きとされた理由は、薬剤費が高額なこと、二次がんを含めた長期合併症に関するデータが乏しいこと、至適投薬期間については不確実性が残ることが挙げられた。
前立腺がん領域のポイント
「BRCAバリアント陽性前立腺がんの大きな特徴は、診断時からのリンパ節転移・遠隔転移症例が有意に多いこと」と小坂 威雄氏(慶應義塾大学医学部泌尿器科教室)。前立腺がんの早期限局がんでの発見例の予後は非常によいことから、転移前にできるだけ早く見つけることが何よりも重要と話した。現在継続中の試験ではあるものの、大規模コホート研究であるIMPACT研究を根拠として、本ガイドラインでは未発症BRCAバリアントの男性保持者に対して、より低いPSAカットオフ値(3.0ng/mL)を用いて40歳からのサーベイランスを実施することを条件付きで推奨している(前立腺癌CQ1)。
また、前立腺がんにおいては生殖細胞系列だけでなく、体細胞系列のバリアントを有する症例が約半数いる。「家族歴が全くない転移前立腺がん患者さんの中にもBRCAバリアント保持者がいる可能性が指摘されている」と小坂氏は話し、BRCA遺伝学的検査の実施が推奨される前立腺がん患者の条件として、他のがん種で条件とされている家族歴のほか、「遠隔転移またはリンパ節転移を有する転移性前立腺がん患者」が加えられていることが大きな特徴とした(前立腺癌FQ1)。また治療については、2020年に新規内分泌療法後の転移を有する症例について、PARP阻害薬が保険収載された。同氏は、今後実臨床における有効性データが蓄積していくことが望まれると話した(前立腺癌FQ2)。
膵がん領域のポイント
膵がんにおいて、BRCAバリアント陽性患者は4~7%と報告されている。BRCA遺伝学的検査の実施が推奨される膵がん患者の条件としては、家族歴のほか、「遠隔転移を有するまたは術後再発」であることが示されている(膵癌FQ1)。尾阪
将人氏(がん研有明病院肝胆膵内科)は、「膵がんの治療選択肢は非常に限られており、遺伝学検査を行うことで選択肢を広げることの意義は大きい」と話した。
BRCAバリアント保持者に対する膵がんのスクリーニングの考え方に関して、同氏は遺伝子変異+膵がん家族歴の聴取が非常に重要と指摘。第一度近親者内に膵がん患者が1人以上おりかつBRCA2陽性の場合SIR(標準化罹患比)が5倍以上、第一度近親者内に膵がん患者が2人以上おりかつBRCA2陽性の場合、SIR(標準化罹患比)が30倍以上というデータを紹介した。本ガイドラインでは、「少なくとも1人の第一度近親者に膵がん家族歴のあるBRCA1、2病的バリアント保持者に対し、MRIまたは超音波内視鏡を用いたスクリーニングを考慮する」とされている(膵癌FQ2)。
治療については、POLO試験においてBRCA病的バリアントを有するプラチナ感受性切除不能膵がんに対する維持療法としてオラパリブがPFSを延長したことを根拠として、同患者に対する治療を条件付きで推奨している(膵癌CQ1)。同氏は留意点として、推奨文から下記を抜粋した:
・OSの延長効果を認めていないことを患者と共有したうえで投与することが望ましい
・BRCA病的バリアントを有する膵がん患者の家系に対しても、継続的な遺伝カウンセリングを実施していくことが望ましい
(ケアネット 遊佐 なつみ)
【参考文献・参考サイトはこちら】