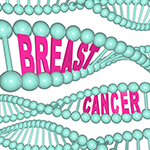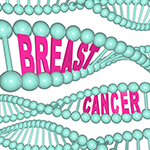提供元:CareNet.com
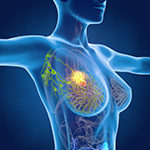
転移を有する乳がん(MBC)の治療はこの10年で大きく進歩している。フランス・Gustave RoussyのThomas
Grinda氏らが、全国的コホートであるESME(Epidemio-Strategy-Medico-Economical)-MBCのデータを用いて、2008~17年におけるMBCの全生存期間(OS)の変化をサブタイプ別に評価した結果、HER2陽性患者では改善し続けていることが示された。ESMO
Open誌2021年4月22日号に掲載。
ESME-MBCでは、フランスのがんセンター18施設で2008年以降に治療を開始したすべてのMBC患者のデータを収集している。この研究では、全体(2万446例)およびサブタイプごとのOSを調査した。サブタイプ別の患者数は、ホルモン受容体陽性(HR+)/HER2陰性(HER2-)患者が1万3,590例、HER2陽性(HER2+)患者が3,919例、トリプルネガティブ(TNBC)患者が2,937例。MBC診断年などの共変量で多変量解析を実施し、経年的なOS改善の可能性、MBC診断後に新規上市薬剤が投与された割合を評価した。
主な結果は以下のとおり。
・コホート全体の追跡期間中央値は65.5ヵ月(95%CI:64.6~66.7)だった。
・MBC診断年は、OSにおける強力な独立予後因子であった(2008年に対する2016年のハザード比[HR]:0.89、95%信頼区間[CI]:0.82~0.97、p=0.009)。この効果はHER2+患者(同HR:0.52、95%CI:0.42~0.66、p<0.001)の改善の影響が大きく、TNBC患者(同HR:0.93、95%CI:0.77~1.11、p=0.41)やHR+/HER2-患者(同HR:1.02、95%CI:0.91~1.13、p=0.41)においては持続的な効果はなかった。
・MBC診断年にかかわらず、HER2+患者における新規抗HER2薬が投与された割合は非常に大きかったが(2016年以降、患者の70%超がペルツズマブを投与されていた)、HR+/HER2-患者におけるエベロリムスとエリブリン、TNBC患者におけるエリブリンが投与された割合はどれも3分の1未満だった。
著者らは「おそらく、実臨床への浸透度が高い主要な抗HER2薬の上市に関連してHER2+MBC患者のOSが劇的に改善したが、他のサブタイプでは改善はみられなかった」と述べている。なお、CDK4/6阻害薬が投与された割合は急速に増加しているが、このコホートではまだその影響を評価できないという。
(ケアネット 金沢 浩子)
【原著論文はこちら】