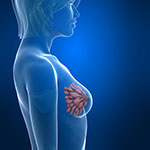提供元:CareNet.com
日本臨床腫瘍学会の専門医制度は、新専門医制度の中で主に内科を基本領域とする「サブスペシャルティ領域専門医」として日本専門医機構より認定された。名称は「腫瘍内科専門医」とされ、今秋・遅くとも来春からの研修開始を目指して最終調整が進められている。第18回日本臨床腫瘍学会学術集会(JSMO Virtual2021)ではこの新専門医制度についてシンポジウムが開催された。本稿では、その概要について解説した田村 研治氏(島根大学医学部附属病院先端がん治療センター)の講演内容を紹介する。
「がん薬物療法専門医」から「腫瘍内科専門医」へ、新制度をめぐる紆余曲折
2018年、日本専門医機構は「がん薬物療法専門医」を新専門医制度における「サブスペシャリティ領域専門医」として承認した。しかし2019年に厚生労働省・医道審議会医師分科会・医師研修部会が発足し、同新制度の問題点を指摘。サブスペシャリティ領域の承認基準や整備指針に不十分な点があるのではないかということで、見直しが図られた。
その結果、最終的に「がん薬物療法専門医」は「腫瘍内科専門医」に名称が変更され、内科のサブスペシャリティ領域の1つとして承認された。
腫瘍内科と呼吸器内科で異なる、サブスぺ領域の類型とは?
サブスペシャリティ領域は、研修実施の時期や考え方に応じて以下の3類型が設けられている。
1) 連動研修を行い得る領域:内科(ほか基本領域)の3年間の研修中に、いくつかの症例について連動して研修可能(消化器内科、呼吸器内科、血液内科など)
2) 連動研修を行わない領域:内科(ほか基本領域)の3年間の研修後に開始(腫瘍内科、アレルギー、感染症など)
3) 少なくとも1つのサブスペシャリティ領域を修得した後に研修を行う領域:(消化器内科→肝臓内科、消化器内視鏡など)
このうち、腫瘍内科は2)連動研修を行わない領域に位置づけられ、3年間の基本領域研修中にがんの症例を経験したとしても、研修経験は共有できない。また、複数のサブスペシャリティ領域の同時登録はできないため、例えば連動研修として呼吸器内科の研修を開始していた場合に、同時期に腫瘍内科での研修を開始することはできない。
しかし、サブスペシャリティ領域どうしの症例のオーバーラップは可能であり、田村氏は「例えば呼吸器内科領域で肺がんの症例を診ていて、2つめのサブスぺ領域として腫瘍内科を選択した場合には、双方の学会の同意のもと、腫瘍内科での症例としても認められることとなっている」と説明した。また、新専門医制度は5年をめどに制度が見直されることとされており、「将来的には、腫瘍内科についても連動研修が可能となるよう目指して体制の整備含め動いていきたい」と展望を示した。
新制度では主に内科を基本領域に
旧専門医制度での「がん薬物療法専門医」取得にあたっては、内科のほか外科、産婦人科、泌尿器科など14学会の専門医資格を基本資格としている。しかし、新専門医制度では、「腫瘍内科専門医」は日本内科学会を基本領域とする。この背景には、新制度では多くのサブスペシャリティ領域専門医の取得が実質的に難しいこと(原則として2領域)、「がん薬物療法専門医」取得者の基本領域は86%を日本内科学会が占めることがある。ただし、日本外科学会を基本領域としている医師も10%ほどおり、田村氏は「とくに乳がん領域で多く、今後日本外科学会については基本領域としての追加を検討していきたい」と話した。
なお、この変更は旧専門医制度「がん薬物療法専門医」取得者の更新には影響せず、例えば皮膚科を基本領域として「がん薬物療法専門医」を取得している医師の資格は失われない。
旧→新制度への今後の移行スケジュール
新専門医制度における内科専門研修1期生は、2018年から3年間の基本領域プログラムを受けており、本来であれば、2021年4月から腫瘍内科等のサブスペシャリティ領域の研修がスタート予定であった。しかし、新型コロナウイルス感染症等の影響で遅れが出ており、基本領域の試験は2021年7月4日に予定されている。「腫瘍内科専門医のモデルカリキュラムは9月頃にはホームページ上で公開予定となっており、J-OSLERの開始も遅くとも来春までには整えたい」と田村氏は説明した。なお、2021年4月からの症例については、さかのぼって実績に含めることができる。
今後数年は旧制度と新制度が並行する形となるが、2024年度頃におそらく最初の腫瘍内科専門医が誕生し、その後最終的には、旧制度は終了する予定との見通しを同氏は示した。参加者からは、「外科などの内科以外を基本領域とするがん薬物療法専門医は腫瘍内科専門医へ移行可能か?」という質問が寄せられた。同氏は、旧制度のがん薬物療法専門医は順次更新が行われるので、新専門医制度による影響は受けないことを説明。名称については今後更新の際に「がん薬物療法専門医」→「腫瘍内科専門医」と変更される可能性はあるが、資格としては変わらず更新が可能とした。
(ケアネット 遊佐 なつみ)
掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。
(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。)