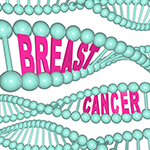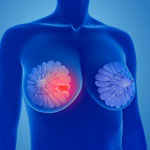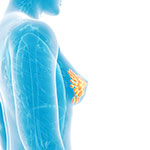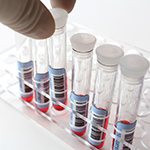提供元:CareNet.com
未治療の局所再発手術不適応または転移のあるPD-L1 CPS 10以上のトリプルネガティブ乳がん患者において、ペムブロリズマブ+化学療法はプラセボ+化学療法と比べて、無増悪生存(PFS)期間が有意かつ臨床的意義のある改善を示した。スペイン・Quiron GroupのJavier Cortes氏らによる第III相の国際多施設共同プラセボ対照二重盲検試験「KEYNOTE-355試験」の結果で、Lancet誌2020年12月5日号で発表された。著者は、「今回示された結果は、転移のあるトリプルネガティブ乳がんの1次治療について、標準治療へのペムブロリズマブ上乗せの意義を示すものである」と述べている。先行研究で同患者へのペムブロリズマブ単剤療法が、持続的な抗腫瘍活性と管理可能な安全性を示しており、研究グループは、同患者へのペムブロリズマブの上乗せが、化学療法の抗腫瘍活性を増強するかを検討した。
29ヵ国209ヵ所の医療機関で試験
KEYNOTE-355試験は、29ヵ国209ヵ所の医療機関を通じ、未治療の局所再発手術不適応または転移を有するトリプルネガティブ乳がん患者を無作為に2対1の2群に割り付け、一方にはペムブロリズマブ(200mg、3週間ごと)+化学療法(nabパクリタキセル、パクリタキセル、ゲムシタビン+カルボプラチンのいずれか)、もう一方にはプラセボ+化学療法を行った。無作為化は、ブロック法(ブロックサイズは6つ)および統合Web応答機能付き対話型音声応答システムを用い、化学療法のタイプ(タキサン系またはゲムシタビン+カルボプラチン)、ベースラインでのPD-L1発現(CPS 1以上または1未満)、同クラス薬剤による化学療法歴(術前・術後)で層別化も行った。
適格基準は、18歳以上、トリプルネガティブ乳がんを中央施設で確認、測定可能病変が1つ以上、中央検査施設でトリプルネガティブ乳がんの状態およびPD-L1の状態を免疫組織学的に検査するための新たな腫瘍病変が提供可能、ECOG PSが0または1、十分な臓器機能であった。試験のスポンサー、研究者、そのほか各地の試験スタッフ(マスクされなかった薬剤師は除く)および患者は、ペムブロリズマブまたはプラセボ投与について知らされず、患者ごとのPD-L1バイオマーカーの結果も知らされなかった。
主要評価項目は2つで、PD-L1 CPSが10以上の患者、CPSが1以上の患者、ITT集団のそれぞれにおけるPFSと全生存(OS)だった。PFSは今回の中間解析で評価し、OSの評価は追跡を継続している。PFSの評価には階層テスト戦略が用いられ、最初にPD-L1 CPSが10以上の患者で行われ(今回の中間解析の事前規定の統計学的基準はα=0.00411)、その後にCPSが1以上の患者(今回の中間解析のα=0.00111、CPSが10以上の患者のPFSからの部分的α値を含む)、最後にITT集団(今回の中間解析のα=0.00111)で評価した。
CPS 10以上の無増悪生存、ペムブロリズマブ群9.7ヵ月、プラセボ群5.6ヵ月
2017年1月9日~2018年6月12日に1,372例がスクリーニングを受け、847例が無作為に割り付けられた(ペムブロリズマブ群566例、プラセボ群281例)。2次中間解析(データカットオフは2019年12月11日)での追跡期間中央値は、ペムブロリズマブ群25.9ヵ月(IQR:22.8~29.9)、プラセボ群26.3ヵ月(22.7~29.7)だった。
CPS 10以上の患者群では、PFS期間中央値はペムブロリズマブ群9.7ヵ月、プラセボ群5.6ヵ月だった(病勢進行または死亡に関するハザード比[HR]:0.65、95%信頼区間[CI]:0.49~0.86、片側p=0.0012)。
CPS
1以上の患者群では、PFS期間中央値はそれぞれ7.6ヵ月、5.6ヵ月で有意差は示されなかった(HR:0.74、95%CI:0.61~0.90、片側p=0.0014)。ITT集団では、それぞれ7.5ヵ月、5.6ヵ月だった(0.82、0.69~0.97、有意性の検定は未実施)。
ペムブロリズマブの治療効果として、PD-L1誘発の増大が確認された。
Grade3~5の治療関連有害イベントの発生率は、ペムブロリズマブ群68%、プラセボ群67%だった。そのうち、死亡はペムブロリズマブ群1%未満、プラセボ群0%だった。
(医療ジャーナリスト 當麻 あづさ)
【原著論文はこちら】
Cortes J, et al. Lancet. 2020;396:1817-1828.
掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。
(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。)