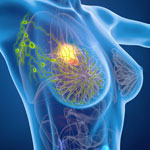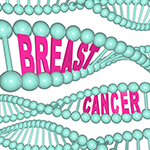提供元:CareNet.com

乳がんの遺伝性の病原性バリアントを有する女性のリスク評価と管理では、がん素因遺伝子の生殖細胞系列の病原性バリアントと関連する、集団ベースの乳がんリスクの推定がきわめて重要とされる。米国・メイヨークリニックのChunling Hu氏らCARRIERS(Cancer Risk Estimates Related to Susceptibility)コンソーシアムは、同国の一般集団において、既知の乳がん素因遺伝子の病原性バリアントと関連する乳がんの有病率とリスクの評価を行った。その結果、BRCA1とBRCA2の病原性バリアントは乳がんリスクが最も高いことを示した。NEJM誌オンライン版2021年1月20日号掲載の報告。
米国の集団ベースの症例対照研究
同コンソーシアムは、乳がん女性3万2,247例(乳がん診断時平均年齢62.1歳、乳がん家族歴あり20.4%)と、マッチさせた非乳がん女性(対照)3万2,544例(試験登録時平均年齢61.2歳、乳がん家族歴あり14.3%)を対象に、集団ベースの症例対照研究を行った(米国国立衛生研究所[NIH]と乳がん研究財団[BCRF]の助成による)。
多遺伝子アンプリコンベースのカスタムパネルを用いてシークエンスを行い、28のがん素因遺伝子の生殖細胞系列の病原性バリアントを同定した。次いで、個々の遺伝子の病原性バリアントと乳がんリスクの関連を評価した。
BRCA1と2バリアントの生涯乳がんリスクは約50%
12の確立された乳がん素因遺伝子の病原性バリアントが、乳がん群の5.03%(1,621例)および対照群の1.63%(531例)で検出された。
BRCA1とBRCA2の病原性バリアントは乳がんリスクが最も高く、BRCA1のオッズ比(OR)は7.62(95%信頼区間[CI]:5.33~11.27、p<0.001)、BRCA2のORは5.23(4.09~6.77、p<0.001)だった。また、PALB2の病原性バリアントの乳がんリスクは中等度(OR:3.83、2.68~5.63)であった。
BRCA1、BRCA2、およびPALB2の病原性バリアントはいずれも、エストロゲン受容体陽性乳がん(OR[95%CI]:BRCA1 3.39[2.17~5.45]、BRCA2 4.66[3.52~6.23]、PALB2
3.13[2.02~4.96])、同陰性乳がん(26.33[17.28~41.52]、8.89[6.36~12.47]、9.22[5.63~15.25])、およびトリプルネガティブ乳がん(42.88[26.56~71.25]、9.70[5.97~15.47]、13.03[7.08~23.75])のリスクが高かった。
一方、BARD1(OR[95%CI]:2.52[1.18~5.00])、RAD51C(2.19[0.97~4.49])、およびRAD51D(3.93[1.40~10.29])の病原性バリアントはエストロゲン受容体陰性乳がんのリスクが高く、BARD1(3.18[1.16~7.42])はトリプルネガティブ乳がんのリスクも高かったのに対し、ATM(1.96[1.52~2.53])、CDH1(3.37[1.24~10.72])、およびCHEK2(2.60[2.05~3.31])はエストロゲン受容体陽性乳がんのリスクが増大していた。
ミスマッチ修復遺伝子(MLH1、MSH2、MSH6)やNBNを含む16の乳がん素因遺伝子候補は、いずれも乳がんリスクの増加とは関連がなかった。また、BRCA1とBRCA2の病原性バリアントの生涯乳がんリスクは約50%で、PALB2は約32%だった。
著者は、「これらの知見は、一般集団におけるがん素因遺伝子の病原性バリアントを有する女性において、がんのスクリーニングやリスク管理戦略に有益な情報をもたらすと考えられる」としている。
(医学ライター 菅野 守)
【原著論文はこちら】
Hu C, et al. N Engl J Med. 2021 Jan 20. [Epub ahead of print]