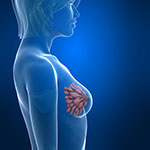提供元:CareNet.com
COVID-19感染拡大の影響により延期されていた第28回日本乳癌学会学術総会が、10月9日(金)~31日(土)にWEB開催される。9月17日にプレスセミナーが開催され、総会会長を務める岩田 広治氏(愛知県がんセンター 副院長・乳腺科部長)、事務局長を務める澤木 正孝氏(同乳腺科医長)らが見どころについて紹介した。
開催スケジュール
10月9日(金)~31日(土) 完全WEB開催(共催セミナーのほか、パネルディスカッションや教育講演のオンデマンド配信などが期間を通じて閲覧可能)
10月9日(金)~18日(日) LIVE配信
10月13日(火)~15日(木) 厳選口演(LIVE)
厳選口演の注目トピック
厳選口演では、応募総数1,938演題の中から採用された51題(2.6%)が発表される。それぞれLIVE配信後に、後日オンデマンド配信が行われる予定。澤木氏は、全13セッションの注目トピックについて解説した。ここでは、外科/薬物/放射線療法の各トピックを抜粋して紹介する。
・厳選口演1:外科療法[10月13日(火)9:30~10:30]
全乳房切除から部分切除、腋窩郭清からセンチネルリンパ節生検へとさらなる手術縮小を目指した研究成果が発表予定。
・厳選口演2:オンコプラスティックサージェリー・乳房再建[10月13日(火)11:00~11:45]
両側同時再建、部分再建、内視鏡手術での再建の工夫やNSMの新たな適応基準など。
・厳選口演6:薬物療法1[10月14日(水)9:30~10:45]
進行乳がんに対するwPTX+BV導入療法後のホルモン維持療法の有用性(JBCRG BOOSTER試験)
転移再発乳癌におけるパクリタキセル+ベバシズマブ導入化学療法後のホルモン療法+カペシタビン併用維持療法
乳癌周術期化学療法時の脱毛軽減目的での頭皮冷却後の毛髪回復状況を調べた前向き研究結果
・厳選口演7:薬物療法2[10月14日(水)11:00~12:00]
HER2陽性転移性乳癌におけるT-DM1治療直後の薬物療法の有効性:KBCSG-TR1917観察研究
転移性HER2陽性乳癌に対するT-DM1後の治療の臨床効果に関する多施設共同コホート研究(WJOG12519B)
HER2陽性進行乳癌患者を対象としたDS-8201のfirst-in-human第1相試験及び第2相試験(DESTINY-Breast01)における併合解析及び日本人サブセット解析
・厳選口演8:薬物療法3[10月14日(水)13:00~13:45]
ホルモン受容体陽性乳癌の術後内分泌療法におけるS-1の併用効果(POTENT試験)
Pembrolizumab+Chemotherapy vs Chemotherapy in Metastatic TNBC:KEYNOTE-355 Japanese Subgroup Data
NTRK fusion陽性乳がんにおけるエヌトレクチニブ:3つの国際共同第1/2相試験の統合解析
・厳選口演13:放射線療法[10月15日(木)14:15~15:30]
本邦乳癌患者に対する小線源を用いた乳房部分照射における観察期間中央値5年の治療成績と再発形式の特徴
早期乳癌に対する乳房温存手術+術中放射線部分照射:10年の結果
早期乳癌に対する炭素イオン線治療の臨床試験の経過
今年のESMOでの発表を徹底議論
10月12日(月)16:00~18:00には、9月に開催された欧州臨床腫瘍学会(ESMO Virtual Congress 2020)での乳がん領域の注目トピックについて議論する緊急特別企画がLIVE配信される(後日オンデマンド配信予定)。
・セッション1
1)Impassion 131:TN 1st line, PD-L1+でAtezo+Nab paclitaxelのfinal OS
2)Impassion 130:TN 1st lineでAtezo+weekly Pがnegative data
3)ASCENT study:TN late lineで、Satizumab govitecan(SG)のP3 dataの発表
・セッション2
4)Impassion 031:TN neoadjuvantで、Atezoを加えて、pCRが有意にアップ
5)PALLAS study:Palboのadjuvant study negative data
6)MONARCH E study:Abemaのadjuvant positive data
WEB上で“直接議論できる場”複数、ZOOMでオフ会も
本来、本総会はAichi Sky Expoにおいて7月に開催予定であった。医師だけでなく、患者さんも含め全員で最新情報を共有・議論したいという意図から、通常のようにいくつもの会場を設けず、「2つのメイン会場を中心に、できるだけ仕切りを設けず、広い場所のいたるところで人が集まり議論をするというイメージで計画していた」と岩田氏。完全WEB開催となったが、その利点を生かして、演者や海外の先生方と直接議論・交流ができるような場がいくつか設けられている。
・Meet the Expert[10月14日(水)、15日(木)8:00~9:00、16:00~17:00]
7名の先生と学会参加者が少人数で直接交流できる。※9月23日より若干名の追加登録開始。締切の可能性あり。
・ポスターツアー[10月14日(水)、15日(木)9:00~11:00]
68名の先生が“ツアーコンダクター”となり、各6演題を厳選し、参加者とともにポスターの閲覧・演者との議論を行う初の企画。※9月23日より若干名の追加登録開始。締切の可能性あり。
・オフ会(ZOOMで飲み会)[10月12日(月)~15日(木)20:30~22:00]
岩田会長は毎日参加予定。MC数名は毎日交代で行われる。
第28回日本乳癌学会学術総会
(ケアネット 遊佐 なつみ)
掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。
(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。)