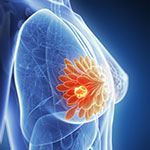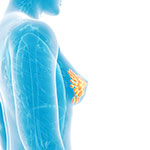提供元:CareNet.com

乳がん発症リスクが高い閉経後女性において、アナストロゾールの予防効果は投与終了後も長期にわたり維持されており、新たな遅発性の副作用は報告されなかったことが、英国・ロンドン大学クイーン・メアリー校のJack Cuzick氏らによる長期追跡試験「IBIS-II試験」で示された。「MAP.3」および「IBIS-II」の2件の大規模臨床試験において、アロマターゼ阻害薬投与後最初の5年間で高リスク女性の乳がん発症率が低下することが報告されていたが、アナストロゾール投与終了後の長期的な乳がん発症率についてはこれまで不明であった。Lancet誌オンライン版2019年12月12日号掲載の報告。また同日、サンアントニオ乳がんシンポジウム(SABCS2019)にて発表された。
乳がん発症高リスク閉経後女性約3,900例で、アナストロゾール5年投与による乳がん発症率をプラセボと比較
IBIS-II試験(International Breast Cancer Intervention Study II)は、乳がん高リスク閉経後女性におけるアナストロゾールの乳がん(浸潤性乳がんまたは非浸潤性乳管がん)に対する発症予防効果および安全性を評価する、国際多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照試験である。
研究グループは、2003年2月2日~2012年1月31日の間に、40~70歳の乳がん発症高リスク閉経後女性(一般女性に対する乳がん相対リスクが40~44歳は4倍以上、45~60歳は2倍以上、60~70歳は1.5倍以上)3,864例を、アナストロゾール(1mgを1日1回経口投与)群(1,920例)またはプラセボ群(1,944例)に1対1の割合で無作為に割り付け、それぞれ5年間投与した。
治療完遂後、年1回追跡調査を行い、乳がん発症、死亡、その他のがんの発症、主要有害事象(心血管イベントおよび骨折)に関するデータを収集した。主要評価項目は、すべての乳がん発症で、Cox比例ハザードモデルを用いてintention-to-treat解析を行った。
アナストロゾール群で追跡期間約11年の乳がん発症率が49%低下
追跡期間中央値131ヵ月(IQR:105~156)において、乳がん発症率はアナストロゾール群で49%減少した(85例vs.165例、ハザード比[HR]:0.51、95%信頼区間[CI]:0.39~0.66、p<0.0001)。
乳がん発症率の低下は、最初の5年間が大きかったが(35例vs.89例、HR:0.39、95%CI:0.27~0.58、p<0.0001)、5年以降も有意であり(新規発症例:50例vs.76例、HR:0.64、95%CI:0.45~0.91、p=0.014)、最初の5年間と5年以降とで有意差はなかった(p=0.087)。
エストロゲン受容体陽性浸潤性乳がんの発症率は54%低下し(HR:0.46、95%CI:0.33~0.65、p<0.0001)、治療完遂後に有意な効果が持続した。非浸潤性乳管がんは59%低下し(HR:0.41、95%CI:0.22~0.79、p=0.0081)、とくにエストロゲン受容体陽性で著しかった(HR:0.22、95%CI:0.78~0.65、p<0.0001)。
観察された全死亡(69例vs.70例、HR:0.96、95%CI:0.69~1.34、p=0.82)、または乳がん死亡(2例vs.3例)について、両群で有意差は確認されなかった。非乳がんの発症率は、アナストロゾール群で有意な低下が確認され(147例vs.200例、オッズ比:0.72、95%CI:0.57~0.91、p=0.0042)、とくに非黒色腫皮膚がんの発症率低下が大きかった。
骨折または心血管疾患のリスク増加は確認されなかった。
結果を踏まえて著者は、「さらなるフォローアップを行い、乳がん死亡への効果を評価することが必要だ」と述べている。
(医学ライター 吉尾 幸恵)
【原著論文はこちら】