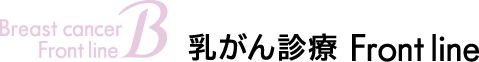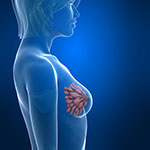提供元:CareNet.com

近年、腫瘍循環器学という新しい概念が提唱されている。10月24日~11月1日にWeb開催された第30回日本医療薬学会総会のシンポジウム「腫瘍循環器(Onco-Cardiology)学を学ぼう~タスクシェア・シフト時代にマネジメントする薬剤師力の発揮~」において、腫瘍循環器領域の第一人者である向井 幹夫氏(大阪国際がんセンター成人病ドック科主任部長)が「腫瘍循環器学とは?臨床現場で薬剤師に求めること」と題し、腫瘍循環器学における新たな視点について語った。
がん治療の進歩で注意すべき心血管リスクも変化
がん患者の心血管リスクは、がん治療時の急性期/慢性期心毒性をピークに回復・寛解期には一度低下傾向を示す。しかし、転移・再発に対するがん治療の開始やがんサバイバーとして生き長らえる中で、潜在的心血管リスクの増悪による晩期心毒性によりリスクは再び上向きに転じることが報告1)されている。向井氏はその1つとして、28種がんのがんサバイバーの治療経過と心臓病による死亡リスクの検討2)から、がん診断後から5~10年の時点で全領域のがんサバイバー、なかでも乳がん、皮膚がん(メラノーマ)、前立腺がん患者などの死亡リスクが上昇する報告を示した。同氏は「新規薬剤によるがん治療の進歩とそれに伴う生存率上昇の反面、心毒性が増加していることが影響している」と述べ、最新のがん治療にも心血管リスクが潜んでいる点を指摘した。
投与終了後の経過観察は生涯必要
がん治療による心毒性・心血管リスクの歴史は1970年代に遡る。殺細胞系抗がん剤アントラサイクリンによる心筋症が明らかになって以降、2000年代には分子標的薬のトラスツズマブにより生じる心筋症が、近年では免疫チェックポイント阻害薬による劇症心筋炎と心血管合併症が問題になっている。さらに、血管新生阻害薬(抗VEGF薬)は心毒性リスクが投与用量に比して増加し、かつ経時的に変化する特徴があり、投与初期には毛細血管攣縮による血圧上昇、数ヵ月後に毛細血管循環障害(密度希薄化)による高血圧症や尿蛋白が出現する。その後、年単位の治療が継続されることでプラーク形成による血栓症・出血が発生し、3~5年の長期治療によって心筋梗塞や脳梗塞などの重篤な心血管疾患発症に至る。このような症例を実際に目の当たりにした同氏は「がん治療が進歩する一方でこれまでにない晩期合併症が増加している」と危惧した。
心毒性発症の原因は多様性を示し、がん自体の作用、心血管疾患の既往、ゲノムの関与、そしてがん治療が影響していることから、「心毒性に対し循環器医の介入はもちろんのこと実際に薬剤を扱う薬剤師も、近年頻度が増加しているがん関連血栓症や動脈硬化血管障害(虚血性心疾患)、不整脈などを幅広く理解しておく必要がある」とも述べた。
がんと循環器疾患の共通点、危険因子と発症機序
がんの危険因子を列挙すると循環器疾患の危険因子との共通項目が非常に多く、たとえば、喫煙、飲酒、食塩摂取、運動不足などが挙げられる。また、がんと動脈硬化発症の機序において、腫瘍が増殖する際の血管新生に影響を及ぼすVEGFは、循環器領域ではプラーク形成にかかわる血管新生や血管内皮障害を起こす。そのほかにもがんの進展と動脈硬化の発症メカニズムには多くの共通点が指摘されており3)、同氏は「遠い存在であったがんと循環器は共通の性格を持つ疾患である」とし、「いずれも生活習慣病として、遺伝子的因子、エピジェネティク因子、環境因子、生活習慣などが原因で酸化ストレス、炎症、増殖、アポトーシス、血管新生などを生じ動脈硬化やがんに発展する。心不全や血栓症などの晩期心毒性はこれらの危険因子を抑えることで発症予防につながることが期待されている」と話した。
薬剤師によるがんサバイバーへの貢献に期待
このようにがんと循環器のリスクの共通性が解明される一方、増加するがんサバイバーへの対応は現在模索中である。しかし、がん診療をがん発症予防、診断と治療計画、がん治療、がんサバイバーの4つのステージに分けて考えた時、どのステージにおいてもこれから薬剤師が活躍すると同氏は期待を寄せる。とくにがん治療が終わった後のがんサバイバーは、自分を知っていてくれるかかりつけ薬剤師に調剤薬局やドラッグストアで接することになる。そこでは、がんサバイバーが直面する晩期合併症、なかでも晩期心毒性に対応するためにがん診療における薬薬連携による情報交換と幅広い理解が求められている。
最後に同氏は「腫瘍循環器学を学び、がんと循環器の共通点を知りタスクシフト・シェア時代に対応することで、がんサバイバーの不安を軽減し支援することができるよう薬剤師の皆さまに“薬剤師力”を発揮していただきたい」と締めくくった。
(ケアネット 土井 舞子)
【参考文献・参考サイトはこちら】
1)Okura Y, et al. Circ J. 2019;83:2191-2202.
2)Sturgeon KM, et al. Eur Heart J. 2019;40:3889-3897.