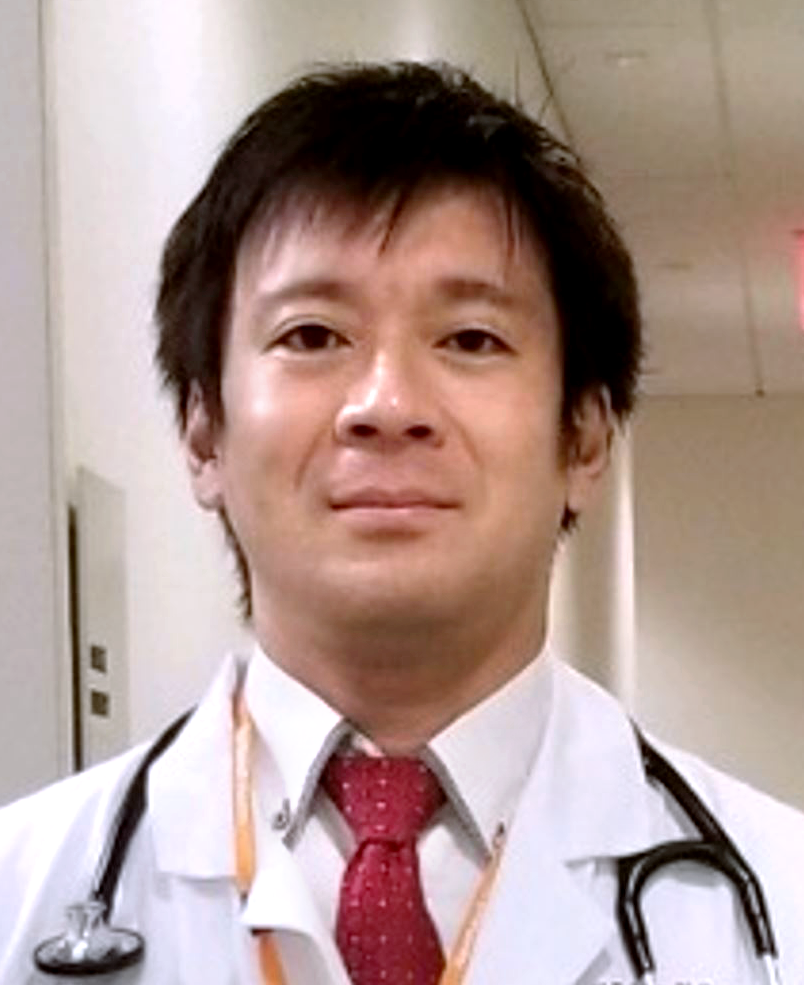提供元:CareNet.com

本連載は、臨床研究のノウハウを身につけたいけれど、メンター不在の臨床現場で悩める医療者のための、「実践的」臨床研究入門講座です。臨床研究の実践や論文執筆に必要な臨床疫学や生物統計の基本について、架空の臨床シナリオに基づいた仮想データ・セットや、実際に英語論文化した臨床研究の実例を用いて、解説していきます。
診療ガイドラインとは
各専門分野の診療ガイドラインは、日本医療機能評価機構が運営するMinds*1ガイドラインライブラリで検索することができます。診療ガイドラインはMindsでは以下のように定義されています。「診療上の重要度の高い医療行為について、エビデンスのシステマティック・レビューとその総体評価、益と害のバランスなどを考量して、患者と医療者の意思決定を支援するために最適と考えられる推奨を提示する文書」1)。Mindsガイドラインライブラリでは無料で閲覧できない診療ガイドラインもありますが、ご自身のRQに関連する先行研究をレビューする際に、まずはじめにチェックしてみる価値のある質の高い2次情報源です。
*1:Medical Information Distribution Service
診療ガイドラインを活用した関連研究レビューの実際
近年の診療ガイドラインは、1)クリニカル・クエスチョン(CQ)および、2)CQに対する回答の提示とその推奨グレード、という2段階構造で記述されています。下記は本連載で、これまでに作成してきた架空の臨床シナリオに基づいたCQです。
CQ:食事療法(低タンパク食)を遵守すると慢性腎臓病患者の腎予後は改善するのだろうか
↓
P:慢性腎臓病患者
E:食事療法(低タンパク食)の遵守
C:食事療法(低タンパク食)の非遵守
O:腎予後
例えば、このCQに関連した診療ガイドラインを、まずはPである「慢性腎臓病」をキーワードにMindsガイドラインライブラリで探してみましょう。すると、「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2018」2)が検索結果の筆頭に挙げられてきます。
この診療ガイドラインの目次を見てみると、「第3章 栄養」のセクションで列記されているCQの中に、われわれのCQにかなり合致した下記の記載が見つかります。
CQ:CKD の進行を抑制するためにたんぱく質摂取量を制限することは推奨されるか?
↓
推奨:CKD の進行を抑制するためにたんぱく質摂取量を制限することを推奨する。ただし、画一的な指導は不適切であり、個々の患者の病態やリスク、アドヒアランスなどを総合的に判断し、腎臓専門医と管理栄養士を含む医療チームの管理の下で行うことが望ましい (推奨グレード B 1)。
推奨グレードは1)そのCQに対する回答の依拠するエビデンスの質と2)推奨の強さによって構成されます。推奨グレードの決定も含め、診療ガイドラインの作成にGRADE*システム3, 4)という手法を用いることが、現在では世界標準となっています。GRADEシステムでは、1)エビデンスの質および2)推奨の強さが、下記のとおり、それぞれ4段階と2段階に格付けされています4)。
*2:Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation
1)エビデンスの質
A(高) :真の効果が効果推定値に近いことに大きな確信がある。
B(中) :効果推定値に対し中等度の確信がある。
C(低) :効果推定値に対する確信性には限界がある。
D(非常に低い):効果推定値に対し、ほとんど確信がもてない。
2)推奨の強さ
1:強い推奨:推奨する。
2:弱い/条件付き推奨:提案する。
この診療ガイドラインで挙げられた前述のCQに対する回答の内容は推奨グレードB1ですので、根拠となるエビデンスの質は中等度であるが強く推奨する、という意味合いになります。次回は、このCQに関する本文の解説を読み込んで、われわれが行う臨床研究で新たなエビデンスを積み上げる余地(ニッチ)があるかどうかを検討してみたいと思います。
【 引用文献 】
1 )福井次矢、山口直人 監修.Minds診療ガイドライン作成の手引き2014.医学書院.2014.
2 )日本腎臓学会編集.エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2018, 東京医学社.
3 )Guyatt G et al. J Clin Epidemiol. 2011;64:383-94.
4 )診療ガイドラインのためのGRADEシステム 第3版.中外医学社
【 参考文献 】
1)福原俊一. 臨床研究の道標 第2版. 健康医療評価研究機構;2017.
2)木原雅子ほか訳. 医学的研究のデザイン 第4版. メディカル・サイエンス・インターナショナル;2014.
3)矢野 栄二ほか訳. ロスマンの疫学 第2版. 篠原出版新社;2013.
4)中村 好一. 基礎から学ぶ楽しい疫学 第4版. 医学書院;2020.
5)片岡 裕貴. 日常診療で臨床疑問に出会ったときに何をすべきかがわかる本 第1版.中外医学社;2019.
講師紹介

長谷川 毅 ( はせがわ たけし ) 氏
昭和大学統括研究推進センター研究推進部門 教授
昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門/衛生学公衆衛生学講座 兼担教授
福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター 特任教授
[略歴]
1996年昭和大学医学部卒業。
2007年京都大学大学院医学研究科臨床情報疫学分野(臨床研究者養成コース)修了。
都市型および地方型の地域中核病院で一般内科から腎臓内科専門診療、三次救急から亜急性期リハビリテーション診療まで臨床経験を積む。その臨床経験の中で生じた「臨床上の疑問」を科学的に可視化したいという思いが募り、京都の公衆衛生大学院で臨床疫学を学び、米国留学を経て現在に至る。
バックナンバー
39. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その2
38. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その1
37. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その2
36. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その1
35. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その2
34. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その1
33. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その8
32. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その7
31. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その6
30. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その5
29. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その4
28. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その3
27. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その2
26. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その1
25. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その5
24. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その4
23. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その3
22. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その2
21. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その1
20. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その3
19. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その2
18. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その1
17. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その3
16.リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その2
15. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その1
14. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その3
13. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その2
12. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用その1
11. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その2
10. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その1
9. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その3
8. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その2
7. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その1
6. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その3
5. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その2
4. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その1
3. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビューその2