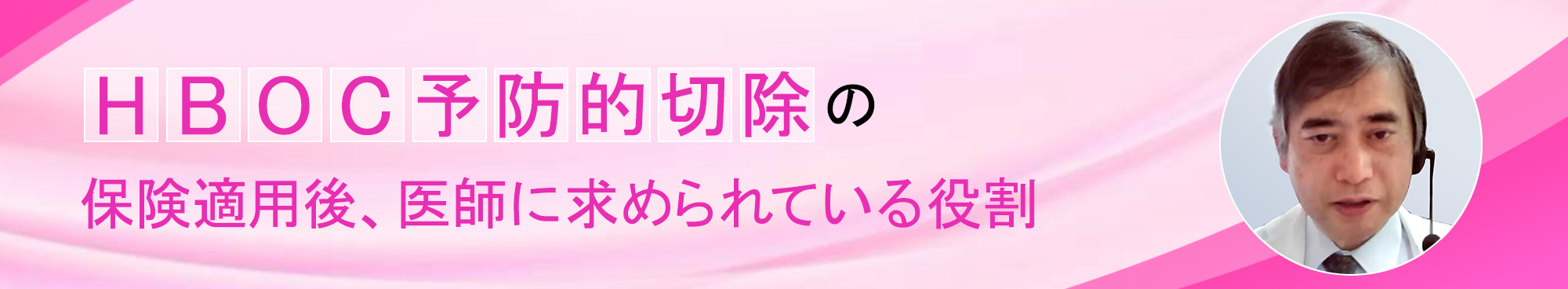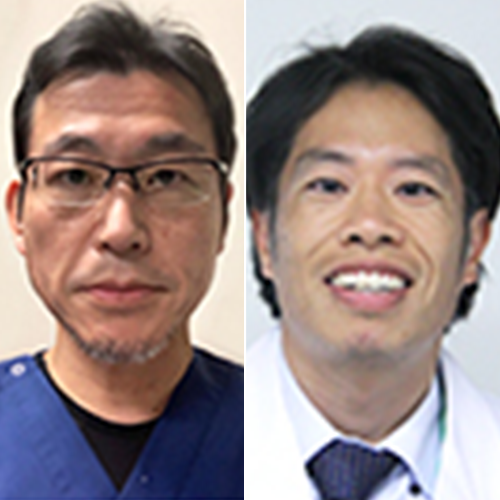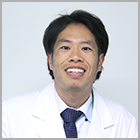提供元:CareNet.com

本連載は、臨床研究のノウハウを身につけたいけれど、メンター不在の臨床現場で悩める医療者のための、「実践的」臨床研究入門講座です。臨床研究の実践や論文執筆に必要な臨床疫学や生物統計の基本について、架空の臨床シナリオに基づいた仮想データ・セットや、実際に英語論文化した臨床研究の実例を用いて、解説していきます。
文献管理ソフト活用のススメ
これまでの連載第4回から第6回では、関連研究レビューのはじめのステップとして、診療ガイドラインの活用法について解説しました。すでにこの時点で、架空の臨床シナリオに基づいたわれわれのリサーチ・クエスチョン(RQ)に関連する先行研究論文が10編以上リストアップされています。学会発表にとどまらず英文原著論文出版まで見据えると、関連研究文献の管理はRQをブラッシュアップする段階から始めたいものです。
何はともあれ、関連研究文献の管理には、文献管理ソフトの活用を強くお勧めします。文献管理ソフトを使うことにより、関連研究の文献情報の収集や閲覧を一元的に管理することができます。単に関連研究論文PDFをパソコンにダウンロードしフォルダに保存しただけでは、参照したい時に、お目当ての論文を探し出すだけでも時間を浪費します。文献管理ソフトでは、収集した文献それぞれの論文タイトル、著者情報、アブストラクト、そしてフルテキストPDF(入手可能な場合)を一元的に管理し閲覧することができます。
それだけでなく、文献管理ソフトは論文執筆の際の引用文献リスト(レファレンス)の作成に大変役立ちます。レファレンスは専門雑誌ごとにそのフォーマットが異なります。したがって、投稿論文がリジェクトされてしまい投稿先の雑誌を変更する度に、フォーマット調整が必要となります。手動でこのような編集をするのには多大な労力がかかりますが、文献管理ソフトを用いるとこの作業がほぼ自動化でき、とても便利です。
文献管理ソフト活用の実際
文献管理ソフトは近年多くのアプリケーションが出てきていますが、筆者はロングセラーの文献管理ソフトで、現在でもスタンダードとされているEndNote®を使用しています。EndNote®は30日間無料トライアル版もありますので、ここではEndNote®を例として、筆者の文献管理ソフトの使い方を簡単に説明させていただきます。
まずは、第6回でリストアップした引用文献を文献管理ソフトウエアにとりこんでみましょう。はじめに、EndNote®を起動して新規ライブラリを作成し、パソコンの任意の場所にライブラリファイルを保存します。次に、第3回で少し触れましたが、関連研究論文の1次情報源としてPubMedを使用します。PubMedのトップページの画面中央の”Find”という項目の下に[Single Citation Matcher]というリンクがあります。引用文献の記載のとおり、書誌情報(雑誌名、出版年、巻、号、最初のページ、など)を入力すると該当する文献がヒットします。その画面上部にある[Send To]をクリックし、プルダウンから[Citation manager]を選択、[Create File]をクリックします。EndNote®を起動した状態で保存されたファイルを開くと、現在開いているライブラリに文献情報(レコード)が取り込まれます。
さらに、EndNote®の[Find Full Text]機能を使うと、ワンクリックでオンライン公開されているフルテキストPDFを検索、自動ダウンロードされ、レコードに添付されます。PDFがダウンロードされるのではなく、フルテキストにアクセス可能なURLがレコードに追加される場合もあります。その場合はそのURLのリンクを開き、フルテキストPDFをダウンロードしてレコードにドラッグ&ドロップすることにより添付できます。大学などの所属施設のネットワークに接続していると、オープンアクセスジャーナルだけでなく、所属施設の図書館などが機関契約している電子ジャーナルから、フルテキストPDFが自動ダウンロードできる場合もあります。
上記の工程を行うことにより、収集した文献それぞれの書誌情報、アブストラクト、フルテキストPDF(入手可能な場合)を一覧できるようになります。次回は、この一覧化した文献情報の関連研究レビューでの活かし方について解説したいと思います。
講師紹介

長谷川 毅 ( はせがわ たけし ) 氏
昭和大学統括研究推進センター研究推進部門 教授
昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門/衛生学公衆衛生学講座 兼担教授
福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター 特任教授
[略歴]
1996年昭和大学医学部卒業。
2007年京都大学大学院医学研究科臨床情報疫学分野(臨床研究者養成コース)修了。
都市型および地方型の地域中核病院で一般内科から腎臓内科専門診療、三次救急から亜急性期リハビリテーション診療まで臨床経験を積む。その臨床経験の中で生じた「臨床上の疑問」を科学的に可視化したいという思いが募り、京都の公衆衛生大学院で臨床疫学を学び、米国留学を経て現在に至る。
バックナンバー
39. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その2
38. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その1
37. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その2
36. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その1
35. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その2
34. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その1
33. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その8
32. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その7
31. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その6
30. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その5
29. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その4
28. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その3
27. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その2
26. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その1
25. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その5
24. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その4
23. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その3
22. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その2
21. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その1
20. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その3
19. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その2
18. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その1
17. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その3
16.リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その2
15. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その1
14. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その3
13. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その2
12. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用その1
11. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その2
10. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その1
9. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その3
8. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その2
7. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その1
6. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その3
5. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その2
4. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その1
3. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビューその2