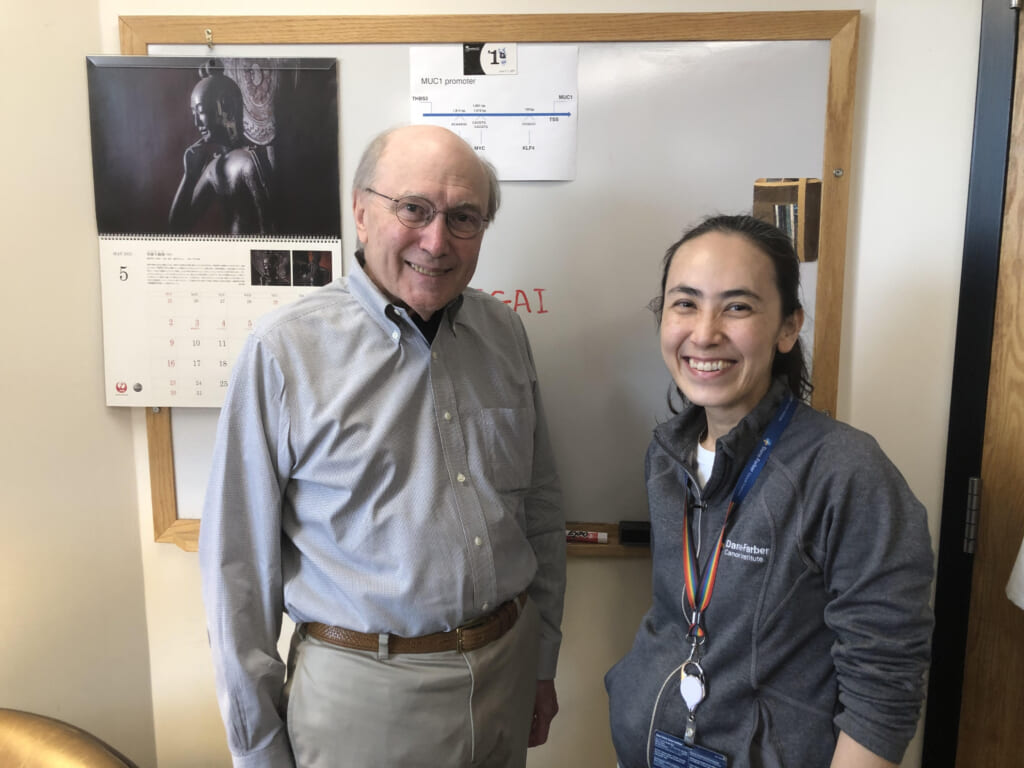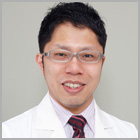提供元:CareNet.com

本連載は、臨床研究のノウハウを身につけたいけれど、メンター不在の臨床現場で悩める医療者のための、「実践的」臨床研究入門講座です。臨床研究の実践や論文執筆に必要な臨床疫学や生物統計の基本について、架空の臨床シナリオに基づいた仮想データ・セットや、実際に英語論文化した臨床研究の実例を用いて、解説していきます。
UpToDate®―該当トピックの本文を読み込んでみる
CQ:食事療法を遵守すると慢性腎臓病患者の腎予後は改善するのだろうか
↓
P:慢性腎臓病(CKD)患者
E:食事療法(低たんぱく食 0.5g/kg標準体重/日)の遵守
C:食事療法(低たんぱく食 0.5g/kg標準体重/日)の非遵守
O:腎予後
前回、これまでブラッシュアップしてきた、上記のCQとRQ(PECO)に関連するUpToDate®のトピックを検索したところ、
人工透析を受けていない慢性腎臓病患者に推奨する食事療法
Dietary recommendations for patients with nondialysis chronic kidney disease
がヒットしました。このトピックには、”PROTEIN INTAKE(たんぱく質摂取量)”という項があり、われわれのRQに関連する先行研究について概説されていそうです。 該当トピックの解説を読み込む前に、このトピックの更新日付を確認してみましょう。トピックの標題の直下に、担当著者・編集者の氏名が明記されており、
“All topics are updated as new evidence becomes available and our peer review process is complete.”
「すべてのトピックは新しいエビデンスが入手可能になりわれわれのピア・レビューが完了すると更新されます(筆者による意訳)。」
とのコメントとともに、
Literature review current through:May 2021. |This topic last updated:Feb 21, 2020.
との記載があります。本稿執筆時点(2021年7月)では、このトピックの関連文献レビューは2021年5月まで行っているが、このトピック本文の最終更新日は2020年2月21日である(筆者による意訳)、ということです。UpToDate®では、その分野の信頼できる専門家が年3回は関連研究レビューを行って都度改訂し、まさに”up-to-date”な2次情報を提供してくれているのです。
今回は、このトピックの”PROTEIN INTAKE(たんぱく質摂取量)”の項を読み込んで、RQのさらなるブラッシュアップに活かしたいと思います。その概要を以下のようにまとめてみました(筆者による抜粋、意訳)。
・対象(P)をネフローゼ症候群患者*と非ネフローゼ症候群患者に分けて記述されている。
*成人ネフローゼ症候群の診断基準1)
1.尿たんぱく3.5g/日以上が持続する
2.低アルブミン血症:血清アルブミン値3.0g/dL以下
3.浮腫
4.脂質異常症(高LDLコレステロール血症)
1、2は診断必須条件、3、4は参考所見
ネフローゼ症候群患者ではたんぱく質摂取量制限は有効性、安全性、双方の観点から推奨しない、との記述があり、われわれのRQの対象(P)からも除外した方が良さそうです。したがって、下記のまとめは非ネフローゼ症候群患者を対象(P)にしぼった関連研究のレビューに基づいたものです。
・推定糸球体濾過量(eGFR)<60mL/分/1.73m2未満の保存期CKD患者ではたんぱく質摂取量は0.8g/kg標準体重/日以下に制限することが推奨される。
・ たんぱく質摂取制限はCKDの進行を遅延させる可能性があるが、その有益性は軽度であることが、ランダム化比較試験(randomized controlled trial:RCT)の結果から示唆されている2-7)。
・ たんぱく質摂取量は0.6g/kg標準体重/日までは安全性も保たれていることが示されているが8-10)、より厳格な低たんぱく質食事療法は長期的には死亡リスクの増加の懸念を示唆する研究報告3)もある。
・ これらのRCTの結果を統合(メタ解析)した、システマティック・レビュー11)でも、たんぱく質摂取制限が有益である可能性が示唆されている。
UpToDate®の記述からも、われわれが曝露要因(E)に設定している「厳格な」たんぱく質制限食(0.5g/kg標準体重/日)の臨床的有用性については、明確なエビデンスはないようです。また、UpToDate® が根拠とするエビデンスもRCTからの知見に基づいたものがほとんどであり、外的妥当性(連載第6回参照)の観点からも、われわれが行う観察研究にある程度の価値はありそうだと考えられます。また、上述したとおり、ネフローゼ症候群は対象(P)から除外するのが適切と判断し、冒頭のCQと RQ(PECO)を下記のように改訂しました。
CQ:食事療法を遵守すると非ネフローゼ症候群の慢性腎臓病患者の腎予後は改善するのだろうか
↓
P:非ネフローゼ症候群の慢性腎臓病(CKD)患者
E:食事療法(低たんぱく食 0.5g/kg標準体重/日)の遵守
C:食事療法(低たんぱく食 0.5g/kg標準体重/日)の非遵守
O:腎予後
次回からは、もうひとつの質の高い2次情報源である、コクラン・ライブラリーの活用方法について解説したいと思います。
【 引用文献 】
- 1)エビデンスに基づくネフローゼ症候群診断ガイドライン2020, 東京医学社.
- 2)Klahr S et al. N Engl J Med. 1994 Mar 31;330:877-884.
- 3)Menon V et al. Am J Kidney Dis. 2009 Feb;53:208-17.
- 4)Ihle BU et al.New Engl J Med. 1989 Dec 28;321:1773-7.
- 5)Cianciaruso B et al.Nephrol Dial Transplant. 2008 Feb;23:636-44.
- 6)Levey AS et al. Am J Kidney Dis.1996 May;27:652-63.
- 7)Locatelli F et al. Lancet. 1991 Jun 1;337:1299-304.
- 8)Kopple JD et al. Kidney Int.1997 Sep;52:778-91.
- 9)Aparicio M et al. J Am Soc Nephrol.2000 Apr;11:708-716.
- 10)Bernhard J et al. J Am Soc Nephrol. 2001 Jun;12:1249-1254.
- 11)Fouque D et al.Cochrane Database Syst Rev. 2020 Oct 29;10(10):CD001892.
講師紹介

長谷川 毅 ( はせがわ たけし ) 氏
昭和大学統括研究推進センター研究推進部門 教授
昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門/衛生学公衆衛生学講座 兼担教授
福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター 特任教授
[略歴]
1996年昭和大学医学部卒業。
2007年京都大学大学院医学研究科臨床情報疫学分野(臨床研究者養成コース)修了。
都市型および地方型の地域中核病院で一般内科から腎臓内科専門診療、三次救急から亜急性期リハビリテーション診療まで臨床経験を積む。その臨床経験の中で生じた「臨床上の疑問」を科学的に可視化したいという思いが募り、京都の公衆衛生大学院で臨床疫学を学び、米国留学を経て現在に至る。
バックナンバー
39. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その2
38. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その1
37. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その2
36. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その1
35. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その2
34. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その1
33. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その8
32. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その7
31. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その6
30. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その5
29. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その4
28. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その3
27. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その2
26. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その1
25. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その5
24. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その4
23. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その3
22. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その2
21. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その1
20. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その3
19. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その2
18. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その1
17. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その3
16.リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その2
15. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その1
14. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その3
13. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その2
12. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用その1
11. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その2
10. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その1
9. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その3
8. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その2
7. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その1
6. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その3
5. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その2
4. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その1
3. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビューその2