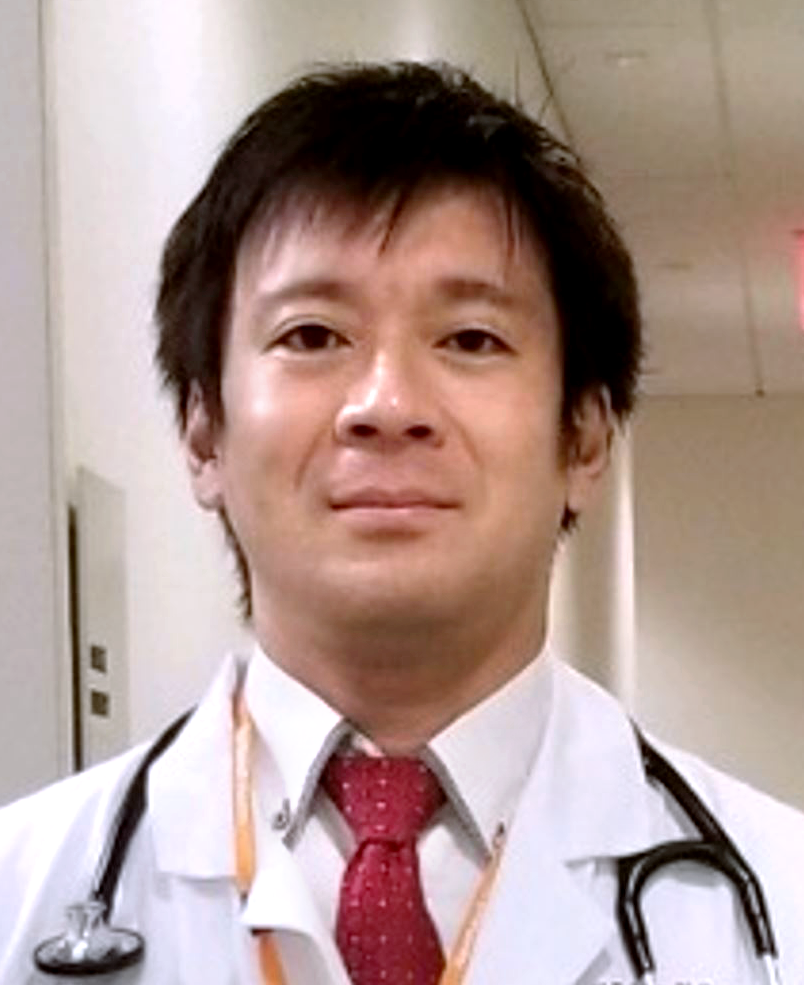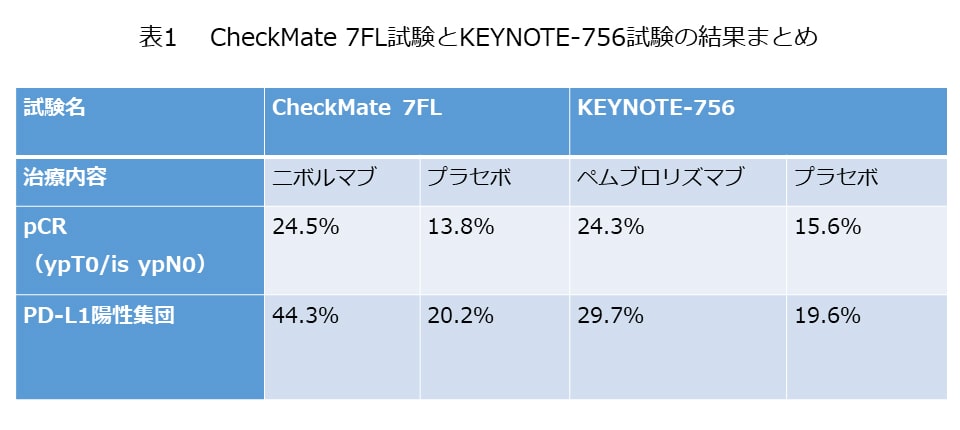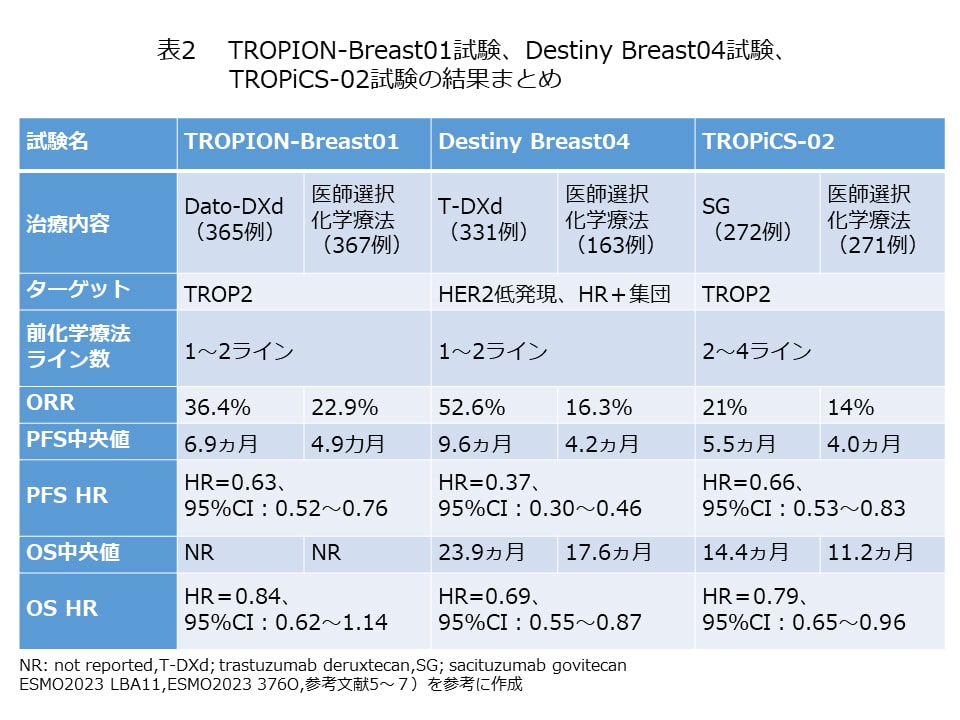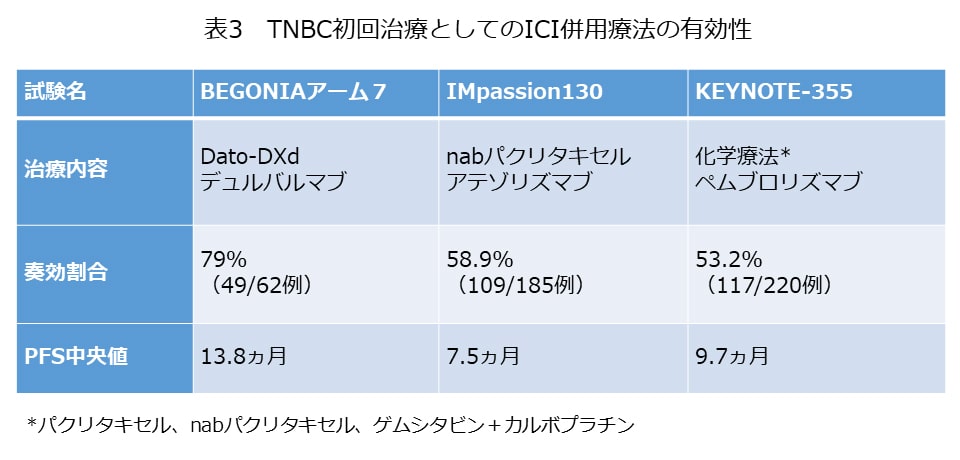提供元:CareNet.com

本連載は、臨床研究のノウハウを身につけたいけれど、メンター不在の臨床現場で悩める医療者のための、「実践的」臨床研究入門講座です。臨床研究の実践や論文執筆に必要な臨床疫学や生物統計の基本について、架空の臨床シナリオに基づいた仮想データ・セットや、実際に英語論文化した臨床研究の実例を用いて、解説していきます。
いきなり!多変量解析?
臨床研究における統計解析というと、みなさんはいきなり多変量解析を行ったり、臨床研究といえば多変量解析というようなイメージを持っていないでしょうか。重回帰分析、ロジスティック回帰分析、Cox回帰分析などの多変量解析のさまざまな手法を用いたことがある方や、学会などでこれらの統計解析手法を聞いたこと、論文で目にしたことがある方は多いでしょう。しかし、統計解析手法を正しく選択するためには、変数やアウトカム指標の型をよく知ることが必要となります。また、いきなり多変量解析に飛びつく前に、まずは変数やアウトカム指標の型を意識して正しく記述すること(記述統計)が重要です。
今回からは、具体的な統計解析手法について、筆者らが行い英文論文化された臨床研究の実例などを引用して解説します。また、架空の臨床シナリオを元に立案したClinical Question(CQ)とResearch Question(RQ)に基づいた仮想データ・セットを用いて、統計解析の実際についても実践的に説明したいと思います。
まずはここで、これまでブラッシュアップしてきたわれわれのRQの研究デザイン、セッティング、およびPECOについて整理します。
CQ:食事療法を遵守すると非ネフローゼ症候群の慢性腎臓病患者の腎予後は改善するのだろうか
D(研究デザイン):(後ろ向き)コホート研究
S(セッティング):単施設外来
P(対象):慢性腎臓病(CKD)患者
組み入れ基準:診療ガイドライン1)で定義されるCKD患者
除外基準:ネフローゼ症候群、透析導入(または腎移植)された患者
E(曝露要因):推定たんぱく質摂取量 0.5g/kg標準体重/日未満
C(比較対照):推定たんぱく質摂取量 0.5g/kg標準体重/日以上
*外来受診ごとに行った連続3回の24時間蓄尿検体を用いてMaroniの式より算出
O(アウトカム):1)末期腎不全(慢性透析療法への導入もしくは先行的腎移植)
*打ち切り(末期腎不全発症前の死亡、転院、研究参加同意撤回などによる研究からの離脱)
2)糸球体濾過量(GFR)低下速度
われわれのRQのプライマリアウトカムは末期腎不全であり、アウトカム指標はその発生率となります。発生率は下記の計算式で求められるのでした(連載第37回参照)。
発生率=一定の観察期間内のアウトカム発生数÷at risk集団の観察期間の合計
実際の臨床研究論文では、発生率は人年法という手法を用いて、1,000人を1年間観察すると(1,000人年)何件アウトカム(イベント)が発生したか、という形式で記述されることが多いです。
以下に、筆者らが2023年に出版した臨床研究論文2)の実際の記述を示します。CKD患者において血清鉄代謝マーカーの1つであるトランスフェリン飽和度(TSAT)レベルと心血管疾患(CVD)およびうっ血性心不全(CHF)の発生リスクの関連を検討した論文です。Resultsの”Incidence of outcome measures”という小見出しで以下のように記載しました。
“Supplementary Fig. S1 shows the incidence rates of CVD and CHF events based on serum TSAT levels. The overall incidence rates of CVD and CHF in the analysed participants were 26.7 and 12.0 events/1000 person-year, respectively. Participants with TSAT <20% had the highest incidence rates of CVD and CHF (33.9 and 16.5 events/1000 person-year, respectively). Conversely, the incidence rates of CVD and CHF were lowest in those with TSAT >40% (17.2 and 6.2 events/1000 person-year, respectively).”
「補足図S1は、血清TSAT値に基づくCVDおよびCHFイベントの発生率を示している。全解析対象者におけるCVDおよびCHFの発生率は、それぞれ26.7および12.0イベント/1,000人年であった。TSATが20%未満の参加者でCVDおよびCHFの発生率が最も高かった(それぞれ33.9と16.5イベント/1,000人年)。一方、CVDとCHFの発症率はTSATが40%以上の患者で最も低かった(それぞれ17.2および6.2イベント/1,000人年)。(筆者による意訳)」
この論文記載のポイントは、血清TSAT値20%未満(診療ガイドライン3)で鉄補充療法開始が推奨される基準値)のCKD患者において、CVDおよびCHFの発症率が最も高い、という記述統計の結果がまず示されたということです。
次回からは仮想データ・セットを用いて、具体的な統計解析方法についても解説をしていきます。
【 引用文献 】
- 1)日本腎臓学会編集. エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023. 東京医学社;2023.
- 2)Hasegawa T, et al. Nephrol Dial Transplant. 2023;38:2713-2722.
- 3)日本透析医学会編集.2015 年版 慢性腎臓病患者における腎性貧血治療のガイドライン.
講師紹介

長谷川 毅 ( はせがわ たけし ) 氏
昭和大学統括研究推進センター研究推進部門 教授
昭和大学医学部内科学講座腎臓内科学部門/衛生学公衆衛生学講座 兼担教授
福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター 特任教授
[略歴]
1996年昭和大学医学部卒業。
2007年京都大学大学院医学研究科臨床情報疫学分野(臨床研究者養成コース)修了。
都市型および地方型の地域中核病院で一般内科から腎臓内科専門診療、三次救急から亜急性期リハビリテーション診療まで臨床経験を積む。その臨床経験の中で生じた「臨床上の疑問」を科学的に可視化したいという思いが募り、京都の公衆衛生大学院で臨床疫学を学び、米国留学を経て現在に至る。
バックナンバー
39. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その2
38. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐E(要因)およびC(比較対照)設定の要点と実際 その1
37. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その2
36. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップ‐O(アウトカム)設定の要点と実際 その1
35. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その2
34. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップーP(対象)設定の要点と実際 その1
33. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その8
32. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その7
31. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その6
30. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その5
29. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その4
28. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その3
27. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その2
26. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 実際にPubMed検索式を作ってみる その1
25. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その5
24. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その4
23. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その3
22. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その2
21. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 1次情報源の活用 PubMed検索 その1
20. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その3
19. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その2
18. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 学術誌、論文、著者の影響力の指標 その1
17. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その3
16.リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その2
15. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー CONNECTED PAPERSの活用 その1
14. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その3
13. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用 その2
12. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー コクラン・ライブラリーの活用その1
11. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その2
10. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー UpToDateの活用その1
9. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その3
8. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その2
7. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 文献管理その1
6. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その3
5. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その2
4. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビュー 診療ガイドラインの活用その1
3. リサーチ・クエスチョンのブラッシュアップー関連研究レビューその2
掲載内容はケアネットの見解を述べるものではございません。
(すべての写真・図表等の無断転載を禁じます。)